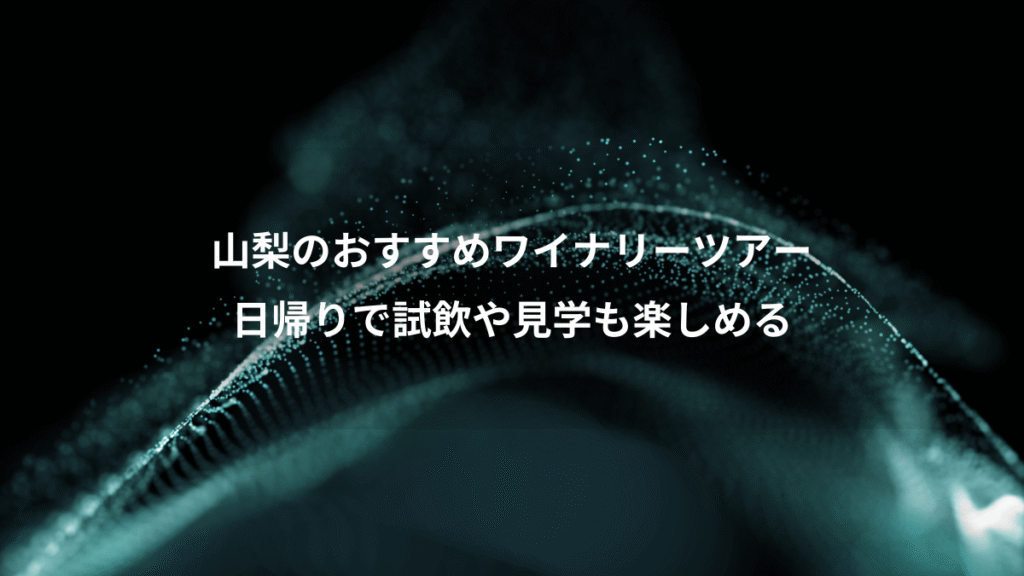日本が世界に誇るワインの銘醸地、山梨県。都心からのアクセスも良く、日帰りで気軽に訪れることができるため、ワイン愛好家はもちろん、初心者の方にも大変人気の観光地です。雄大な自然に囲まれたブドウ畑を散策し、造り手の情熱に触れながらテイスティングする一杯は、格別な味わいがあります。
しかし、山梨には数多くのワイナリーが存在するため、「どこに行けばいいのか分からない」「自分に合ったワイナリーはどう選べばいいの?」と迷ってしまう方も少なくありません。
この記事では、そんな方々のために、山梨のワイナリーツアーが持つ魅力の深掘りから、失敗しないワイナリーの選び方、日帰りでも満喫できるおすすめのワイナリー10選まで、網羅的にご紹介します。さらに、当日の服装や持ち物、アクセス方法、周辺の観光スポットまで詳しく解説。
この記事を読めば、あなたにぴったりのワイナリーツアーが見つかり、最高のワイン体験を計画できるようになるでしょう。
目次
山梨のワイナリーツアーが人気の理由
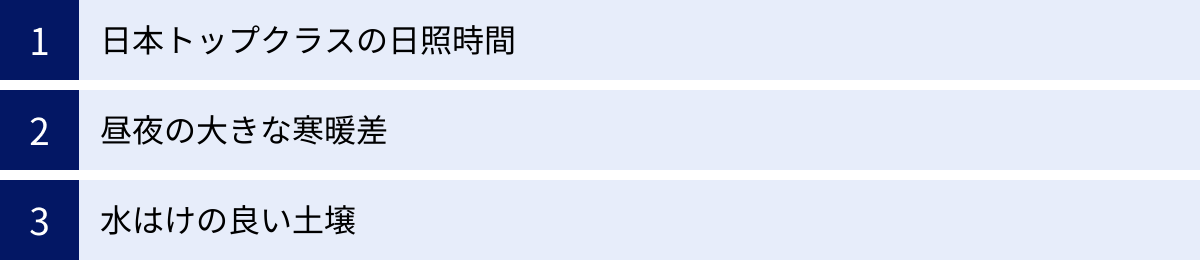
なぜ、多くの人々が山梨のワイナリーツアーに魅了されるのでしょうか。その理由は、単に美味しいワインが飲めるというだけではありません。日本のワイン造りの歴史そのものを体感できる奥深さと、世界品質のワインを生み出す豊かな自然環境にあります。ここでは、山梨が「日本ワインの聖地」と称される所以と、その地で育まれる代表的なブドウ品種の魅力に迫ります。
日本ワイン発祥の地としての歴史と魅力
山梨県、特に甲州市勝沼町は、日本のワイン産業が産声を上げた「日本ワイン発祥の地」として知られています。その歴史は明治時代初期にまで遡ります。1877年(明治10年)、この地に日本で初めての民間ワイン醸造会社「大日本山梨葡萄酒会社」が設立されました。当時、高野正誠と土屋龍憲という二人の青年がワイン醸造技術を習得するためにフランスへ渡り、その知識と情熱を持ち帰ったことが、今日の日本ワインの礎を築いたのです。
この歴史的な背景から、山梨には創業100年を超える老舗ワイナリーが数多く現存し、その歴史的建造物や資料館を巡るだけでも、日本のワイン造りが歩んできた道のりを肌で感じられます。ワイナリーツアーに参加すれば、単なる工場見学に留まらず、日本の食文化とワインがどのように関わってきたのか、その壮大な物語に触れることができるでしょう。
また、山梨がワインの名産地となったのは、歴史的背景だけが理由ではありません。盆地特有の気候が、高品質なブドウ栽培に最適な条件を備えています。具体的には、以下の3つの要素が挙げられます。
- 日本トップクラスの日照時間: 山梨県は全国的に見ても日照時間が非常に長く、ブドウが光合成を活発に行い、糖度をしっかりと蓄えることができます。これが、果実味豊かで凝縮感のあるワインの源となります。
- 昼夜の大きな寒暖差: 盆地地形のため、夏は日中の気温が上昇する一方で、夜間は放射冷却によって気温がぐっと下がります。この寒暖差がブドウの酸を程よく保ち、色づきを良くします。糖度と酸味のバランスが取れた、引き締まった味わいのワインが生まれる秘訣です。
- 水はけの良い土壌: 笛吹川や釜無川などが形成した扇状地には、水はけの良い砂礫質の土壌が広がっています。水はけが良すぎるとブドウの樹は水分を求めて地中深くまで根を張り、土壌のミネラル分を豊富に吸収します。これがワインに複雑味と奥行きを与えるのです。
これらの自然条件と、先人たちから受け継がれてきた栽培・醸造技術が融合し、山梨ワインの卓越した品質を支えています。その品質は国からも認められており、2013年には国税庁から地理的表示(GI)「山梨」が指定されました。これは、フランスのAOC(原産地呼称統制)やイタリアのDOCG(統制保証付原産地呼称)のように、特定の産地で定められた基準を満たした高品質なワインであることを証明するものです。GI「山梨」を名乗るためには、山梨県産のブドウを100%使用し、県内で醸造されることなど、厳しい基準をクリアしなければなりません。
このように、歴史、自然、そして品質保証制度が三位一体となって、山梨のワイナリーツアーを他にはない特別な体験へと昇華させているのです。
山梨を代表する主なブドウ品種
山梨のワインを語る上で欠かせないのが、その土地を象徴するブドウ品種です。特に「甲州」と「マスカット・ベーリーA」は、日本固有の品種として国内外から高い評価を受けています。それぞれの特徴を知ることで、ワイナリーでのテイスティングが何倍も楽しくなるはずです。
甲州
「甲州」は、日本の食文化に寄り添う、日本を代表する白ブドウ品種です。そのルーツは1000年以上前に遡るとも言われ、ヨーロッパからシルクロードを経て日本に伝わったという説が有力です。淡い紫色の果皮を持つこのブドウは、生食用としても親しまれてきましたが、明治時代にワイン醸造が始まって以降、その真価が発揮されることとなりました。
甲州ワインの最大の特徴は、その繊細で奥ゆかしい香味にあります。グレープフルーツやカボス、スダチといった和柑橘を思わせる爽やかな香りに、白桃やリンゴのニュアンスが重なります。味わいは、凛としたシャープな酸味が基調となり、ミネラル感が豊かで、非常にクリーンな印象を与えます。この上品な味わいが、寿司、天ぷら、おひたしといった繊細な味付けの和食と驚くほど良く合います。
近年では醸造技術の進化により、甲州ワインのスタイルは多様化しています。
- シュール・リー製法: 発酵後に澱(おり)とワインを一定期間接触させる製法。これにより、ワインに厚みと複雑味、うま味が加わります。
- 樽熟成: 樽で熟成させることで、ヴァニラやナッツのような香ばしい風味が加わり、リッチで骨格のある味わいになります。
- スパークリングワイン: 爽やかな酸味を活かしたスパークリングワインは、乾杯の一杯から食中酒まで幅広く楽しめます。
- オレンジワイン: 果皮や種と一緒に醸すことで、オレンジ色がかった色調と、ほのかな渋み、複雑な香りが生まれます。
ワイナリーを訪れた際には、ぜひ様々なスタイルの甲州ワインを飲み比べて、その表現の幅広さを体感してみてください。
マスカット・ベーリーA
「マスカット・ベーリーA」は、日本のワインブドウの父・川上善兵衛によって生み出された、日本を代表する黒ブドウ品種です。新潟県にある岩の原葡萄園の創業者である川上善兵衛は、日本の気候風土に適したブドウ品種を求め、生涯にわたって品種改良に取り組みました。マスカット・ベーリーAは、1927年にアメリカ系の「ベーリー」を母、ヨーロッパ系の「マスカット・ハンブルグ」を父として交配され誕生した、まさに日本のオリジナル品種です。
マスカット・ベーリーAから造られる赤ワインは、華やかで親しみやすい果実香が特徴です。イチゴやラズベリーキャンディ、綿あめのような甘くチャーミングな香りがグラスから立ち上り、ワイン初心者の方でも「美味しい」と感じやすい魅力を持っています。味わいは、渋み(タンニン)が穏やかで、果実味豊かな酸味が心地よく、非常に飲みやすいスタイルが主流です。
この親しみやすいキャラクターから、醤油やみりんを使った甘辛い味付けの料理、例えば、すき焼き、焼き鳥(タレ)、豚の角煮などと素晴らしい相性を見せます。
一方で、マスカット・ベーリーAもまた、生産者の探求心によって新たな可能性を広げています。樹齢の高いブドウから造られたり、樽熟成を施されたりしたものは、キャンディ香が落ち着き、スパイスや土、なめし革のような複雑なニュアンスが現れます。凝縮感のある果実味と滑らかなタンニンが調和した、長期熟成にも耐えうる本格的な赤ワインも数多く生み出されています。
歴史と風土が織りなす物語に触れ、甲州やマスカット・ベーリーAといった土地固有のブドウ品種の個性を知る。これこそが、山梨のワイナリーツアーが多くの人々を惹きつけてやまない理由なのです。
失敗しない山梨ワイナリーの選び方
数ある山梨のワイナリーの中から、自分にとって最高の場所を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。漠然と選ぶのではなく、「エリア」「体験内容」「予約の有無」という3つの軸で絞り込んでいくことで、満足度の高いワイナリー巡りを計画できます。
行きたいエリアから選ぶ
山梨のワイナリーは県内各地に点在していますが、特にいくつかのエリアに集中しています。それぞれのエリアに特徴があるため、自分の好みや交通手段に合わせて選ぶのがおすすめです。
| エリア | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 勝沼・塩山エリア | ・日本ワイン発祥の地で、ワイナリーが最も密集 ・老舗から新進気鋭まで多様なワイナリーが存在 ・公共交通機関でのアクセスが良好(JR勝沼ぶどう郷駅) ・周遊バスやレンタサイクルが利用しやすい |
・初めてワイナリー巡りをする人 ・車なしで効率よく複数のワイナリーを回りたい人 ・日本のワイン史に触れたい人 |
| 甲府・石和エリア | ・甲府盆地の中心に位置し、温泉地としても有名 ・比較的規模の大きなワイナリーが点在 ・宿泊とワイナリー巡りを組み合わせやすい ・甲府駅や石和温泉駅からのアクセスが便利 |
・温泉旅行とワイナリー巡りを一緒に楽しみたい人 ・家族旅行やグループ旅行で訪れる人 ・アクセス至便な場所を好む人 |
| 穂坂・韮崎エリア | ・茅ヶ岳の麓、標高400~700mに広がる産地 ・日照時間が長く、寒暖差が激しい気候 ・凝縮感と力強さのあるブドウが育つ ・カベルネ・ソーヴィニヨンなど欧州品種の評価も高い |
・本格的なワイン愛好家 ・特定の品種や力強いスタイルのワインが好きな人 ・雄大な自然景観の中でワインを楽しみたい人 |
勝沼・塩山エリアは、まさに「ワイナリーの銀座」。JR勝沼ぶどう郷駅を拠点に、徒歩やタクシー、レンタサイクルで数多くのワイナリーを巡ることが可能です。駅周辺には観光案内所があり、ワイナリーマップを手に入れて散策プランを立てるのも楽しいでしょう。特に秋の収穫期には「勝沼ぶどう郷ワインツーリズム」などのイベントも開催され、エリア全体が活気に満ち溢れます。初心者の方が「まずはどこかへ」と考えるなら、このエリアを選べば間違いありません。
甲府・石和エリアは、山梨観光の中心地です。石和温泉郷に宿泊し、日中にワイナリーを訪れるというプランが人気です。甲府駅周辺には飲食店も多く、ワイナリーで購入したワインを持ち込んで楽しめる(BYO)お店を探すのも一興です。このエリアのワイナリーは、見学施設やレストランが充実している大規模な場所も多く、ゆったりと過ごしたい方に向いています。
穂坂・韮崎エリアは、より深くワインを探求したい方向けのエリアと言えるでしょう。標高の高い斜面に広がるブドウ畑は美しく、そこで育つブドウからは骨格のしっかりとしたワインが生まれます。アクセスは車が中心となりますが、その分、落ち着いた環境でじっくりとワインと向き合うことができます。「通」好みのワイナリーが多く、造り手と直接話ができる機会も多いのが魅力です。
体験したい内容(見学・試飲・食事)で選ぶ
ワイナリーでできることは、ワインを飲むだけではありません。どんな体験をしたいかによって、選ぶべきワイナリーは大きく変わってきます。
- 醸造所見学ツアーで学びたい
ワイナリーの心臓部である醸造施設を見学できるツアーは、ワイン造りのプロセスを深く理解できる絶好の機会です。ツアーにはいくつかの種類があります。- 無料・自由見学: 予約なしで、決められた見学通路から自由に見ることができるタイプ。手軽ですが、説明はパネルなどが中心です。
- ガイド付きツアー(有料/無料): ワイナリーのスタッフがブドウ畑や醸造施設、樽が眠る貯蔵庫などを案内してくれる本格的なツアー。 造り手のこだわりや苦労話など、ここでしか聞けない貴重な話が聞けるのが最大の魅力です。ワインへの理解が格段に深まるため、時間に余裕があればぜひ参加をおすすめします。多くの場合、ツアーの最後にはテイスティングが含まれています。
- テイスティング(試飲)をメインに楽しみたい
ワイナリー巡りの醍醐味は、やはりテイスティングです。試飲のスタイルもワイナリーによって様々です。- 無料試飲: ショップカウンターなどで、数種類の定番ワインを無料で試飲できるスタイル。気軽にそのワイナリーの味を知ることができます。
- 有料試飲(テイスティングカウンター): グラス1杯単位や、3種飲み比べセットなど、有料で様々なワインを試せるスタイル。フラッグシップワインやバックヴィンテージ(過去の年のワイン)など、通常はボトルでしか購入できない希少なワインをグラスで試せるのが大きなメリットです。
- 試飲専用サーバー: 専用のカードを購入し、サーバーから好きなワインを好きな量だけ注いで試飲できるシステム。多くの種類を少しずつ試したい場合に最適です。
- 食事とのマリアージュを堪能したい
ワインと料理の組み合わせ(マリアージュ)は、互いの魅力を高め合う素晴らしい体験です。山梨には、レストランやカフェを併設するワイナリーも少なくありません。- 本格フレンチ・イタリアン: ワイナリーのフラッグシップワインに合わせてコース料理が提供されるレストラン。記念日や特別な日のランチに最適です。窓からブドウ畑を眺めながらの食事は、忘れられない思い出になるでしょう。
- カジュアルなカフェ・デリ: 地元の食材を使ったデリプレートや軽食を、ワインと共に気軽に楽しめるスタイル。ブドウ畑のテラス席でピクニック気分を味わえる場所もあります。
予約の必要性で選ぶ
行きたいワイナリーが決まったら、必ず予約が必要かどうかを確認しましょう。特に週末や連休は混雑するため、事前の確認と予約がスムーズなワイナリー巡りの鍵となります。
- 予約不要のワイナリー
主にワインショップでの購入や、カウンターでの簡易的な無料試飲が目的であれば、予約なしで訪問できるワイナリーが多くあります。「近くまで来たから、ちょっと寄ってみよう」という気軽な立ち寄りが可能です。ただし、団体での訪問や、特定のワインの在庫を確認したい場合は、事前に電話連絡を入れておくと親切です。 - 予約必須のワイナリー
前述のガイド付き見学ツアーや、レストランでの食事は、ほとんどの場合で事前予約が必須です。人気のツアーやレストランは数週間前、あるいは1ヶ月以上前から予約が埋まってしまうことも珍しくありません。ワイナリーの公式サイトにオンライン予約システムが用意されていることが多いので、早めに確認・予約手続きを済ませましょう。電話でのみ予約を受け付けている場合もあります。
予約する際には、キャンセルポリシーや人数の変更期限なども併せて確認しておくことが大切です。これらの選び方を参考に、自分の旅のスタイルに合ったワイナリーをリストアップし、最高のツアーを計画してみてください。
【日帰りOK】山梨のおすすめワイナリー10選
ここでは、数ある山梨のワイナリーの中から、日帰りでも十分に楽しめ、かつ初心者から愛好家まで満足できる個性豊かな10のワイナリーを厳選してご紹介します。それぞれの特徴やツアー内容を比較し、あなたのお気に入りを見つけてください。
| ワイナリー名 | エリア | 見学ツアー | 試飲 | レストラン | 予約の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー | 勝沼 | ◎ (有料/要予約) | ◎ (有料) | 〇 (カフェ) | ツアーは要予約 |
| サントリー登美の丘ワイナリー | 穂坂・韮崎 | ◎ (有料/要予約) | ◎ (有料) | 〇 (ショップ内) | ツアーは要予約 |
| ルミエールワイナリー | 甲府・石和 | ◎ (有料/要予約) | ◎ (有料/無料あり) | ◎ (フレンチ) | ツアー・レストランは要予約 |
| まるき葡萄酒 | 勝沼 | 〇 (無料/要予約) | ◎ (有料/無料あり) | × | 見学は要予約 |
| マンズワイン勝沼ワイナリー | 勝沼 | 〇 (無料/一部要予約) | ◎ (有料/無料あり) | × | 一部ツアーは要予約 |
| 原茂ワイン | 勝沼 | × | ◎ (有料) | ◎ (カフェ) | カフェは予約推奨 |
| シャトー・ジュン | 勝沼 | 〇 (要問い合わせ) | ◎ (有料) | × | 要問い合わせ |
| 勝沼醸造 | 勝沼 | × | ◎ (有料) | ◎ (レストラン/バー) | レストランは要予約 |
| シャトー酒折ワイナリー | 甲府・石和 | 〇 (無料/自由見学) | ◎ (有料/無料あり) | × | 予約不要(団体除く) |
| マルス山梨ワイナリー | 甲府・石和 | 〇 (無料/自由見学) | ◎ (有料/無料あり) | × | 予約不要(団体除く) |
※上記の情報は変更される可能性があるため、訪問前に必ず各ワイナリーの公式サイトで最新情報をご確認ください。
① シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー
日本ワインの歴史そのものを体感できる、まさに聖地と呼ぶべきワイナリーです。1903年に建てられた日本最古の木造ワイン醸造所「ワイン資料館」は、その歴史的価値から近代化産業遺産にも認定されています。敷地内にはテイスティングカウンターやカフェも併設され、歴史とモダンが見事に融合した空間が広がります。
ツアーは、ワイン造りの哲学や歴史を深く学べる有料のコースが複数用意されています。ブドウ畑から醸造施設、地下セラーまでを専門のガイドが丁寧に案内してくれ、最後にはツアーでしか飲めない特別なワインを含むテイスティングが楽しめます。特にフラッグシップである「城の平」や「桔梗ヶ原メルロー」は、日本ワインの到達点を示す逸品として知られています。ワイン初心者から熱心な愛好家まで、誰もが知的好奇心を満たされる体験ができるでしょう。(参照:シャトー・メルシャン公式サイト)
② サントリー登美の丘ワイナリー
南アルプスや富士山を望む、標高約600mの丘陵地に広がる絶景ワイナリー。約150ヘクタールという広大な自家ぶどう園は圧巻の一言です。天気の良い日には、展望デッキからの眺めを楽しむだけでも訪れる価値があります。
ここでは、広大な敷地を巡りながらブドウ栽培やワイン造りについて学べる、多彩な有料ツアーが開催されています。栽培・醸造担当者が自ら案内する特別なツアーもあり、ワイン造りの最前線に触れることができます。ツアー後には、併設のワインショップでテイスティングが可能。フラッグシップの「登美」シリーズをはじめ、ここでしか手に入らない限定ワインも販売されています。自然の雄大さと、大手ならではの徹底した品質管理を両方感じられるワイナリーです。(参照:サントリー登美の丘ワイナリー公式サイト)
③ ルミエールワイナリー
1885年創業の歴史を誇る老舗でありながら、常に革新的なワイン造りに挑戦し続けるワイナリー。特に登録有形文化財にも指定されている「石蔵発酵槽」を用いたワイン造りは、ルミエールの象徴です。現在もこの石蔵を使い、甲州種を醸して造られる「石蔵和飲」は、国内外で高い評価を受けています。
有料の見学ツアーでは、この歴史的な石蔵や地下セラーを巡り、ルミエールのワイン造りへのこだわりを深く知ることができます。また、ワイナリーに併設されたレストラン「ゼルコバ」は特筆すべき存在です。地元の食材をふんだんに使った本格フレンチと、ルミエールのワインが織りなすマリアージュは格別。ブドウ畑を眺めながら過ごす優雅なひとときは、最高の思い出になるはずです。ショップでは無料試飲も可能で、気軽に立ち寄ることもできます。(参照:ルミエールワイナリー公式サイト)
④ まるき葡萄酒
1891年(明治24年)創業の、現存する日本最古のワイナリーとして知られています。その歴史を物語る土蔵の貯蔵庫や古い醸造器具は、訪れる者にノスタルジックな感慨を与えます。派手さはありませんが、日本のワイン造りの原点に触れたい方にはぜひ訪れてほしい場所です。
無料の見学(要予約)では、スタッフが歴史やワイン造りについて丁寧に説明してくれます。ワインショップでは、無料試飲と有料試飲の両方が楽しめます。特に、甕(かめ)で熟成させたワインなど、まるき葡萄酒ならではのユニークな商品も魅力の一つ。フラッグシップの「ラフィーユ」シリーズは、コストパフォーマンスに優れた高品質なワインとして人気があります。歴史の重みを感じながら、じっくりとワインを選びたい方におすすめです。 (参照:まるき葡萄酒公式サイト)
⑤ マンズワイン勝沼ワイナリー
キッコーマングループが運営する大手ワイナリーで、安定した品質と充実した見学施設が魅力です。予約不要で自由に見学できるコースが設けられており、ガラス越しに醸造タンクや樽熟成庫、瓶詰めのラインなどを見ることができます。要所には説明パネルが設置されているため、自分のペースでワイン造りの工程を学ぶことが可能です。
ワインギャラリーでは、定番の「ソラリス」シリーズから日常使いのワインまで、幅広いラインナップを無料で試飲できます(一部有料)。特に「ソラリス」は、国内外のコンクールで数々の受賞歴を誇るプレミアムワインであり、その実力をぜひ試してみてください。広々とした売店はお土産選びにも最適で、ワインの他にワインに合うおつまみなども充実しています。ファミリーでも気軽に楽しめる、間口の広いワイナリーです。(参照:マンズワイン勝沼ワイナリー公式サイト)
⑥ 原茂ワイン
JR勝沼ぶどう郷駅からほど近い、趣のあるワイナリー。築100年以上の母屋を改装したカフェ「カーサ・ダ・ミサ」が特に有名で、その風情ある雰囲気は多くの観光客を惹きつけます。カフェでは、自家製ワインと共に、地元の野菜をたっぷり使ったランチプレートや手作りスイーツが楽しめます。窓から見える甲府盆地の景色もごちそうです。
ワイナリーとしては小規模ですが、丁寧に造られたワインは根強いファンを持ちます。特に「ハラモ・ヴィンテージ」シリーズは、自社農園のブドウを100%使用したこだわりの逸品。ショップでは有料でテイスティングが可能です。大規模な見学ツアーはありませんが、その分、カフェでゆったりと時間を過ごしたり、ショップでスタッフと話しながらワインを選んだりと、アットホームな雰囲気を満喫できます。(参照:原茂ワイン公式サイト)
⑦ シャトー・ジュン
人気アパレルブランド「JUN」が運営する、おしゃれで洗練された雰囲気のワイナリー。ファッションブランドならではの感性が、ワイナリーのたたずまいやワインのラベルデザインにも反映されています。ワインだけでなく、ライフスタイル全体を提案するような世界観が魅力です。
自社畑では、山梨の代表品種である甲州やマスカット・ベーリーAのほか、カベルネ・ソーヴィニヨンやシャルドネといった欧州品種も栽培しています。ショップでは、これらのワインを有料でテイスティングできます。特に甲州種のワインは評価が高く、様々なスタイルの甲州を造り分けています。見学については要問い合わせとなりますが、併設されたショップや美しい庭園を散策するだけでも、その洗練された雰囲気を十分に楽しむことができます。(参照:シャトー・ジュン公式サイト)
⑧ 勝沼醸造
「甲州」というブドウ品種の可能性を世界に知らしめた、日本を代表する甲州ワインのトップ生産者です。国内外の有名レストランやワイン専門誌で絶賛される彼らのワインは、まさに世界品質。ブドウの個性を最大限に引き出すため、畑の区画ごとに醸造を行うなど、そのこだわりは徹底しています。
ワイナリーの敷地内には、テイスティングカウンター、レストラン、そしてブドウ畑を望むテラス席があり、非常に洗練された空間が広がっています。テイスティングでは、スタンダードなクラスから、樽熟成させたリッチな味わいの「アルガブランカ イセハラ」のようなトップキュヴェまで、様々な甲州ワインを飲み比べることができます。ワイン愛好家であれば、一度は訪れるべき聖地の一つと言えるでしょう。(参照:勝沼醸造公式サイト)
⑨ シャトー酒折ワイナリー
甲府盆地を一望できる高台に位置し、その近代的な建物が目を引くワイナリーです。予約なしで醸造施設や地下の樽貯蔵庫を自由に見学できるのが大きな特徴。ガラス張りの見学通路から、ステンレスタンクや熟成中の樽を間近に見ることができ、ワイン造りの臨場感を味わえます。
ショップに併設されたテイスティングコーナーでは、専用のプリペイドカードを購入し、ワインサーバーから好きなワインを好きな量だけ試飲できるシステムを採用。定番ワインから希少な限定品まで、常時20種類以上のワインが揃っており、少しずつたくさんの種類を試したい方にはたまりません。特に、マスカット・ベーリーAを木樽で熟成させた「樽熟成マスカット・ベーリーA」は、この品種の新たな可能性を示したワインとして高い人気を誇ります。(参照:シャトー酒折ワイナリー公式サイト)
⑩ 本坊酒造 マルス山梨ワイナリー
ウイスキー造りで有名な本坊酒造が、笛吹市石和町で運営するワイナリー。「マルスウイスキー」のブランドで知られていますが、ワイン造りにおいても長い歴史と実績を持っています。一つの場所でワインとウイスキー、両方の魅力を楽しめるのが最大の特色です。
工場は見学通路から自由に見学でき、ワインの醸造・貯蔵設備に加えて、ウイスキーのポットスチル(蒸留器)や貯蔵庫も見ることができます。売店では、ワインはもちろん、限定品のウイスキーやブランデーも販売されており、お酒好きにはたまらないラインナップ。試飲カウンターでは、ワインの無料試飲が可能です(一部有料)。石和温泉郷からも近く、気軽に立ち寄れる観光スポットとしても人気を集めています。(参照:本坊酒造公式サイト)
ワイナリーツアー当日の服装と持ち物
ワイナリーツアーを心から楽しむためには、事前の準備が大切です。特に服装と持ち物は、当日の快適さを大きく左右します。ここでは、ワイナリー巡りに最適な服装のポイントと、持っていると便利なアイテムをリストアップしてご紹介します。
ツアーに最適な服装
ワイナリーは自然の中にある施設であり、醸造設備が置かれた場所でもあります。おしゃれをしつつも、機能性と安全性を考慮した服装を心がけましょう。
- 最重要アイテム:歩きやすい靴
ワイナリーツアーで最も重要なのは、間違いなく「歩きやすい靴」です。 ツアーでは、舗装されていないブドウ畑を歩いたり、滑りやすい床の醸造所内を移動したり、階段を上り下りしたりする場面が多くあります。そのため、スニーカーやフラットソールのウォーキングシューズが最適です。
一方で、ハイヒールやピンヒールは絶対に避けましょう。土の地面にヒールがめり込んで歩きにくいだけでなく、醸造所の床を傷つけたり、グレーチング(金属製の格子状の蓋)にヒールが挟まったりする危険性があります。また、コツコツという足音は、静かなセラー(貯蔵庫)では非常に響き、他の参加者の迷惑になる可能性もあります。 - 動きやすさを重視した服装
パンツスタイルが最も動きやすくおすすめです。畑でしゃがんでブドウの樹を観察したり、醸造タンクを覗き込んだりする際にも気になりません。スカートを履く場合は、風でめくれやすいフレアスカートよりも、足さばきの良いロングスカートやマキシ丈のものが良いでしょう。 - 温度調節ができる羽織もの
ワインの貯蔵庫や地下セラーは、年間を通して温度が15℃前後に保たれています。 これは、ワインの品質を安定させるために不可欠な環境です。そのため、真夏の暑い日に訪れたとしても、セラーの中はひんやりと感じます。半袖一枚では体が冷えてしまう可能性があるので、カーディガンや薄手のジャケット、パーカー、ストールなど、さっと羽織れるものを必ず一枚持参しましょう。ブドウ畑は日差しが強い一方で、セラーは涼しいという温度差に対応できるようにしておくことが快適に過ごすコツです。 - 香水や香りの強い柔軟剤はNG
これはワイナリーを訪れる上での最も大切なマナーの一つです。ワインのテイスティングでは、グラスに鼻を近づけてその繊細で複雑な香りを楽しむことが醍醐味です。香水やオーデコロン、香りの強いヘア製品や柔軟剤の匂いは、ワイン本来の香りをかき消してしまい、自分だけでなく周りの人々のテイスティングの妨げになります。当日は、無香料の制汗剤を使用するなど、香りのエチケットを徹底しましょう。 - 汚れを気にしなくても良い色や素材
必須ではありませんが、念のため考慮しておくと安心です。テイスティングの際にワインが跳ねてしまったり、畑の土がついてしまったりする可能性もゼロではありません。真っ白なシャツや高価なデリケート素材の服は避け、万が一汚れても気にならないような、濃い色の服装や洗濯しやすい素材の服を選ぶと、よりリラックスしてツアーを楽しめます。
あると便利な持ち物リスト
服装に加えて、以下のアイテムがあるとワイナリー巡りがさらに快適で充実したものになります。
| 持ち物 | 用途・理由 |
|---|---|
| 日焼け対策グッズ | ブドウ畑は日差しを遮るものが少ないため、帽子、サングラス、日焼け止めは必須です。特に春から秋にかけては紫外線が強いので忘れずに。 |
| メモ帳とペン | テイスティングしたワインの名前、ブドウ品種、ヴィンテージ(収穫年)、香りや味わいの感想などを記録するため。後でワインを購入する際の参考になりますし、自分の好みが分かってくる楽しみもあります。スマートフォンのメモ機能でも代用可能です。 |
| エコバッグ・サブバッグ | ワインを購入した際に入れるために便利です。ワイナリーの袋は有料の場合もありますし、複数本購入すると重くなるため、丈夫なエコバッグがあると持ち運びが楽になります。 |
| 現金 | 多くのワイナリーではクレジットカードが利用できますが、小規模なワイナリーや一部の有料試飲カウンターなどでは現金のみの場合もあります。念のため、ある程度の現金を用意しておくと安心です。 |
| (運転しない方)水分補給用の水 | アルコールには利尿作用があるため、気づかないうちに水分不足になりがちです。テイスティングの合間に水を飲むことで、悪酔いを防ぎ、味覚をリフレッシュさせる効果もあります。多くのワイナリーで水は用意されていますが、移動中などのために持っておくと便利です。 |
| カメラ | 美しいブドウ畑やワイナリーの建物を写真に収めるため。ただし、醸造施設内やセラーなど、場所によっては撮影が禁止されている場合があります。 必ず事前にガイドに確認し、マナーを守って撮影しましょう。 |
| ハンカチ・ティッシュ | 基本的な持ち物ですが、手を拭いたり、グラスの縁を拭ったりと、何かと役立ちます。 |
これらの準備を万全にして、心置きなく山梨のワイナリーツアーを満喫してください。
山梨のワイナリーへの主なアクセス方法

山梨のワイナリー巡りを計画する上で、移動手段は非常に重要な要素です。全員で気兼ねなく試飲を楽しみたいなら公共交通機関、自由度を優先するなら車、とそれぞれのメリット・デメリットを理解して、自分の旅のスタイルに合った方法を選びましょう。
公共交通機関(電車・バス)を利用する場合
最大のメリットは、参加者全員が心置きなくワインの試飲を楽しめることです。運転の心配がないため、様々なワイナリーでテイスティングを堪能できます。特に、ワイナリーが密集する勝沼エリアでは、公共交通機関の利用が非常に便利です。
- 拠点となる主要駅
ワイナリー巡りの玄関口となるのは、主にJR中央本線の駅です。- 勝沼ぶどう郷駅: 勝沼エリアのワイナリー巡りの中心拠点。駅舎からの甲府盆地の眺めは素晴らしく、旅の始まりに気分が高まります。
- 塩山駅: 勝沼エリアの北側に位置し、こちらも多くのワイナリーへのアクセス拠点となります。
- 山梨市駅: フルーツ公園や温泉施設へのアクセスも良好です。
- 石和温泉駅: 石和温泉郷の最寄り駅。宿泊とワイナリー巡りを組み合わせる際の拠点になります。
- 甲府駅: 山梨県の中心駅。特急も停車し、各方面へのバス路線も充実しています。
- 駅からワイナリーへの足
駅からワイナリーまでは、いくつかの交通手段があります。- 周遊バス・観光バス: 特に勝沼エリアでは、週末や観光シーズンを中心に「勝沼周遊バス(ぶどうバス)」が運行されることがあります。主要なワイナリーや観光スポットを結んで走るため、車がなくても効率的に周遊できます。運行期間やルート、料金は年度によって変わるため、甲州市観光協会の公式サイトなどで事前に最新情報を確認することが不可欠です。
- 路線バス: 各駅から路線バスも運行されていますが、本数が1時間に1本以下という路線も少なくありません。利用する場合は、事前に乗りたいバスの時刻表を往復分しっかりと調べて、計画を立てる必要があります。
- タクシー: 駅から目的地までダイレクトに移動できるため、時間と労力を節約できます。2〜4人のグループであれば、料金を割り勘にすることでお得に利用できる場合もあります。駅前に常駐していることが多いですが、帰りにワイナリーから駅まで利用したい場合は、ワイナリーのスタッフにタクシーを呼んでもらうか、事前にタクシー会社の電話番号を控えておくとスムーズです。
- レンタサイクル: 勝沼ぶどう郷駅や塩山駅周辺にはレンタサイクル店があります。天気の良い日には、ブドウ畑の中を自転車で駆け抜けるのは非常に気持ちが良い体験です。ただし、山梨は坂道が多い地形なので、体力に自信がない方は電動アシスト付き自転車を選ぶことを強くおすすめします。
公共交通機関を利用する場合の注意点は、時間に制約があることです。バスや電車の時刻を常に意識する必要があるため、訪問できるワイナリーの数はおのずと限られます。巡りたいワイナリーの優先順位をつけ、無理のないスケジュールを組むことが大切です。
車(レンタカー・タクシー)を利用する場合
車を利用する最大のメリットは、時間や場所に縛られず、自由気ままにワイナリー巡りができることです。公共交通機関ではアクセスの難しい郊外のワイナリーにも足を延ばせますし、重たいワインボトルを何本購入しても持ち帰りが楽です。
- 最大の注意点:ドライバーは試飲厳禁
言うまでもありませんが、車を運転する人は、アルコールを一滴たりとも飲むことはできません。 飲酒運転は法律で固く禁じられています。グループで行く場合は、事前に必ずハンドルキーパー(運転に徹する人)を決めておきましょう。 ハンドルキーパー役の人は、ワインの試飲はできませんが、その分、多くのワイナリーが運転手向けに提供している高品質なぶどうジュースやノンアルコール飲料を楽しむことができます。ワイナリーの雰囲気やブドウ畑の景色、そしてお土産選びの楽しみは十分に味わえます。ハンドルキーパーへの感謝を忘れず、お土産に好きなワインを一本プレゼントするなどの配慮をすると、全員が気持ちよく楽しめるでしょう。 - レンタカーの利用
都心から電車で主要駅(甲府駅、勝沼ぶどう郷駅など)まで行き、駅周辺でレンタカーを借りるという方法も効率的です。渋滞の多い中央道を自分で運転するストレスを回避できます。特に週末や連休はレンタカーの予約が埋まりやすいため、早めの手配がおすすめです。 - 駐車場について
ほとんどのワイナリーには、無料の訪問者用駐車場が完備されています。ただし、収穫祭などのイベント開催時には駐車場が満車になることもあるため、時間に余裕を持って行動しましょう。 - 観光タクシー・ハイヤーのチャーター
料金は高くなりますが、運転をプロに任せ、自分たちの行きたい場所だけを巡る「チャーター」という選択肢もあります。地元の道に詳しいドライバーが効率的なルートを案内してくれる上、参加者全員が試飲を楽しめるという、公共交通機関と車の「良いとこ取り」ができる贅沢な方法です。記念日旅行や、お酒好きな仲間とのグループ旅行などで検討する価値は十分にあります。
どちらのアクセス方法にも一長一短があります。誰と行くのか、何を一番楽しみたいのかを考えて、最適なプランを立ててください。
ワイナリー巡りと一緒に楽しみたい周辺観光スポット
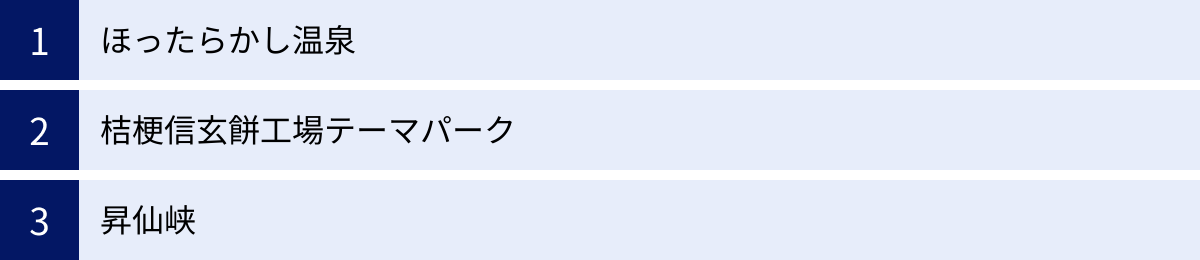
せっかく山梨まで足を運ぶなら、ワイナリー巡りだけでなく、周辺の魅力的な観光スポットも訪れてみてはいかがでしょうか。ワインで心を満たした後は、絶景の温泉やご当地グルメ、大自然の造形美が旅をさらに豊かなものにしてくれます。ここでは、ワイナリー巡りと組み合わせて楽しめる、定番の人気スポットを3つご紹介します。
ほったらかし温泉
ワイナリー巡りで歩き回った体の疲れを癒すのに、これ以上の場所はないでしょう。「ほったらかし温泉」は、その名の通り、素朴で飾らない雰囲気が魅力の絶景日帰り温泉施設です。最大の魅力は、甲府盆地を一望し、その向こうに雄大な富士山を望むパノラマビュー。 標高約700mの高さから見下ろす景色は、まさに圧巻の一言です。
敷地内には「あっちの湯」と「こっちの湯」という2つの浴場があります。
- あっちの湯: 従来の2倍の広さを誇る新しい浴場。日の出から夜景まで、甲府盆地の壮大な景色を存分に楽しめます。特に、空が白み始め、富士山のシルエットが浮かび上がる日の出の時間は、言葉を失うほどの美しさです。
- こっちの湯: 木のぬくもりと岩造りの風情ある浴場。正面に富士山を望む落ち着いた雰囲気で、古くからのファンに愛されています。
日の出の1時間前から営業しているため、早朝に温泉を楽しんでからワイナリー巡りに出かけるというプランも可能です。また、夜は満天の星と甲府盆地の夜景が「新日本三大夜景」にも選ばれており、ロマンチックな雰囲気に包まれます。温泉でさっぱりした後にいただく名物の「温玉あげ」も絶品です。(参照:ほったらかし温泉公式サイト)
桔梗信玄餅工場テーマパーク
山梨の代表的な銘菓「桔梗信玄餅」の製造工程を見学できる、食のアミューズメントパークです。ワイナリーが集まる笛吹市にあり、アクセスしやすいのも魅力です。
このテーマパークで絶大な人気を誇るのが、「お菓子の詰め放題」です。専用の袋に、形が少し不揃いなだけで味は正規品と変わらない桔梗信玄餅やその他のお菓子を、袋が破れない限り好きなだけ詰めることができます。テレビやSNSでも頻繁に取り上げられるため、毎日早朝から整理券を求める人々で長蛇の列ができます。挑戦したい方は、朝一番で訪れることを強くおすすめします。
詰め放題以外にも、一つひとつ手作業で包装される桔梗信玄餅の製造ラインを見学したり、ここでしか味わえない「桔梗信玄ソフト+」などの限定スイーツを楽しんだり、アウトレット価格でお得にお土産を購入したりと、楽しみ方は様々。子供から大人まで、家族全員で楽しめるスポットです。(参照:桔梗信玄餅工場テーマパーク公式サイト)
昇仙峡
甲府市の北部に位置する「昇仙峡」は、国の特別名勝にも指定されている日本有数の渓谷です。釜無川の支流、荒川によって長い年月をかけて削り取られた花崗岩の断崖や奇岩が、約5kmにわたって続きます。
渓谷沿いには遊歩道が整備されており、清流のせせらぎを聞きながらハイキングを楽しむことができます。特に見どころは、日本の滝百選にも選ばれている落差30mの「仙娥滝(せんがたき)」や、天を突くようにそびえ立つ高さ180mの巨岩「覚円峰(かくえんぽう)」など、自然が創り出したダイナミックなアート作品の数々です。
より手軽に絶景を楽しみたい方は、「昇仙峡ロープウェイ」がおすすめです。山頂のパノラマ台駅からは、富士山や南アルプス連峰を一望できます。新緑がまぶしい初夏や、渓谷全体が燃えるような赤や黄色に染まる紅葉の季節は、特に美しい景色が広がります。ワイナリー巡りで都会的な楽しみを味わった後に、大自然の中で心身ともにリフレッシュするのに最適な場所です。(参照:昇仙峡観光協会公式サイト)
これらのスポットを旅のプランに組み込むことで、ワインだけでなく、山梨が持つ多様な魅力を存分に体験できるはずです。
山梨のワイナリーツアーに関するよくある質問
最後に、山梨のワイナリーツアーに関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。事前にこれらの疑問を解消しておくことで、より安心して当日を迎えられます。
予約なしでも見学や試飲はできますか?
回答:ワイナリーや体験したい内容によって異なります。
- 予約なしで可能なこと:
多くのワイナリーでは、併設されたワインショップでの買い物や、カウンターでの簡易的な無料試飲(数種類)は予約なしで可能です。近くを通りかかった際にふらっと立ち寄り、そのワイナリーの雰囲気を味わったり、お土産を購入したりすることは気軽にできます。また、シャトー酒折ワイナリーのように、見学通路から自由に見学できる施設もあります。 - 予約が推奨・必須なこと:
一方で、スタッフが案内してくれるガイド付きの見学ツアー、特別なワインをテイスティングできるセミナー、併設レストランでの食事などは、ほとんどの場合で事前予約が必須です。特に人気のツアーやレストランは、週末や観光シーズンには数週間前、場合によっては1ヶ月以上前に予約が満席になってしまうこともあります。
結論として、行きたいワイナリーと、そこで何をしたいかが決まっている場合は、必ず公式サイトで予約の要否を確認し、必要であれば早めに予約手続きを済ませておくことを強くおすすめします。 これが、当日「満席で入れなかった…」という事態を避けるための最も確実な方法です。
ワイナリー巡りに最適な季節はいつですか?
回答:一年を通して楽しめますが、目的によっておすすめの季節は異なります。
| 季節 | 特徴・楽しみ方 |
|---|---|
| 春(4月~5月) | ブドウの樹が芽吹き、新緑が目に鮮やかな季節です。気候が穏やかで過ごしやすく、ブドウ畑の散策が非常に気持ち良いでしょう。GWにはイベントを開催するワイナリーもあります。 |
| 夏(7月~8月) | ブドウの果実が日に日に大きく成長していく生命力あふれる季節です。太陽の下、キリリと冷えた甲州の白ワインやスパークリングワインを味わうのは格別です。 |
| 秋(9月~11月) | ブドウの収穫(ヴェレゾン)とワインの仕込みが行われる、ワイナリーが最も活気づくシーズンです。 醸造の様子を間近で見られるチャンスも多く、各地で新酒祭りなどのイベントが開催されます。ブドウ畑が美しく色づく紅葉の季節でもあり、観光には最高の時期と言えます。 |
| 冬(12月~2月) | 観光客が比較的少なく、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりとワイナリーを巡ることができます。醸造は一段落し、ワインが樽やタンクの中で静かに熟成していく時期です。暖炉のあるテイスティングルームなどで、造り手とじっくり話をしながら、コクのある赤ワインなどを味わうのに最適な季節です。 |
最も人気があり、イベントも多いのは秋ですが、それぞれの季節にしかない魅力があります。ご自身の興味や旅行のスタイルに合わせて訪れる時期を選んでみてください。
車で行っても楽しめますか?
回答:はい、十分に楽しめます。ただし、絶対的なルールがあります。
車での訪問は、移動の自由度が高く、多くのワイナリーを効率的に回れるため非常に便利です。しかし、忘れてはならないのが「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という鉄則です。
運転手(ハンドルキーパー)は、アルコールを含む試飲を一切することはできません。 これはワイナリー巡りにおける絶対的なマナーであり、法的な義務です。
では、運転手は楽しめないのかというと、決してそんなことはありません。
- 高品質なぶどうジュース: 多くのワイナリーでは、ワイン用のブドウから造った濃厚で美味しいぶどうジュースを用意しています。市販のジュースとは一線を画すその味わいは、試してみる価値が大いにあります。
- 見学や雰囲気の享受: 試飲ができなくても、美しいブドウ畑の景観を楽しんだり、歴史ある醸造所を見学したり、ワイン造りの話を聞いたりと、五感で楽しめる要素はたくさんあります。
- お土産選びの楽しみ: 試飲は同乗者に任せ、その感想を参考にしながら、自宅で楽しむためのお気に入りの一本をじっくり選ぶのも大きな楽しみです。
結論として、事前にグループ内で「誰が運転に徹するか」を明確に決め、そのルールを全員が守ることで、車でのワイナリー巡りは非常に快適で楽しいものになります。 運転手の協力に感謝し、全員で素晴らしい思い出を作りましょう。