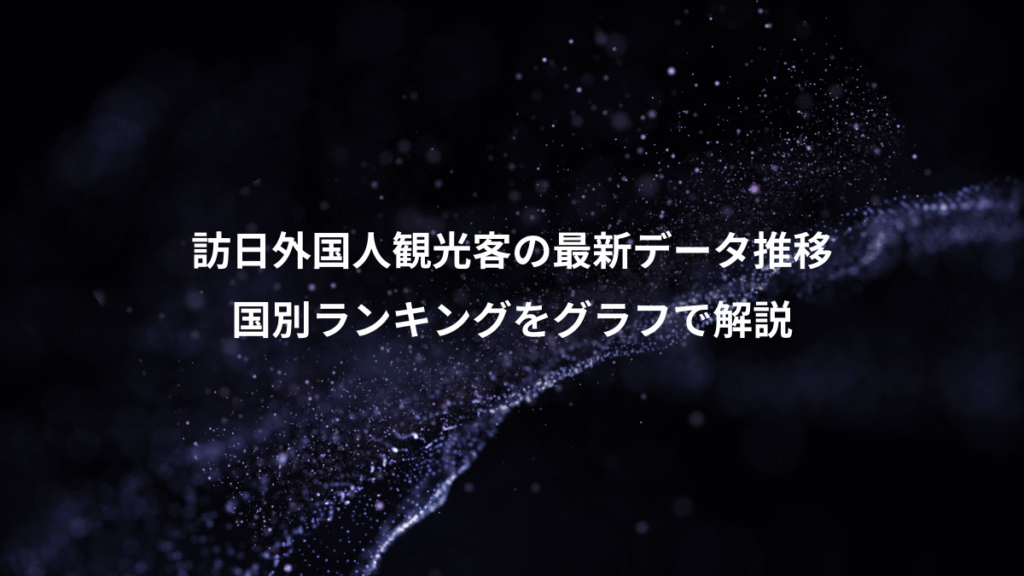日本を訪れる外国人観光客、いわゆるインバウンド市場は、近年目覚ましい回復と成長を遂げています。円安や水際対策の緩和を追い風に、その数はコロナ禍以前の記録を塗り替える勢いを見せており、日本の観光産業はもちろん、経済全体にも大きな影響を与えています。
しかし、その実態を正確に把握するためには、最新のデータを多角的に分析することが不可欠です。どの国・地域から、どれくらいの人が、どのような目的で日本を訪れ、何にお金を使っているのでしょうか。また、過去から現在に至るまでの推移には、どのような背景があるのでしょうか。
この記事では、政府の公式統計データを基に、訪日外国人観光客に関する最新の動向を徹底的に解説します。月別の推移から国・地域別ランキング、消費動向、そして未来の展望まで、グラフや表を交えながら、誰にでも分かりやすく、そして深く掘り下げていきます。インバウンドビジネスに関わる方はもちろん、日本の現状を知りたいすべての方にとって、必見の情報が満載です。
目次
訪日外国人観光客とは
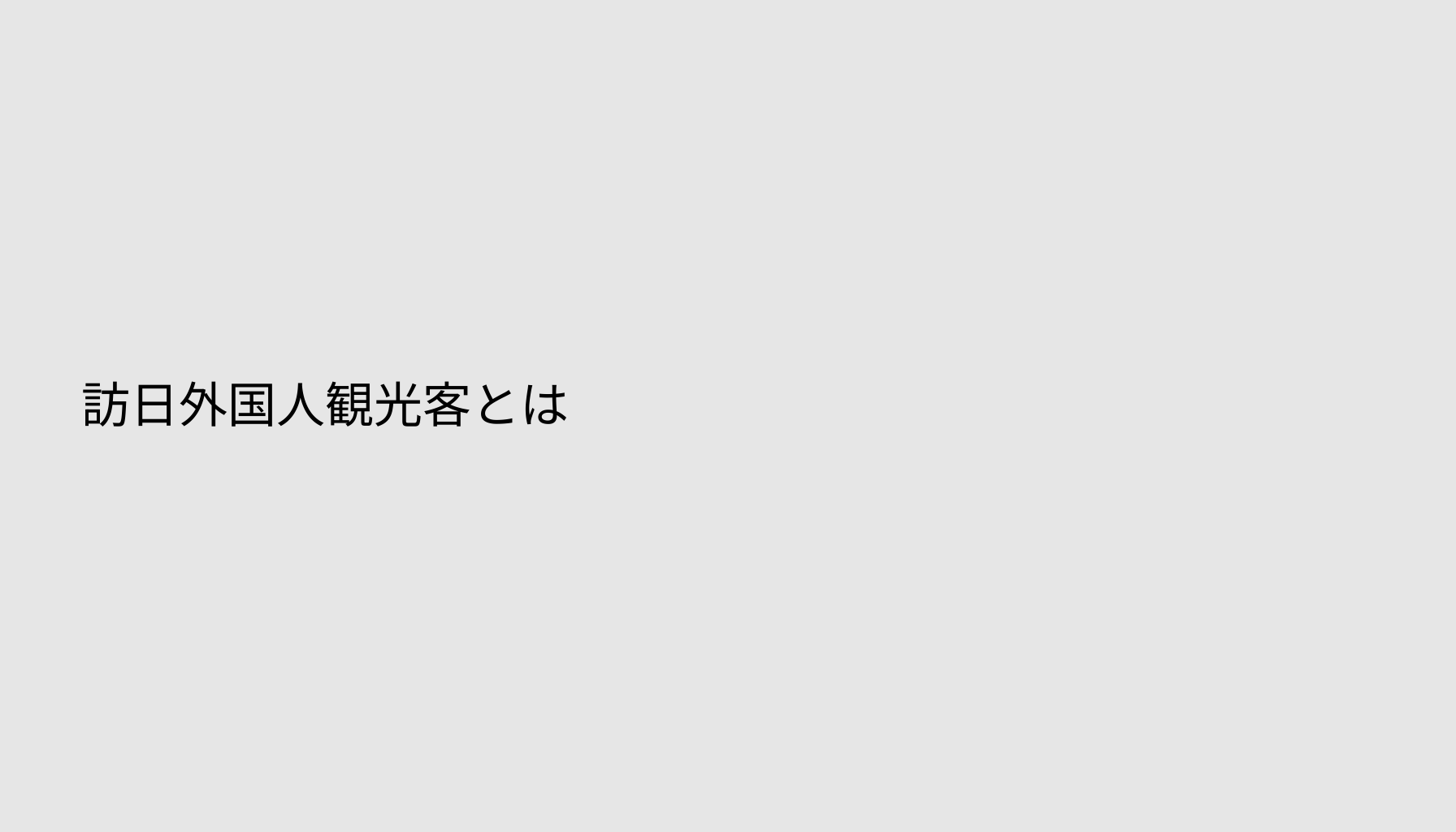
インバウンド市場を理解する上で、まず基本となるのが「訪日外国人観光客」という言葉の定義です。関連用語である「インバウンド」との違いと併せて、その正確な意味を把握しておきましょう。
「訪日外国人観光客」の定義
一般的に「訪日外国人観光客」という言葉が使われる際、その統計的な根拠となるのは、日本政府観光局(JNTO)が発表する「訪日外客数」です。この「訪日外客」とは、外国人正規入国者から、日本に居住する外国人を除いた、短期滞在の外国人を指します。
より具体的には、出入国在留管理庁の「出入国管理統計」を基に、JNTOが独自に算出しています。この統計における「外国人正規入国者」とは、日本に入国が許可された外国人の総数ですが、ここには日本での生活を前提とした「永住者」や「定住者」、その配偶者などが含まれています。インバウンド市場の動向を測る上では、これらの人々は「観光客」とは性質が異なるため、除外する必要があります。
そこで、「外国人正規入国者」の総数から、以下の在留資格を持つ人々を「日本の居住者」とみなし、差し引いた数が「訪日外客数」として集計されます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永住者
さらに、航空機や船舶の乗員(クルー)も観光目的ではないため、この集計からは除外されます。
つまり、「訪日外客数」とは、観光、ビジネス、親族訪問、留学、研修など、様々な目的で日本に短期的に滞在する外国人の総数と定義できます。
重要な点として、JNTOが発表する「訪日外客数」は、目的別に「観光」「商用」「その他」の3つに分類されています。私たちが一般的にイメージする「訪日外国人観光客」は、このうちの「観光」目的の旅行者を指しますが、報道や公的な資料で単に「訪日外客数」と記されている場合は、ビジネス客や留学生などを含む全体の数値を指していることがほとんどです。
この記事で扱うデータも、特に断りがない限り、この観光客、商用客、その他の目的の来訪者をすべて含んだ「訪日外客数」を基本としています。この定義を理解しておくことで、各種データをより正確に解釈できるようになります。
「インバウンド」との違い
「訪日外国人観光客」と非常によく似た文脈で使われる言葉に「インバウンド」があります。両者は密接に関連していますが、その指し示す範囲には微妙な違いがあります。
「インバウンド(inbound)」は、もともと「内向きの」「入ってくる」といった意味を持つ英語です。これが観光業界で使われる場合、「外国から日本へやってくる旅行」そのものや、それに関連する市場全体を指す、より広範な概念として用いられます。
以下に、両者の違いを整理してみましょう。
| 用語 | 指し示す対象 | 具体的な使われ方の例 |
|---|---|---|
| 訪日外国人観光客 | 日本を訪れる「人」そのもの。具体的な旅行者個人やその集団を指す。 | 「2023年の訪日外国人観光客数は約2,507万人だった」「韓国からの訪日外国人観光客が増加している」 |
| インバウンド | 外国人の訪日旅行という「現象」や「市場」全体。関連するビジネスや経済活動を含む。 | 「インバウンド需要を取り込む」「インバウンド消費の動向」「インバウンド対策を強化する」 |
このように、「訪日外国人観光客」がミクロな視点で「人」に焦点を当てているのに対し、「インバウンド」はマクロな視点で「市場」や「ビジネス」を捉える際に使われる傾向があります。
例えば、「インバウンドビジネス」という言葉は、訪日外国人観光客を対象とした宿泊業、飲食業、小売業、交通機関、体験サービスなど、関連するあらゆる産業を包含します。また、「インバウンド対策」と言えば、多言語対応、Wi-Fi環境の整備、キャッシュレス決済の導入、免税手続きの簡素化など、訪日客を受け入れるための環境整備全般を指します。
結論として、「訪日外国人観光客」はインバウンド市場を構成する最も重要な要素であり、その動向がインバウンド市場全体の規模や方向性を決定づけると言えます。この二つの言葉の意味を正しく使い分けることで、関連するニュースやレポートの理解がより一層深まるでしょう。
【2024年最新】訪日外国人観光客数の動向
日本のインバウンド市場は、2022年10月の水際対策大幅緩和以降、驚異的な回復を続けています。ここでは、日本政府観光局(JNTO)が発表する最新の統計データに基づき、2024年の訪日外国人観光客数の動向を詳しく見ていきます。
最新の月次データ
JNTOの最新の発表によると、2024年5月の訪日外客数(推計値)は3,040,100人となり、2019年同月比で9.6%増となりました。これにより、2024年3月から3ヶ月連続で単月300万人を超えるという、過去にない水準に達しています。
2024年に入ってからの月次推移を見ると、インバウンド市場の力強い成長が明確に見て取れます。
| 年月 | 訪日外客数(推計値) | 2019年同月比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 2,688,100人 | ±0.0% | 2019年同月とほぼ同水準まで回復 |
| 2024年2月 | 2,788,000人 | +7.1% | 閏年の影響もあり、2月として過去最高を記録 |
| 2024年3月 | 3,081,600人 | +11.6% | 単月で初めて300万人を突破。桜のシーズンが追い風 |
| 2024年4月 | 3,042,900人 | +4.0% | 2ヶ月連続の300万人超え |
| 2024年5月 | 3,040,100人 | +9.6% | 3ヶ月連続の300万人超え。欧米豪や中東で大幅増 |
参照:日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数(2024年5月推計値)
この好調な推移の背景には、複数の要因が複合的に絡み合っています。
第一に、歴史的な円安が最大の追い風となっています。外国人旅行者にとって、日本の商品やサービスが自国通貨建てで非常に割安になっており、これが日本への旅行意欲を強力に刺激しています。特に、購買力の高い欧米豪からの旅行者にとっては、より質の高い宿泊施設や食事、体験にお金を使うインセンティブとなっています。
第二に、国際航空便の回復が進んでいることが挙げられます。コロナ禍で大幅に減便されていた日本と世界各地を結ぶ航空路線が、着実に復便・増便されています。特に、東アジアや東南アジアを結ぶLCC(格安航空会社)の便数が回復してきたことで、気軽に日本を訪れる旅行者が増加しています。
第三に、継続的なプロモーション活動の効果も無視できません。JNTOや各自治体、民間企業が連携し、海外の旅行博への出展やSNSを通じた情報発信を積極的に行った結果、日本の多様な魅力が海外で広く認知されるようになりました。特に、アニメや漫画といったポップカルチャー、豊かな自然を活かしたアドベンチャーツーリズム、各地のユニークな食文化などが、新たな訪日リピーター層の開拓に繋がっています。
2024年3月以降、3ヶ月連続で300万人を超える水準で推移していることは、日本のインバウンド市場が新たな成長フェーズに入ったことを示唆しています。これはもはや単なる「回復」ではなく、コロナ禍前を上回る「成長」と言えるでしょう。
国・地域別の最新状況
全体の訪日客数が好調に推移する中で、国・地域別の動向を見ると、その回復度合いには濃淡があります。2024年5月のデータを見ると、全体の傾向がより鮮明になります。
2024年5月の訪日客数を国・地域別に見ると、トップは韓国(738,800人)、次いで中国(545,400人)、台湾(466,000人)、香港(217,500人)、米国(183,500人)と続きます。
特筆すべきは、調査対象の23市場のうち、13市場(韓国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、イタリア、北欧地域、中東地域(サウジアラビア、UAE、カタール、イスラエル)、インドネシア、ベトナム、インド、フィリピン)で5月として過去最高を記録した点です。
- 東アジア市場(韓国、台湾、香港):
地理的な近さや航空便の多さから、引き続きインバウンド市場全体を牽引する中心的な存在です。特に韓国は、2019年同月比で43.3%増と驚異的な伸びを見せており、市場の力強さを象徴しています。台湾も15.1%増と好調を維持しており、安定したリピーター層が市場を支えています。 - 欧米豪・中東市場:
円安の恩恵を最も受けているのがこれらの市場です。米国(+35.7%)、カナダ(+31.3%)、メキシコ(+60.8%)、ドイツ(+31.7%)、イタリア(+56.4%)、そして中東4カ国(+86.0%)など、軒並み2019年同月比で30%以上の高い伸び率を記録しています。これらの国からの旅行者は滞在期間が長く、一人当たりの消費額も高い傾向があるため、インバウンド消費額を押し上げる重要な要因となっています。 - 中国市場:
一方で、コロナ禍前には最大の市場であった中国は、2019年同月比で27.9%減と、主要市場の中で回復が遅れています。2023年8月に日本への団体旅行が解禁されましたが、その回復ペースは緩やかです。この背景には、中国国内の経済状況、航空便の回復ペースが他の地域に比べて遅いこと、そして旅行形態がかつての団体旅行中心から個人旅行(FIT)へとシフトしていることなどが挙げられます。しかし、545,400人という絶対数はいまだに全市場で2番目に多く、そのポテンシャルは依然として巨大です。今後の回復ペースが、インバウンド市場全体の成長率を左右する鍵となるでしょう。
このように、現在のインバウンド市場は、韓国を中心とする東アジア市場が安定した基盤となり、円安を追い風とした欧米豪・中東市場が成長を力強く牽引するという構図になっています。一方で、巨大市場である中国の回復が今後の大きな伸びしろとして期待される状況です。
2023年の国・地域別訪日外国人観光客数ランキングTOP10
2023年は、日本のインバウンド市場が本格的な回復軌道に乗った記念すべき年となりました。年間の訪日外客数は25,066,100人に達し、過去最高だった2019年(31,882,049人)の78.6%まで回復しました。ここでは、2023年通年の国・地域別ランキングTOP10を詳しく見ていきながら、各市場の特性を解説します。
| 順位 | 国・地域 | 2023年 訪日客数 | 構成比 | 2019年比 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 韓国 | 6,958,500人 | 27.8% | +24.6% |
| ② | 台湾 | 4,202,400人 | 16.8% | -14.0% |
| ③ | 香港 | 2,114,400人 | 8.4% | -7.7% |
| ④ | アメリカ | 2,045,900人 | 8.2% | +19.3% |
| ⑤ | 中国 | 2,425,000人 | 9.7% | -74.7% |
| ⑥ | タイ | 995,500人 | 4.0% | -24.4% |
| ⑦ | フィリピン | 622,300人 | 2.5% | +21.9% |
| ⑧ | カナダ | 420,100人 | 1.7% | +17.1% |
| ⑨ | オーストラリア | 611,600人 | 2.4% | -1.7% |
| ⑩ | ベトナム | 574,200人 | 2.3% | +15.7% |
※順位は見出しの指定に準拠。人数ベースでは5位は中国となる。
参照:日本政府観光局(JNTO) 2023年 年間推計値
① 韓国
2023年、訪日客数で圧倒的なトップに立ったのが韓国です。その数は約696万人に達し、訪日客全体の4分の1以上を占める最大の市場となりました。さらに特筆すべきは、コロナ禍前の2019年と比較しても24.6%増と、大幅に数字を伸ばしている点です。
この背景には、地理的な近さがもたらす手軽さがあります。ソウルから福岡まで約1時間半、東京まで約2時間半というアクセスの良さに加え、LCCの便数が非常に豊富なため、週末や短い休暇を利用して気軽に日本を訪れることができます。
また、K-POPや韓国ドラマ、映画などを通じて日本の若者文化に関心を持つ層がいるのと同様に、韓国でも日本のアニメや食、ファッションといった文化への関心が高く、特に若者層を中心に訪日旅行の人気が定着しています。旅行スタイルとしては、グルメやショッピングをメインに、最新のトレンドスポットを巡る短期滞在型が主流です。リピーターも非常に多く、東京や大阪といった大都市だけでなく、福岡、札幌、沖縄など地方都市への訪問が活発なのも特徴です。
② 台湾
長年にわたり、日本のインバウンド市場を支えてきた重要なパートナーが台湾です。2023年は約420万人が訪日し、韓国に次ぐ第2位となりました。人口が約2,300万人であることを考えると、驚異的な訪日率の高さです。
台湾市場の最大の特徴は、親日的な国民性と、非常に高いリピート率にあります。日本の文化や習慣への理解が深く、日本語を話せる人も少なくありません。そのため、旅行の満足度が高く、何度も日本を訪れる旅行者が後を絶ちません。
旅行スタイルは個人旅行が主流で、大都市だけでなく、地方の温泉地や景勝地、田園風景などをゆっくり楽しむ旅を好む傾向があります。特に日本の鉄道網への関心が高く、JRパスなどを活用して日本各地を周遊する鉄道ファンも多いことで知られています。2019年比ではまだマイナスですが、回復は順調に進んでおり、今後も安定した市場であり続けることは間違いないでしょう。
③ 香港
第3位は、約211万人が訪日した香港です。人口約730万人という都市国家からこれだけの数の旅行者が訪れるという事実は、日本がいかに香港の人々にとって魅力的な旅行先であるかを物語っています。
香港市場は、流行に敏感で、最新の情報を基に旅行計画を立てる層が多いのが特徴です。グルメ、ショッピング、季節のイベント(桜や紅葉)など、明確な目的を持って訪日するケースが多く見られます。所得水準も比較的高く、高級なレストランでの食事やブランド品の購入など、消費意欲も旺盛です。
台湾と同様にリピーターが非常に多く、短い休暇を利用して年に何度も日本を訪れるヘビーリピーターが市場を支えています。彼らは定番の観光地だけでなく、ガイドブックには載っていないような隠れた名店やスポットを探し出すことにも長けています。
④ アメリカ
欧米豪市場の筆頭として第4位にランクインしたのがアメリカです。約205万人が訪日し、2019年比で19.3%増と大幅な伸びを記録しました。
この躍進の最大の要因は、歴史的な円安です。米ドルに対して円の価値が下がったことで、アメリカの旅行者にとって日本での滞在費や買い物が非常に割安になりました。これにより、これまで高嶺の花だった日本旅行が身近になり、多くの観光客が訪れる結果となりました。
アメリカからの旅行者は、滞在期間が比較的長く、伝統文化や自然景観への関心が高い傾向があります。東京、箱根、京都、大阪を結ぶ「ゴールデンルート」が依然として人気ですが、スキーやスノーボードを楽しむために北海道や長野を訪れたり、日本の精神文化に触れるために高野山で宿坊体験をしたりと、目的は多様化しています。高い消費額も魅力であり、日本経済への貢献度も非常に高い市場です。
⑤ 中国
コロナ禍前まで長年にわたり訪日客数トップを独走していた中国は、2023年は約243万人で、2019年比では74.7%減と大幅に落ち込みました。これは、他国に比べて水際対策の緩和や団体旅行の解禁が遅れたことが主な原因です。
しかし、そのポテンシャルが失われたわけではありません。絶対数では依然としてトップクラスであり、回復が本格化すれば、再び市場の様相を大きく変える力を持っています。
現在の中国市場では、かつての「爆買い」に象徴される団体旅行から、より深い体験を求める個人旅行(FIT)へのシフトが顕著に進んでいます。彼らは、定番の観光地巡りだけでなく、アニメの聖地巡礼、地方の伝統工芸体験、美容医療ツアーなど、よりパーソナルで専門的なテーマに関心を持っています。今後のインバウンド市場の行方を占う上で、中国の個人旅行層の動向が最も重要な鍵となります。
⑥ タイ
東南アジア市場を代表するのがタイで、約99.5万人が訪日しました。2013年のビザ免除措置以降、訪日客数が飛躍的に増加し、日本はタイ人にとって最も人気のある海外旅行先の一つとして定着しています。日本の雪景色への憧れが強く、冬の北海道は特に人気が高いデスティネーションです。また、日本のキャラクターや食文化への関心も高く、ショッピングや食べ歩きを楽しむ旅行者が多く見られます。
⑦ フィリピン
約62万人が訪日し、2019年比で21.9%増と高い伸びを見せたのがフィリピンです。経済成長を背景に中間層が拡大し、海外旅行への関心が高まっています。特に日本の四季の美しさ、テーマパーク、そして清潔で安全な都市環境が魅力とされています。英語が公用語の一つであるため、コミュニケーションのハードルが比較的低いことも、旅行先として日本が選ばれる理由の一つです。
⑧ カナダ
アメリカと同様に、円安を追い風に訪日客数を大きく伸ばしたのがカナダです。約42万人が訪日し、2019年比で17.1%増となりました。カナダの旅行者は、日本の豊かな自然を活かしたアクティビティへの関心が高く、特に北海道や長野でのスキー・スノーボードは世界的に有名で、多くのカナダ人スキーヤーを惹きつけています。長期滞在者が多く、消費単価も高い優良な市場です。
⑨ オーストラリア
南半球に位置するオーストラリアは、季節が逆になるため、日本の冬を「サマースキー」として楽しむ旅行者が多いことで知られています。2023年は約61万人が訪日し、コロナ禍前とほぼ同水準まで回復しました。スキーリゾートだけでなく、日本の食文化や伝統文化への関心も高く、親日的でリピーターも多いのが特徴です。
⑩ ベトナム
経済成長が著しいベトナムは、インバウンド市場における「ネクストスター」として注目されています。2023年は約57万人が訪日し、2019年比で15.7%増と好調でした。技能実習生や留学生として日本に滞在する人が多いことも、両国間の人的交流を活発にし、観光旅行の増加に繋がっています。親日的な国民性で、日本の質の高い製品やサービス、美しい桜などに強い憧れを持っています。
訪日外国人観光客数の年別推移(2003年~2023年)
現在のインバウンド市場の活況を理解するためには、過去からの長期的な視点が欠かせません。ここでは、日本政府が「ビジット・ジャパン事業」を開始した2003年から、コロナ禍を経て回復を遂げた2023年までの約20年間の推移を振り返ります。この間の変動は、日本の観光政策、世界経済、そして国際情勢の写し鏡と言えるでしょう。
| 年 | 訪日外客数 | 前年比 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 5,211,725人 | -1.1% | ビジット・ジャパン事業開始、SARS流行 |
| 2008 | 8,350,835人 | +11.0% | リーマンショック発生 |
| 2011 | 6,218,752人 | -27.8% | 東日本大震災発生 |
| 2013 | 10,363,918人 | +24.0% | 初の1,000万人突破、東京五輪開催決定 |
| 2015 | 19,737,409人 | +47.1% | 中国からの訪日客による「爆買い」が流行語に |
| 2016 | 24,039,700人 | +21.8% | 初の2,000万人突破 |
| 2018 | 31,191,856人 | +8.7% | 初の3,000万人突破 |
| 2019 | 31,882,049人 | +2.2% | 過去最高記録を更新 |
| 2020 | 4,115,828人 | -87.1% | 新型コロナウイルス感染症拡大、世界的な渡航制限 |
| 2021 | 245,862人 | -94.0% | 東京五輪(無観客開催)、厳しい水際対策の継続 |
| 2022 | 3,832,110人 | +1458.5% | 水際対策の大幅緩和(10月)、個人旅行解禁 |
| 2023 | 25,066,100人 | +554.3% | コロナ禍前の約8割までV字回復 |
参照:日本政府観光局(JNTO) 年別 訪日外客数, 出国日本人数の推移(1964年-2023年)
この20年間の推移は、大きく4つの時期に分けることができます。
① 黎明期(2003年~2010年):観光立国への助走
2003年、政府は「ビジット・ジャパン事業(現:ビジット・ジャパン観光プロモーション事業)」を開始し、国を挙げて外国人観光客の誘致に乗り出しました。当初は年間500万人規模だった訪日客数は、韓国や台湾へのビザ免除、海外でのプロモーション強化などにより、緩やかな増加基調をたどります。2008年にはリーマンショックの影響で一時的に落ち込みますが、それでも年間800万人台まで成長し、観光立国としての土台が築かれた時期でした。
② 急成長期(2011年~2019年):未曾有のインバウンドブーム
2011年の東日本大震災により、訪日客数は622万人まで激減し、インバウンド市場は深刻な打撃を受けました。しかし、ここから日本は驚異的なV字回復と成長を遂げます。
この急成長を支えたのは、①円安の進行、②東南アジア諸国へのビザ発給要件緩和、③LCC(格安航空会社)の就航拡大、④免税制度の拡充といった複数の好条件が重なったことでした。
2013年には念願の1,000万人を突破。2015年には中国人観光客による「爆買い」が社会現象となり、消費額も大きく押し上げられました。その後も勢いは止まらず、2016年に2,000万人、2018年には3,000万人と、わずか5年で3倍に増加するという、まさに未曾有のインバウンドブームが到来しました。そして2019年には、3,188万人という歴代最高の金字塔を打ち立てます。
③ 停滞期(2020年~2022年前半):コロナ禍による断絶
栄華を極めたインバウンド市場は、2020年初頭からの新型コロナウイルスの世界的なパンデミックによって一変します。各国で厳しい渡航制限が敷かれ、日本も例外ではありませんでした。訪日客数は激減し、2021年にはわずか25万人弱と、1964年の統計開始以来、最低水準にまで落ち込みました。全国の観光地から外国人観光客の姿が消え、インバウンド関連事業者は壊滅的な打撃を受けました。これは、インバウンドがいかに国際情勢に左右されやすい、脆弱な側面を持つかを浮き彫りにした時期でもありました。
④ 回復・新成長期(2022年後半~現在):力強い復活と新たなステージ
長く続いた停滞期に転機が訪れたのは、2022年10月11日です。政府が水際対策を大幅に緩和し、ビザなし渡航と個人旅行が再開されると、堰を切ったように外国人観光客が戻り始めました。この回復を強力に後押ししたのが、歴史的な円安です。
2023年には年間で2,500万人を超える水準まで回復。そして2024年に入ると、コロナ禍前の2019年を上回るペースで推移しており、市場は単なる「回復」から、新たな高みを目指す「新成長期」へと移行しています。この力強い復活は、日本の観光コンテンツが持つ普遍的な魅力と、変化に対応してきた官民の努力の賜物と言えるでしょう。
訪日外国人観光客の消費動向データ
訪日外国人観光客の「数」だけでなく、彼らが日本でどれくらいのお金を使っているのか、すなわち「消費額」を把握することは、インバウンドの経済効果を測る上で極めて重要です。ここでは、観光庁が定期的に実施している「訪日外国人消費動向調査」の最新データに基づき、その実態に迫ります。
最新の旅行消費額(2024年1-3月期)
観光庁の最新の発表によると、2024年1-3月期の訪日外国人旅行消費額は、推計で1兆7,505億円に達しました。これは、これまで過去最高だった2023年10-12月期の1兆6,688億円をさらに上回り、四半期ベースで過去最高額を更新する結果となりました。
コロナ禍前の2019年同期(1兆118億円)と比較すると、実に73.3%増という驚異的な伸び率です。訪日客数が2019年同期比で17.5%増であったことを考えると、客数の伸びをはるかに上回るペースで消費額が拡大していることがわかります。このデータは、現在のインバウンド市場が「量」だけでなく「質」の面でも大きな成長を遂げていることを明確に示しています。
この力強い消費の背景には、前述の円安効果に加え、一人当たりの旅行支出の増加が大きく寄与しています。
2023年(年間)の旅行消費額
2024年の好調さを理解するため、まずは回復を確固たるものにした2023年通年のデータを見てみましょう。
2023年の年間の訪日外国人旅行消費額は、確報値で5兆3,065億円となりました。これは、コロナ禍前の2019年の4兆8,135億円を上回り、年間ベースで過去最高額を記録しました。政府が「観光立国推進基本計画」で掲げていた「インバウンド消費額5兆円の早期達成」という目標を、見事にクリアした形です。
ここで注目すべきは、2023年の訪日客数は2019年の約8割(78.6%)であったにもかかわらず、消費総額では2019年を上回ったという事実です。これは、訪日客一人ひとりが使う金額が、コロナ禍前よりも大幅に増加したことを意味しています。
一人当たりの旅行支出額
訪日客数の回復を上回るペースで消費額が伸びている最大の要因は、一人当たりの旅行支出(単価)の上昇です。
- 2024年1-3月期の一人当たり旅行支出は、推計で208,760円。2019年同期(147,560円)と比較して41.5%増加しています。
- 2023年年間の一人当たり旅行支出は、212,586円。2019年(158,531円)と比較して34.1%増加しています。
なぜ、これほどまでに旅行単価が上昇しているのでしょうか。その理由は、主に以下の4点が考えられます。
- 円安効果: 自国通貨の価値が高い外国人旅行者にとって、日本の商品やサービスが割安に感じられるため、より高価な宿泊施設を選んだり、買い物や食事にお金をかけたりする傾向が強まっています。
- 滞在日数の長期化: コロナ禍を経て、特に欧米豪からの旅行者を中心に、一度の旅行で長く滞在し、じっくりと日本を体験しようという傾向が見られます。滞在日数が延びれば、それに比例して支出額も増加します。
- 旅行スタイルの変化: かつての団体旅行に比べて、個人旅行(FIT)は自由度が高く、自分の興味関心に合わせてお金を使うことができます。高付加価値な体験(プライベートガイドツアー、高級旅館での滞在など)への支出が増えていることも、単価を押し上げる一因です。
- 物価・サービス価格の上昇: 日本国内のインフレや、深刻な人手不足を背景とした宿泊料金・サービス料金の値上げが、そのまま旅行支出額に反映されている側面もあります。
国・地域別に見ると、特に欧米豪からの旅行者の支出額の高さが際立ちます。2023年のデータでは、英国(34.1万円)、スペイン(33.6万円)、イタリア(33.4万円)などが上位を占めており、これらの国からの旅行者数の増加が全体の単価を押し上げていることが分かります。
費目別の消費内訳
では、訪日外国人観光客は具体的に何にお金を使っているのでしょうか。2023年(年間)の消費額5兆3,065億円の内訳を見てみましょう。
| 費目 | 金額(億円) | 構成比 | 2019年比(構成比) |
|---|---|---|---|
| 宿泊費 | 1兆8,343億円 | 34.6% | +4.4ポイント |
| 買物代 | 1兆4,046億円 | 26.5% | -8.3ポイント |
| 飲食費 | 1兆1,953億円 | 22.5% | +0.9ポイント |
| 交通費 | 6,050億円 | 11.4% | +2.0ポイント |
| 娯楽等サービス費 | 2,673億円 | 5.0% | +1.0ポイント |
参照:観光庁 訪日外国人消費動向調査 2023年年次報告書
このデータから、いくつかの重要なトレンドが読み取れます。
第一に、最大の支出項目は「宿泊費」であり、全体の3分の1以上を占めています。コロナ禍前(2019年)と比較して構成比が4.4ポイントも上昇しており、全国的なホテル単価の高騰が全体の消費額を押し上げている主要因であることがわかります。
第二に、かつて「爆買い」でインバウンド消費を象徴した「買物代」の構成比は、2019年から8.3ポイントと大幅に減少しています。これは、旅行の目的がモノの購入(モノ消費)から、体験や経験(コト消費)へとシフトしていることを示す明確な証拠です。
第三に、宿泊費に加えて「飲食費」「交通費」「娯楽等サービス費」の構成比が軒並み上昇しています。これは、旅行者が日本ならではの食事を楽しんだり、地方へ足を延ばしたり、様々な文化体験やアクティビティに参加したりすることに、より多くのお金を使うようになったことを意味します。
総じて、現在のインバウンド消費は、宿泊を基盤としつつ、食や体験といった「コト消費」に重点が置かれた、より成熟したバランスの良い構造へと変化していると言えるでしょう。
訪日外国人が日本で体験したいことTOP5
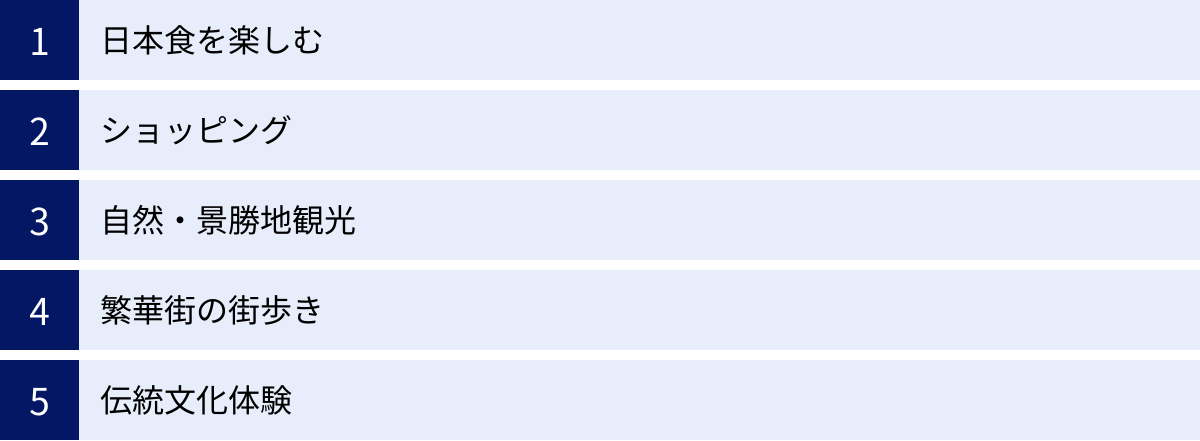
訪日外国人観光客は、日本の何に魅力を感じ、どのような体験を求めて来日するのでしょうか。観光庁の「訪日外国人の消費動向」調査における「訪日前に最も期待していたこと」のデータを基に、人気の体験トップ5を解説します。これらのニーズを理解することは、効果的なインバウンド誘致戦略を立てる上で不可欠です。
① 日本食を楽しむ
訪日前に期待することとして、常に圧倒的な1位を維持しているのが「日本食を楽しむ」ことです。寿司、ラーメン、天ぷらといった世界的に有名な料理はもちろんのこと、焼肉、うなぎ、そば、うどんといった多様な専門料理、さらにはB級グルメの代表格であるたこ焼きやお好み焼き、そして見た目も美しい和菓子まで、日本の食文化の奥深さと幅広さが、国籍を問わず多くの旅行者を惹きつけています。
日本食がこれほどまでに支持される理由は複数あります。
- 質の高さと美味しさ: 素材の味を活かす調理法、職人の技術、衛生管理の徹底など、日本の食は全体的にレベルが高いと評価されています。
- 多様性: 高級な懐石料理から、手軽な立ち食いそば、活気あふれる居酒屋、地域の特色が詰まった郷土料理まで、予算やシーンに応じて無限の選択肢があります。
- 健康的なイメージ: ユネスコ無形文化遺産にも登録された「和食」は、栄養バランスに優れた健康的な食事として世界的に認知されています。
- 視覚的な魅力: 料理の美しい盛り付けや、精巧に作られた食品サンプル、活気のある市場の様子など、目で見ても楽しめる要素が豊富です。
具体的な体験としては、豊洲市場や各地の朝市での新鮮な海産物の食べ歩き、ラーメン激戦区での人気店巡り、デパ地下での多種多様な惣菜やスイーツの購入、地方の酒蔵見学と日本酒の試飲などが人気です。食は、それ自体が旅の主目的となり得る、最強の観光コンテンツであり、食をフックにした地方誘客の可能性は非常に大きいと言えます。
② ショッピング
日本でのショッピングは、長年にわたり外国人観光客にとって大きな楽しみの一つです。特に円安が続く現在は、海外の旅行者にとって日本の製品が非常にお得に購入できるため、その魅力は一層高まっています。
人気のある商品は多岐にわたります。
- 化粧品・医薬品: 高品質で種類が豊富な日本の化粧品や、ユニークな機能を持つ医薬品・健康グッズは、特にアジアからの旅行者に絶大な人気を誇ります。
- 菓子類: 抹茶味のキットカットに代表されるような、日本ならではのフレーバーを持つお菓子は、お土産の定番です。パッケージの美しさも評価されています。
- アニメ・キャラクターグッズ: アニメイトやポケモンセンター、ジブリパークなど、日本発のコンテンツに関連する商品は、世界中のファンにとって垂涎の的です。
- 日本ブランドの製品: ユニクロのようなファッションブランド、高品質な文房具、精密な家電製品など、日本の「ものづくり」に対する信頼は厚く、多くの旅行者が購入していきます。
買い物の場所も、百貨店、ドラッグストア、家電量販店、100円ショップ、アウトレットモールなど様々です。しかし、訪日客が評価しているのは商品の魅力だけではありません。店員の丁寧な接客態度、美しいラッピング、清潔な店内といった、日本ならではの「おもてなし」を含んだ購買体験そのものが、大きな付加価値となっています。
③ 自然・景勝地観光
日本の国土の約7割は森林であり、南北に長い国土は多様な自然環境を育んでいます。この四季折々の美しい自然や、独特の景観も、訪日旅行の大きな魅力となっています。
- 四季の彩り: 春の桜、初夏の青々とした緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節ごとに全く異なる表情を見せる風景は、特に熱帯や亜熱帯地域からの旅行者にとって強い憧れの対象です。
- 象徴的な景観: 世界文化遺産である富士山は、日本のシンボルとして圧倒的な知名度を誇ります。他にも、京都の竹林の道、鳥取砂丘、沖縄の青い海など、ユニークな景勝地が数多く存在します。
- アクティビティとの融合: 近年、単に自然を眺めるだけでなく、その中で体を動かす「アドベンチャーツーリズム」への関心が高まっています。北海道ニセコでのパウダースノー体験、瀬戸内しまなみ海道でのサイクリング、屋久島でのトレッキングなど、自然とアクティビティを組み合わせた体験は、特に欧米豪の旅行者に人気です。
都市部の喧騒から離れ、日本の静かで美しい自然に触れることは、多くの旅行者にとって心癒される体験となっています。国立公園をはじめとする地方の自然資源は、インバウンド誘致における日本の大きな強みです。
④ 繁華街の街歩き
渋谷のスクランブル交差点、新宿のネオン街、大阪・道頓堀の巨大な立体看板など、日本の大都市が持つエネルギッシュで未来的な風景は、それ自体が一大観光コンテンツです。多くの旅行者は、映画やアニメで見たこれらの風景を実際に体験することを楽しみにして来日します。
繁華街の街歩きが人気なのは、その安全性と清潔さ、そしてカオスと秩序が同居するユニークな雰囲気にあります。夜遅くまで多くの人々が行き交うにもかかわらず、安心して散策できる環境は、世界的に見ても稀有です。
また、これらの繁華街は、最先端のファッション、グルメ、エンターテインメントが集積する場所でもあります。メインストリートを歩くだけでなく、一歩路地裏に入れば、個性的なセレクトショップや隠れ家的なバー、昔ながらの飲み屋横丁が広がっており、探検するような楽しみもあります。SNSでの「写真映え」を意識したカラフルな看板やストリートアートも多く、街歩きそのものが思い出に残るアクティビティとして認識されています。
⑤ 伝統文化体験
近代的な都市の魅力と並んで、日本の奥深い歴史や精神性に触れることができる伝統文化体験も、根強い人気を誇ります。特に、欧米豪からの知的好奇心が旺盛な旅行者にとって、重要な旅行目的の一つとなっています。
代表的な体験としては、以下のようなものが挙げられます。
- 寺社仏閣の参拝: 京都や奈良、鎌倉などの古都にある歴史的な寺社を訪れることは、多くの旅行者にとって外せない体験です。建物の美しさだけでなく、その静謐な雰囲気に魅了される人も少なくありません。
- 着物・浴衣の着用体験: 観光地で着物や浴衣をレンタルし、街を散策する体験は、手軽に日本の伝統に親しめるとして、特に女性グループやカップルに人気です。
- 各種「道」の体験: 茶道、書道、華道、武道(空手、柔道)など、日本の精神文化を体現する「道」を体験するプログラムも人気があります。専門家の指導のもと、その作法や哲学の一端に触れることは、深い感動と学びをもたらします。
これらの体験は、単なる娯楽としてだけでなく、日本の歴史や価値観をより深く理解するための手段として求められています。旅行者が「本物」の文化に触れる機会を提供することは、リピーターの創出や、日本のファンを増やす上で非常に効果的です。
今後のインバウンド市場の見通し
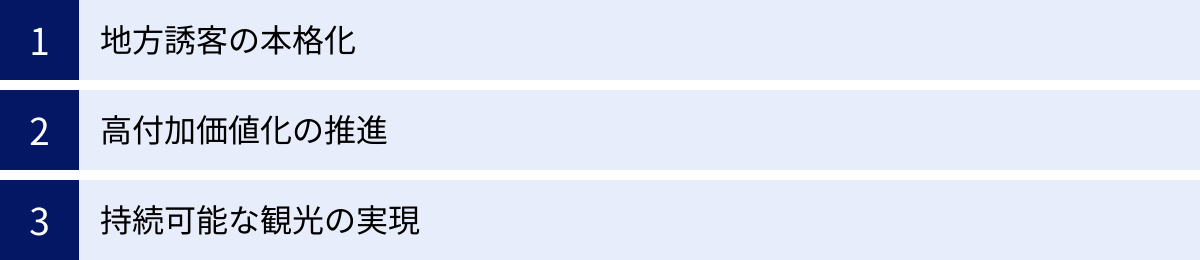
驚異的な回復力を見せる日本のインバウンド市場。その勢いは今後も続くのでしょうか。ここでは、2024年以降の短期的な展望から、2030年を見据えた中長期的な予測、そして変化する旅行者の情報収集方法まで、未来の市場動向を考察します。
2024年の展望
2024年のインバウンド市場は、極めて明るい見通しとなっています。すでに上半期(1-5月)の時点で、訪日外客数は1,464万人を超えており、これは過去最高だった2019年を上回るペースです。
このままの勢いが続けば、2024年の年間訪日外客数が、2019年の過去最高記録である3,188万人を更新することはほぼ確実と見られています。特に、夏休みシーズンや秋の紅葉シーズンに向けて、欧米豪や東南アジアからの旅行者の予約は好調に推移しており、市場の勢いは衰える気配がありません。
消費額に関しても、旅行単価の上昇が続いていることから、年間で安定的に5兆円を超えることはもちろん、6兆円台に達する可能性も十分に考えられます。
一方で、この急激な回復と成長は、新たな課題も生み出しています。
- オーバーツーリズム(観光公害): 特定の観光地に観光客が集中することで、交通渋滞、ゴミ問題、騒音、そして地域住民の生活への影響が深刻化しています。富士山の登山規制や、京都での観光客向けバス路線の新設など、対策が急務となっています。
- 人手不足と宿泊料金の高騰: 観光業界全体で人手不足が深刻化しており、サービスの質の維持が課題となっています。また、需要の急増により全国的にホテル料金が高騰し、旅行者の満足度低下や、日本人国内旅行者の旅行控えに繋がる懸念もあります。
2024年は、過去最高の「量」を達成すると同時に、これらの課題にいかに向き合い、「質」の高い持続可能な観光へと転換できるかが問われる、重要な一年となるでしょう。
2025年以降の予測
2025年以降のインバウンド市場を占う上で、最大の起爆剤となるのが2025年4月から開催される「大阪・関西万博」です。万博の開催期間中には、世界中から多くのビジネス客や観光客が訪れることが予想され、インバウンド市場をさらに一段階押し上げる大きなきっかけとなります。
政府は、改定された「観光立国推進基本計画」の中で、以下の野心的な目標を掲げています。
- 2025年までに、訪日外国人旅行者数を2019年水準(3,188万人)超え
- 2025年までに、訪日外国人旅行消費額単価を20万円(2019年比約25%増)
- 訪日外国人旅行消費額を早期に7兆円
さらに中長期的には、「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円」という、極めて高い目標を設定しています。
これらの目標を達成するためには、もはや既存の延長線上にある取り組みだけでは不十分です。以下の3つの視点が鍵となります。
- 地方誘客の本格化: 現在の観光客は依然として東京・大阪・京都のゴールデンルートに集中しています。日本の多様な魅力を伝え、全国各地に観光客を分散させることで、オーバーツーリズムを緩和し、地方経済を活性化させる必要があります。
- 高付加価値化の推進: 一人当たりの消費額をさらに高めるため、富裕層をターゲットにしたオーダーメイドの旅行商品や、ユニークな文化体験、長期滞在を促すコンテンツの開発が求められます。
- 持続可能な観光(サステナブルツーリズム)の実現: 地域の自然環境や文化、住民の生活を守りながら観光を発展させるという視点が不可欠です。環境負荷の少ない交通手段の推進や、文化遺産の保全活動への協力などを通じて、旅行者自身も持続可能性に貢献するような観光の形を目指す必要があります。
訪日旅行の意向と情報収集の方法
日本のインバウンド市場が今後も成長を続けるためには、世界の人々が日本を「行きたい国」と思い続けてくれることが大前提です。幸いなことに、各種の国際的な調査において、日本は「次に行きたい旅行先」として常にトップクラスの人気を維持しており、その潜在的な需要は非常に大きいと言えます。
しかし、その「行きたい」という気持ちを、実際の「訪日」という行動に移してもらうためには、現代の旅行者の情報収集スタイルに合わせたアプローチが不可欠です。
かつてはガイドブックや旅行代理店のパンフレット、PC向けの公式サイトが情報源の中心でした。しかし現在、その主役は完全にスマートフォンとSNSに移っています。
- 動画コンテンツの影響力: YouTubeやTikTokで、外国人インフルエンサーが日本の魅力を紹介する動画は絶大な影響力を持っています。彼らが訪れた飲食店や景勝地が、瞬く間に「聖地」として世界中の旅行者の目的地リストに加えられます。
- ビジュアル重視のSNS: Instagramでは、「#japantravel」といったハッシュタグで検索すれば、無数の美しい写真や短い動画(リール)が見つかります。旅行者はこれらのビジュアルからインスピレーションを得て、自分の旅程を組み立てます。
- リアルな口コミの価値: 個人のブログやGoogleマップのレビュー、各種旅行系口コミサイトに投稿される「本音」の評価は、広告以上に信頼される情報源となっています。
このような変化に対応するため、インバウンドビジネスに関わる事業者や自治体には、デジタルマーケティング、特にSNSを駆使した戦略的な情報発信がこれまで以上に強く求められています。単に情報を発信するだけでなく、訪れたくなるような魅力的なコンテンツを創出し、インフルエンサーや一般の旅行者によって「口コミ」が自然に拡散されるような仕組みを構築することが、未来のインバウンド市場で成功するための鍵となるでしょう。