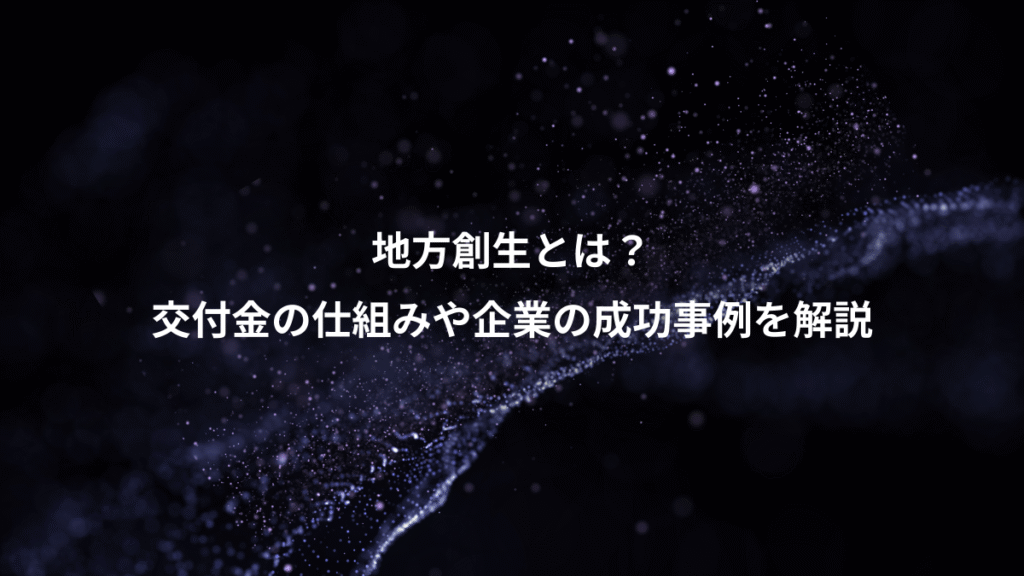日本が直面する人口減少や少子高齢化、そして東京への一極集中といった課題。これらの深刻な問題に対応し、国全体の活力を維持するために不可欠な取り組みが「地方創生」です。この言葉を耳にする機会は増えましたが、その具体的な内容や目的、そして私たち企業や個人に何ができるのかを深く理解している方はまだ多くないかもしれません。
地方創生は、単に地方の過疎化を防ぐだけではありません。それぞれの地域が持つ独自の魅力や資源を最大限に活かし、自律的で持続可能な社会を築き上げることを目指す、未来への壮大なプロジェクトです。そこには、新しいビジネスチャンスや多様な働き方の可能性が満ち溢れています。
この記事では、地方創生の基本的な定義から、その背景にある日本の課題、国が進める交付金などの支援策、企業が参画するメリット、そして私たち一人ひとりができることまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。地方創生の本質を理解し、自社の成長や個人のライフプランに繋げるための一助となれば幸いです。
目次
地方創生とは

地方創生は、現代日本が抱える構造的な課題に対応するための国家的なプロジェクトです。まずはその基本的な定義や目的、歴史的背景について理解を深めていきましょう。
地方創生の定義と目的
地方創生とは、人口減少と東京一極集中を是正し、それぞれの地域が個性を活かして自律的かつ持続可能な社会を創り上げることを目的とした、一連の政策や取り組みの総称です。単に地方に資金を投入するだけの地域振興策とは一線を画し、中長期的な視点で日本の構造を変革しようとする点が特徴です。
この取り組みの根底には、「このままでは日本の社会経済システムが維持できなくなる」という強い危機感があります。地方で人口が減少し、経済が縮小すれば、国全体の活力が失われてしまいます。そのため、地方が自らの力で「しごと」を生み出し、それが「ひと」を呼び込み、さらに「まち」が活性化するという好循環を創り出すことが、地方創生の究極的な目標です。
具体的には、以下のような状態を目指しています。
- 経済の自律性: 地域内の資源や人材を活用し、外部からの支援に過度に依存しない安定した経済基盤を確立する。
- 社会の持続可能性: 若者が地元で働き、結婚・子育てができる環境を整え、将来にわたってコミュニティが維持される。
- 暮らしの質の向上: 都市部とは異なる、地域ならではの豊かな自然や文化を享受できる、質の高い生活環境を実現する。
これらの目的を達成するために、国、地方公共団体、企業、そして国民一人ひとりが連携し、それぞれの立場で役割を果たすことが求められています。
地方創生の歴史と「まち・ひと・しごと創生法」
地方創生の概念が本格的に国の政策として位置づけられたのは、2014年のことです。この年、「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、同時に「まち・ひと・しごと創生本部」が内閣に設置されました。
この法律が制定された背景には、長年にわたる日本の構造問題があります。高度経済成長期以降、仕事や教育の機会を求めて多くの若者が地方から東京をはじめとする大都市圏へ流出しました。この「東京一極集中」は、地方の過疎化と高齢化を加速させ、地域経済の疲弊や社会インフラの維持困難といった問題を引き起こしました。
これまでも「ふるさと創生事業」や「地域再生計画」など、様々な地域振興策が実施されてきましたが、人口減少という大きな潮流を食い止めるには至りませんでした。そこで、より強力かつ総合的な対策として、地方創生が国家戦略として打ち出されたのです。
「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。これは、地方創生の目標達成に向けた具体的な施策やKPI(重要業績評価指標)を定めた5カ年の計画です。
- 第1期総合戦略(2015年度~2019年度): 地方における「しごと」と「ひと」の好循環を確立することに重点が置かれました。地方への企業誘致や移住支援、若者の地元定着などが主なテーマでした。
- 第2期総合戦略(2020年度~2024年度): 第1期の成果と課題を踏まえ、より長期的な視点での取り組みが盛り込まれました。「関係人口」の創出・拡大や、Society 5.0の実現に向けたデジタル技術の活用(デジタルトランスフォーメーション、DX)、地方創生SDGsの推進などが新たな柱として加わっています。
このように、地方創生は時代の変化や社会の要請に応じて進化を続けており、一過性のキャンペーンではなく、日本の未来を形作るための継続的な取り組みとして位置づけられています。
国が掲げる4つの基本目標
国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、地方創生を実現するための具体的な方向性として、4つの基本目標が掲げられています。これらは相互に関連し合っており、総合的に推進されることが重要です。
① 地方での安定した雇用をつくる
地方の活力を維持するためには、若者が地元で働き、生活を築いていけるだけの魅力的で安定した雇用機会が不可欠です。この目標は、単に雇用者数を増やすだけでなく、所得の向上や働きがいのある仕事の創出を目指すものです。
具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 地域の中核企業の育成・誘致: 地域の経済を牽引する力のある企業を育て、また、本社機能の一部を地方に移転する企業を支援する。
- 地域資源を活用した産業振興: 農林水産物、観光資源、伝統技術など、その土地ならではの資源を活かした新しいビジネスを創出する。例えば、IT技術を活用した「スマート農業」や、地域の文化を体験できる「着地型観光」の開発などが進められています。
- 起業・創業支援: 地方での新しいチャレンジを後押しするため、創業支援拠点の整備や、資金調達、経営ノウハウの提供など、手厚いサポート体制を構築する。
② 地方への新しい人の流れをつくる
東京一極集中の流れを転換し、地方に関心を持つ人々が移住・定住したり、多様な形で地域と関わったりする「新しい人の流れ」を創出することが目標です。コロナ禍を契機にテレワークが普及したことで、この流れは加速する可能性を秘めています。
具体的な取り組みは以下の通りです。
- 移住・定住の促進: 移住者向けの支援金(移住支援金)や住宅支援、仕事探しのサポートなどをパッケージで提供し、移住のハードルを下げる。
- 関係人口の創出・拡大: 「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことです。副業やボランティア、ふるさと納税などを通じて地域と継続的に関わる人々を増やし、地域の担い手を確保します。
- 地方大学の振興: 地域の若者が地元大学に進学し、卒業後も地元に定着する流れを強化する。大学が地域の知の拠点として、産業振興や課題解決に貢献することも期待されています。
③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
人口減少の根本的な要因である少子化に歯止めをかけるため、若い世代が安心して結婚し、子どもを産み育てられる社会環境を整備することが急務です。経済的な不安や子育ての負担感を軽減し、「子どもを持ちたい」という希望を実現できる地域づくりを目指します。
具体的な取り組みには、次のようなものがあります。
- 経済的支援の強化: 結婚に伴う新生活支援や、不妊治療への助成、出産・子育てにかかる費用の負担軽減策など。
- 子育てサービスの充実: 待機児童の解消に向けた保育所の整備、地域子育て支援拠点の拡充、病児保育サービスの提供など、仕事と子育てを両立しやすい環境をつくる。
- 働き方改革の推進: 長時間労働の是正や男性の育児休業取得促進など、男女が共に子育てに参画できる職場環境づくりを企業に働きかける。
④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
人口が減少していく中でも、人々が安全・安心に暮らし続けられるよう、地域社会の仕組みを再構築することが目標です。コンパクトでネットワーク化された地域構造への転換や、デジタル技術の活用が鍵となります。
具体的な取り組みは以下の通りです。
- コンパクト・プラス・ネットワークの推進: 居住エリアや都市機能(医療、福祉、商業施設など)を一定の範囲に集約させ(コンパクト化)、それらの拠点を公共交通や情報通信網で結ぶ(ネットワーク化)ことで、効率的で持続可能なまちづくりを進める。
- 地域インフラの維持・更新: 老朽化が進む道路や水道、公共施設などを計画的に維持・更新し、災害に強い地域をつくる。
- 地域コミュニティの活性化: 小さな拠点(道の駅など)の整備や、NPO、地域住民が主体となった活動を支援し、地域課題を共同で解決していく仕組みを育む。
地方創生を進めるための2つの基本視点
第2期総合戦略では、上記の4つの基本目標を効果的に推進するために、新たに2つの横断的な視点が示されました。
一つは「横展開」の視点です。これは、ある地域で成功した優良事例やノウハウを、他の地域でも応用・展開していくことを指します。地方創生ポータルサイトなどを通じて情報共有を促進し、日本全体の底上げを図ります。
もう一つは「縦展開」の視点です。これは、企業やNPO、大学、関係人口といった多様な主体が、それぞれの専門性やリソースを活かして地方創生の取り組みに参画し、官民連携を深化させていくことを意味します。
これら4つの基本目標と2つの基本視点が、現在の地方創生政策の根幹をなしています。これらを理解することが、地方創生という大きなテーマを捉える第一歩となるでしょう。
なぜ地方創生が重要視されるのか?日本の現状と課題
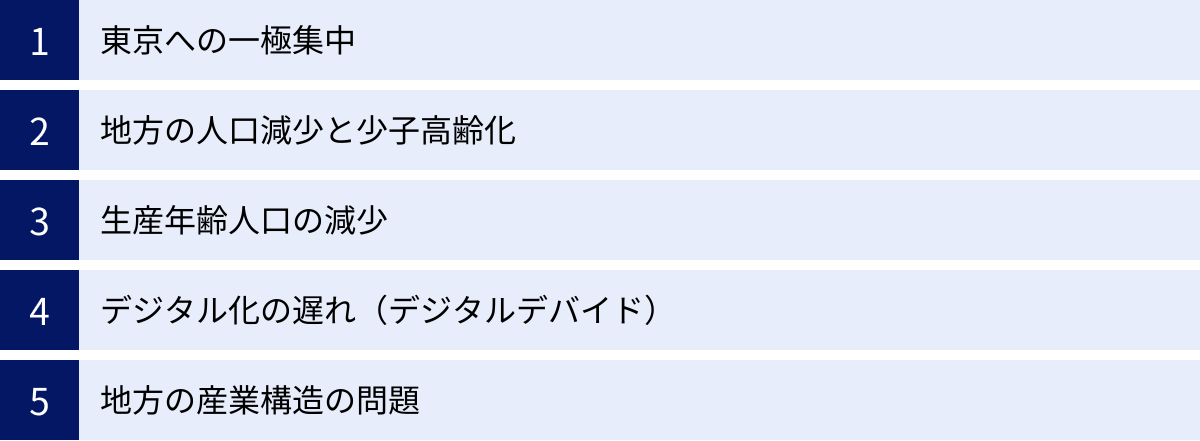
国を挙げて地方創生に取り組む背景には、日本が直面している深刻で待ったなしの課題があります。東京への一極集中、地方の人口減少、そしてそれに伴う様々な問題が、国の持続可能性そのものを脅かしているのです。ここでは、地方創生がなぜこれほどまでに重要視されるのか、その根拠となる日本の現状と課題を詳しく見ていきます。
東京への一極集中
日本の最大の問題の一つが、政治、経済、文化などあらゆる機能が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に過度に集中している「東京一極集中」です。
総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、長年にわたり東京圏は転入超過(転入者数が転出者数を上回る状態)が続いています。特に、進学や就職を機に地方から若者が流出する傾向が顕著です。企業の本社機能も東京に集中しており、全国の上場企業のうち約半数が東京に本社を置いています。
この一極集中は、様々な弊害をもたらします。
- 災害リスクの増大: 首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった大規模災害が発生した場合、日本の政治・経済の中枢機能が麻痺し、国全体に甚大な被害が及ぶリスクがあります。
- 地方の衰退: 若者や企業が流出することで、地方は働き手を失い、税収が減少し、経済が停滞します。これにより、行政サービスの低下やインフラの維持困難といった問題が深刻化し、さらなる人口流出を招くという悪循環に陥ります。
- 都市部の課題: 東京圏では、満員電車などの交通混雑、住宅価格の高騰、待機児童問題など、過密による生活の質の低下が問題となっています。
- イノベーションの停滞: 多様な価値観や文化が育まれるはずの地方が衰退することで、国全体の創造性や活力が失われる懸念もあります。
地方創生は、この一極集中の流れを是正し、多極分散型の国づくりを目指すことで、国全体のリスクを分散させ、持続可能な発展を可能にするための重要な戦略なのです。
地方の人口減少と少子高齢化
東京一極集中の裏側で、地方では深刻な人口減少と少子高齢化が進行しています。日本の総人口は2008年をピークに減少に転じており、この傾向は今後さらに加速すると予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)
特に地方部では、若者の流出(社会減)と、出生数の減少・死亡数の増加(自然減)が同時に進行しており、人口減少のペースが全国平均を上回っています。それに伴い、高齢化も急速に進んでいます。高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は全国平均でも高い水準にありますが、多くの地方自治体ではすでに30%、40%を超えており、「限界集落」と呼ばれるコミュニティの維持が困難な地域も増えています。
このような人口構造の変化は、地域社会に深刻な影響を及ぼします。
- 社会保障制度の逼迫: 年金や医療、介護といった社会保障制度は、現役世代が納める保険料で高齢者を支える仕組みです。支える側(現役世代)が減り、支えられる側(高齢者)が増えることで、制度の維持が困難になります。
- インフラ・行政サービスの維持コスト増: 人口が減少しても、道路や水道、学校、病院といった社会インフラや行政サービスを維持するためには一定のコストがかかります。住民一人当たりの負担が増大し、サービスの縮小や廃止を余儀なくされるケースも出てきます。
- 地域コミュニティの担い手不足: 地域の祭りや伝統行事の継承、消防団や自治会活動といった、地域を支える活動の担い手が不足し、コミュニティ機能が低下・消滅する恐れがあります。
地方創生は、こうした人口減少・少子高齢化の進行に歯止めをかけ、人口が減っても豊かに暮らせる社会の仕組みを再構築することを目指しています。
生産年齢人口の減少
人口減少の中でも特に深刻なのが、経済活動の中心的な担い手である「生産年齢人口(15歳~64歳の人口)」の減少です。日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後も急激な減少が見込まれています。
生産年齢人口の減少は、日本経済全体に大きな打撃を与えます。
- 労働力不足: 様々な産業で人手不足が深刻化し、事業の継続が困難になる企業が増加します。特に、介護、建設、運輸といったエッセンシャルな分野での人手不足は、国民生活に直接的な影響を及ぼします。
- 内需の縮小: 働き手が減り、所得が伸び悩むことで、国内の消費が低迷します。これにより、企業の売上が減少し、設備投資や賃上げが滞るというデフレスパイラルに陥るリスクが高まります。
- 経済成長の鈍化: 労働力という生産要素が減少するため、国全体の経済成長率が低下します。技術革新による生産性向上がなければ、経済規模は縮小の一途をたどることになります。
この課題に対応するため、地方創生では、地方における魅力的な雇用を創出し、若者や女性、高齢者など多様な人材が活躍できる環境を整備することで、労働参加率を高めることが重要なテーマとなっています。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、少ない人数でも高い生産性を上げられる産業構造への転換を急いでいます。
デジタル化の遅れ(デジタルデバイド)
近年、社会経済活動のあらゆる場面でデジタル化(DX)の重要性が叫ばれていますが、日本、特に地方部ではその取り組みが遅れているという課題があります。これを「デジタルデバイド(情報格差)」と呼びます。
デジタルデバイドには、いくつかの側面があります。
- インフラ格差: 都市部では高速な光回線や5G網の整備が進む一方、山間部や離島などでは依然として通信環境が不十分な地域が存在します。
- リテラシー格差: 高齢者を中心に、スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな人々が多く、デジタルサービスの恩恵を受けられない状況があります。また、中小企業においても、DXを推進できる人材が不足しています。
- 行政のデジタル化の遅れ: 行政手続きのオンライン化が遅れており、住民や企業にとって非効率なままとなっています。
このデジタル化の遅れは、地方の競争力を削ぎ、住民の利便性を損なう大きな要因です。
- 生産性の停滞: 中小企業がDXに取り組めなければ、生産性が上がらず、大都市圏の企業との格差がますます広がります。
- 行政サービスの非効率: 窓口に行かなければ手続きができない、紙ベースでのやり取りが多いといった状況は、住民にとっても行政職員にとっても負担となります。
- 新たなビジネスチャンスの喪失: テレワークやオンラインビジネス、スマート農業、遠隔医療といったデジタル技術を活用した新しいサービスの展開が困難になります。
地方創生では、デジタル田園都市国家構想を掲げ、地方のデジタルインフラを整備するとともに、住民や企業へのデジタル教育を推進し、行政サービスのDXを加速させることで、このデジタルデバイドを解消し、地方のハンディキャップを強みに変えようとしています。
地方の産業構造の問題
多くの地方経済は、公共事業や特定の製造業、あるいは一次産業に大きく依存しているという構造的な問題を抱えています。こうした産業構造は、外部環境の変化に弱いという脆弱性を持っています。
- 公共事業への依存: 財政状況の悪化により公共事業が削減されると、地域経済全体が大きな打撃を受けます。
- 特定産業への依存: 特定の企業の工場などに地域経済が依存している場合、その企業が海外移転や事業縮小を決定すると、大量の失業者を生み、地域経済が壊滅的な影響を受けるリスクがあります(いわゆる企業城下町の課題)。
- 一次産業の課題: 農業や漁業は、後継者不足や高齢化、価格の不安定さ、輸入産品との競合といった多くの課題を抱えています。
地方創生は、こうした脆弱な産業構造から脱却し、地域資源を活かした新たな成長産業を育成することで、多角的で強靭な経済基盤を構築することを目指しています。 例えば、地域の食文化と観光を組み合わせたガストロノミーツーリズムの推進や、IT企業やクリエイティブ産業の誘致、再生可能エネルギー産業の振興などが、その具体例です。
これらの課題は、それぞれが独立しているのではなく、複雑に絡み合っています。だからこそ、一つの側面からだけでなく、「まち・ひと・しごと」を一体的に捉えた総合的なアプローチである地方創生が、今の日本にとって不可欠なのです。
地方創生を推進する国の主な取り組み
国は、地方創生という大きな目標を達成するために、財政支援、税制優遇、情報提供など、多角的な支援策を展開しています。これらの制度を理解することは、自治体はもちろん、地方創生に貢献したいと考える企業にとっても非常に重要です。ここでは、国の主な取り組みについて、その仕組みや目的を詳しく解説します。
地方創生交付金の仕組み
地方創生の取り組みを財政面から強力に後押しするのが「地方創生交付金」です。これは、地方公共団体が自主的・主体的に行う地方創生の取り組みに対して、国が交付する資金です。特徴は、使い道が細かく定められた従来の補助金とは異なり、自治体が地域の特性や実情に応じて柔軟に事業を設計できる自由度の高さにあります。
地方創生交付金は、主に以下の3つの種類に分けられます。それぞれ目的や対象となる事業が異なります。
| 交付金の種類 | 主な目的 | 対象事業の例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 地方創生臨時交付金 | 緊急的な課題への対応(例:コロナ禍における物価高騰対策など) | 地域経済の活性化、生活者支援、事業者支援など | 社会経済情勢の変化に対応するため、臨時的・機動的に措置される。 |
| 地方創生推進交付金 | 先駆的・優良な取り組み(ソフト事業)の支援 | 移住促進、関係人口創出、DX推進、人材育成、新産業創出など | KPIを設定し、PDCAサイクルを回すことが求められる。官民連携が重要視される。 |
| 地方創生拠点整備交付金 | 地方創生の拠点となる施設整備(ハード事業)の支援 | サテライトオフィス、コワーキングスペース、子育て支援施設、地域産品販売施設など | ソフト事業と一体的に整備されることが必要。地域の活性化に繋がる「稼ぐ力」が求められる。 |
地方創生臨時交付金
正式名称を「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」といいます。その名の通り、元々は新型コロナウイルスの感染拡大防止や、影響を受けた地域経済・住民生活を支援するために創設されました。その後、原油価格・物価高騰への対応など、その時々の社会経済情勢に応じた目的にも活用できるよう拡充されています。
自治体は、この交付金を活用して、地域の実情に合わせた独自の支援策(例:プレミアム付商品券の発行、事業者への経営支援金、子育て世帯への給付金など)を迅速に実施できます。
地方創生推進交付金
こちらは、地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・主体的な取り組みのうち、特に先導的なもの(ソフト事業)を支援する交付金です。未来につながる持続可能な事業を創出することが目的であり、「稼ぐ地域」をつくるための起爆剤としての役割が期待されています。
対象となる事業は多岐にわたりますが、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 人材育成・確保: 地域の企業ニーズに応える専門人材の育成プログラム、U・I・Jターン希望者と地元企業のマッチング支援。
- 官民連携プラットフォームの構築: 地域の課題解決に向けて、行政、企業、NPO、大学などが連携する協議会の運営。
- DXの推進: 中小企業のDX導入支援、行政手続きのオンライン化、遠隔医療・教育システムの実証実験。
この交付金を申請する際には、具体的な成果目標(KPI)を設定し、事業の効果を客観的に測定・評価するPDCAサイクルを徹底することが求められます。
地方創生拠点整備交付金
こちらは、地方創生推進交付金が支援するソフト事業と連携して、地域再生の核となる施設(ハード)の整備を支援する交付金です。施設をただ建設するだけでなく、その施設がどのようにして地域の活性化や雇用の創出に貢献するのか、具体的な運営計画や収益計画がセットで求められます。
例えば、以下のような施設整備が対象となります。
- 都市部企業のサテライトオフィスや、移住者・起業家が利用するコワーキングスペースの整備。
- 古民家を改修した滞在型観光施設や、地域の特産品を加工・販売する6次産業化施設。
- 仕事と子育てを両立できる環境をつくるための、テレワークスペースを併設した子育て支援施設。
重要なのは、これらの交付金は自治体が主体となって活用するものですが、その事業の多くは民間企業やNPOとの連携(官民連携)を前提としている点です。企業にとっては、自社のノウハウやリソースを活かして地域の課題解決に貢献し、新たな事業機会を得るチャンスとなり得ます。
(参照:内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生)
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
企業が地方創生に直接的に関わるための非常に有効な制度が、「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」です。これは、企業が、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。
通常の寄附金は経費として算入される「損金算入」による軽減効果(寄附額の約3割)のみですが、企業版ふるさと納税では、これに加えて最大で寄附額の6割に相当する額が税額控除されます。つまり、損金算入と合わせて最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担を約1割にまで圧縮できるという、極めて大きな税制優遇措置です。
この制度のポイントは以下の通りです。
- 対象事業: 寄附の対象となるのは、自治体が策定し、国が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に限られます。
- 寄附の下限: 1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
- 注意点: 本社が所在する自治体への寄附は対象外となります。また、寄附の代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
企業にとって、この制度を活用するメリットは税制優遇だけではありません。
- 社会貢献: 応援したい地域の課題解決に直接貢献でき、CSR(企業の社会的責任)活動として高く評価されます。
- 新たな関係構築: 寄附をきっかけに自治体や地域住民との新たなパートナーシップが生まれ、新規事業の展開や人材採用につながる可能性があります。
- 企業ブランドの向上: 地方創生に積極的に取り組む企業として、社会的なイメージやブランド価値の向上が期待できます。
(参照:内閣府地方創生推進事務局 企業版ふるさと納税ポータルサイト)
地方創生テレワークの推進
コロナ禍を機に急速に普及したテレワークは、地方創生の観点からも大きな可能性を秘めています。働く場所を選ばないテレワークは、「地方に住みながら東京の仕事をする」といった新しいライフスタイルを可能にし、東京一極集中の是正に貢献します。
国は「地方創生テレワーク」を推進するため、様々な支援を行っています。
- 交付金による支援: 地方公共団体がサテライトオフィスやコワーキングスペースを整備する際に、地方創生拠点整備交付金などを活用できます。
- 情報提供・マッチング: 企業向けに地方のサテライトオフィス情報を提供するポータルサイトの運営や、地方でのテレワーク導入に関心のある企業と自治体とのマッチングイベントなどを開催しています。
- 税制優遇: 地方拠点強化税制により、企業が本社機能(オフィスなど)を地方に移転・拡充した場合に、税制上の優遇措置を受けられます。
地方創生テレワークは、移住だけでなく、都市部の企業に勤める人が休暇などを利用して地方で仕事をする「ワーケーション」の促進にもつながり、後述する「関係人口」の拡大に貢献します。
関係人口の創出・拡大
地方創生を成功させるためには、その地域の担い手を増やすことが不可欠です。しかし、いきなり移住・定住者を増やすことは容易ではありません。そこで重要になるのが「関係人口」という考え方です。
関係人口とは、「定住人口」でも「交流人口(観光客)」でもない、その地域と多様かつ継続的に関わる人々を指します。例えば、以下のような人々が関係人口に含まれます。
- 出身地や親族の居住地など、その地域にルーツがある人
- 過去に仕事や居住で関わりがあった人
- ふるさと納税で特定の自治体を継続的に応援している人
- 副業やプロボノ(専門知識を活かしたボランティア)で地域のプロジェクトに参加している人
- ワーケーションで定期的に訪れる人
国は、この関係人口を「地域づくりの裾野を広げる重要な存在」と位置づけ、その創出・拡大を支援しています。関係人口が増えることで、地域には経済的な効果だけでなく、外部の新しい視点やスキルがもたらされ、地域活性化の新たな原動力となることが期待されています。
地方創生SDGsの推進
SDGs(持続可能な開発目標)は、地方創生の目指す方向性と多くの点で合致しています。 例えば、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」は地方創生の理念そのものであり、目標8「働きがいも経済成長も」は地方での雇用創出に、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」は地方産業のDX推進にそれぞれ対応します。
国は、この親和性の高さを活かし、「地方創生SDGs」を推進しています。具体的には、SDGsの達成に向けて優れた取り組みを行う自治体を「SDGs未来都市」として選定し、その取り組みを支援しています。また、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を設立し、SDGsに取り組む企業やNPO、大学などが自治体と連携できる場を提供しています。
SDGsという世界共通の目標を羅針盤とすることで、地方創生の取り組みがより普遍的な価値を持ち、国内外からの共感や投資を呼び込みやすくなるというメリットがあります。
これらの国の取り組みは、地方創生という壮大なプロジェクトを動かすための重要なエンジンです。企業はこれらの制度を賢く活用することで、社会貢献と自社の成長を両立させることが可能になります。
企業が地方創生に取り組む4つのメリット
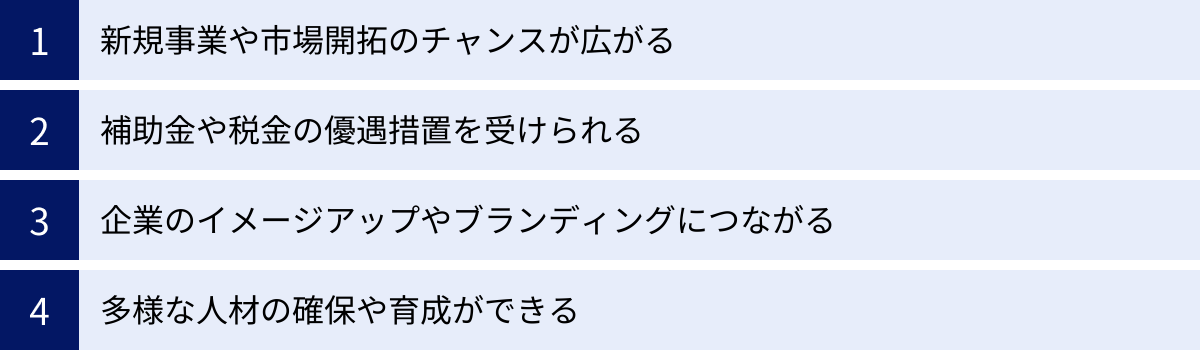
地方創生は、社会的な課題解決への貢献という側面だけでなく、企業にとって多くのビジネスチャンスや成長機会をもたらす可能性を秘めています。コストや手間がかかるというイメージを抱くかもしれませんが、戦略的に取り組むことで、事業の持続的な発展に繋がる大きなメリットを得られます。ここでは、企業が地方創生に取り組む主な4つのメリットを解説します。
① 新規事業や市場開拓のチャンスが広がる
地方には、都市部とは異なる独自の課題や、まだ満たされていない潜在的なニーズが数多く存在します。これらは、見方を変えれば、新たなビジネスのシーズ(種)の宝庫です。企業が自社の持つ技術、ノウハウ、アイデアを地方の課題解決に結びつけることで、これまでにない新規事業や市場を開拓できる可能性があります。
具体的には、以下のようなチャンスが考えられます。
- 高齢化社会対応ビジネス: 高齢化が特に進んでいる地方では、見守りサービス、配食サービス、移動支援(デマンド交通など)、遠隔医療サポートといった、高齢者の生活を支えるビジネスへの需要が高まっています。
- 一次産業のDX化: 担い手不足や生産性の低さに悩む農業・林業・水産業の現場に、IT企業がドローンやセンサー技術、AIによるデータ分析などを導入し、「スマート農業(漁業)」を支援するビジネス。これは生産性向上だけでなく、新たな付加価値の創出にも繋がります。
- 空き家・遊休資産の活用: 地方で増加する空き家や廃校を、企業のサテライトオフィス、研修施設、体験型宿泊施設、クリエイターの創作拠点などとして再生・活用するビジネス。地域資源を有効活用し、新たな交流を生み出します。
- 再生可能エネルギー事業: 豊富な自然環境を活かし、太陽光、風力、小水力、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電事業を展開する。これはエネルギーの地産地消に貢献し、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価向上にも繋がります。
地方の課題を「解決すべきコスト」ではなく「事業機会」として捉える視点を持つことが、地方創生をビジネスチャンスに変える鍵となります。
② 補助金や税金の優遇措置を受けられる
国や地方自治体は、企業が地方創生に取り組むことを強力に後押しするため、様々なインセンティブを用意しています。これらを活用することで、新規事業の立ち上げや拠点設置にかかる初期投資やリスクを大幅に軽減できます。
代表的な制度としては、前章で解説したものが挙げられます。
- 地方創生関連の交付金・補助金: 自治体が国から受けた地方創生推進交付金などを財源として、地域課題解決に貢献する民間企業の事業に対して補助金を出すケースが数多くあります。例えば、サテライトオフィス開設費用の補助、DX導入支援補助、新商品開発補助など、内容は多岐にわたります。
- 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制): 自治体の地方創生プロジェクトに寄附をすることで、最大で寄附額の約9割に相当する税の軽減効果を受けられます。直接的な事業投資とは異なりますが、地域との強固な関係性を築くきっかけとなり、間接的にビジネスチャンスに繋がることが期待できます。
- 地方拠点強化税制: 東京23区にある本社機能を地方に移転したり、地方の拠点を拡充したりする場合に、設備投資への税額控除や雇用促進に関する税制優遇を受けられます。
これらの制度を活用するには、自社の事業計画と各制度の趣旨や要件を合致させる必要があります。自治体の担当窓口や専門家と相談しながら、戦略的に制度活用を検討することが重要です。単なるコスト削減策としてではなく、事業戦略の一環としてこれらの優遇措置を捉えることで、地方創生への取り組みを加速させることができます。
③ 企業のイメージアップやブランディングにつながる
現代の消費者は、単に製品やサービスの品質・価格だけでなく、それを提供する企業の姿勢や社会への貢献度を重視する傾向が強まっています。また、投資家も、短期的な利益だけでなく、長期的な持続可能性を示すESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを投資判断の重要な基準としています。
地方創生への取り組みは、こうした社会の要請に応える絶好の機会であり、企業の社会的評価やブランドイメージを大きく向上させる効果が期待できます。
- CSR(企業の社会的責任)活動としてのアピール: 地域の雇用創出や環境保全、文化継承などに貢献する活動は、企業のウェブサイトや統合報告書、メディアなどを通じて発信することで、企業の社会的責任を果たしている姿勢を内外に示すことができます。
- ESG評価の向上: 地方創生は、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)のすべての側面に関わります。例えば、再生可能エネルギー事業は「E」、多様な人材の雇用や地域コミュニティへの貢献は「S」、自治体との公正なパートナーシップは「G」に該当します。ESG評価が高まることで、金融機関からの融資が有利になったり、ESGファンドからの投資を呼び込んだりしやすくなります。
- 採用ブランディングへの貢献: 特に若い世代は、企業の社会貢献意識を重視する傾向があります。「地域を元気にする仕事ができる」「社会の役に立っている実感を得られる」といったメッセージは、優秀で意欲の高い人材を惹きつける強力な魅力となります。
物語性のある取り組みは、消費者の共感を呼び、製品やサービスへのロイヤルティを高める効果もあります。「あの会社は、〇〇(地域名)の活性化に貢献している」というポジティブな評判は、広告費では得られない強力な無形資産となります。
④ 多様な人材の確保や育成ができる
東京一極集中が進む一方で、地方での暮らしや働き方を希望するUターン・Iターン・Jターン人材も確実に存在します。また、テレワークの普及により、居住地にとらわれずに能力を発揮したいと考える人も増えています。企業が地方に拠点を設けたり、リモートワークを積極的に導入したりすることは、こうした多様な人材を獲得するための有効な戦略となります。
- 優秀な地方人材の獲得: 地方には、都市部でのキャリアを経験した後に地元に戻ってきたUターン人材や、豊かな自然環境での子育てなどを求めて移住してきたIターン人材など、高いスキルと意欲を持つ人材が埋もれている可能性があります。地方に拠点を構えることで、こうした人材の受け皿となることができます。
- 従業員のエンゲージメント向上: 従業員に対して、テレワークやワーケーション、地方拠点での勤務といった多様な働き方の選択肢を提供することは、ワークライフバランスの向上に繋がり、従業員の満足度やエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めます。これは、離職率の低下や生産性の向上にも貢献します。
- 人材育成の機会: 都市部とは異なる環境、異なる価値観を持つ地域の人々との協働は、従業員にとって新たな視点やスキルを学ぶ絶好の機会となります。課題解決能力やコミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力など、座学では得られない実践的な能力を養うことができます。
地方創生への取り組みは、単なる社会貢献活動ではなく、企業の根幹をなす「人」という経営資源を強化するための戦略的な投資と捉えることができます。多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、組織のダイバーシティ&インクルージョンが促進され、イノベーションが生まれやすい企業風土の醸成にも繋がっていくでしょう。
企業ができる地方創生の取り組みアイデア
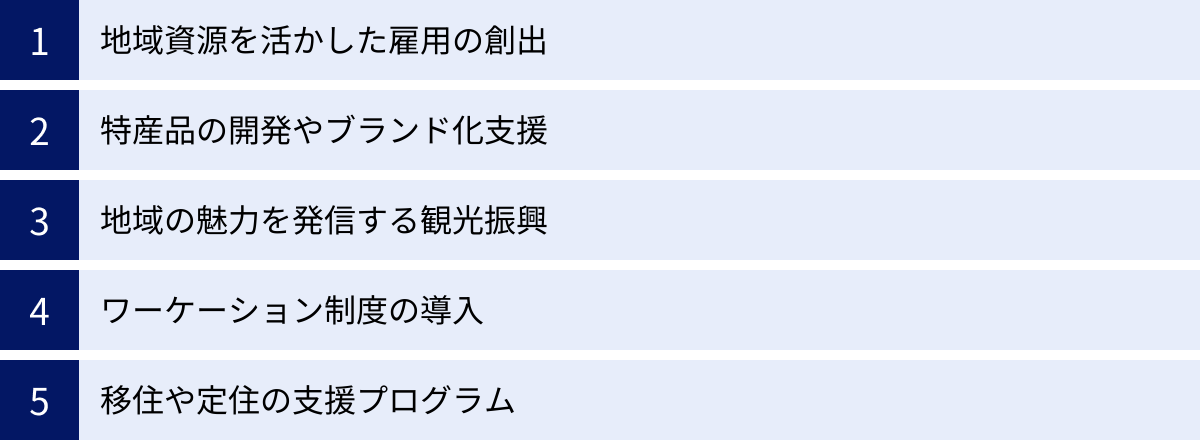
地方創生に貢献したいと考えても、「具体的に何をすれば良いのか分からない」という企業は多いかもしれません。大切なのは、自社の強み(技術、ノウハウ、人材、ネットワークなど)と、地域のニーズや課題をうまく結びつけることです。ここでは、企業が実践できる地方創生の具体的な取り組みアイデアを、いくつかの切り口から紹介します。
地域資源を活かした雇用の創出
その地域にしかない「宝物」を活かして新しい仕事を生み出すことは、地方創生の王道ともいえるアプローチです。企業の持つ企画力や技術力、マーケティング力を掛け合わせることで、地域資源は大きな価値を持つビジネスへと生まれ変わります。
- 農林水産物の6次産業化支援: 地域の農家や漁師と連携し、生産(1次)だけでなく、加工(2次)、販売・サービス(3次)までを一貫して行う「6次産業化」を支援します。例えば、規格外の果物を使ったジャムやジュースの商品化、地元の魚介類を使ったレストランの開業、IT企業がECサイトの構築やオンラインでのブランディングを支援する、といった形が考えられます。これにより、農林水産業の付加価値を高め、生産者の所得向上と新たな雇用創出に繋がります。
- 伝統工芸や文化の新たな活用: 後継者不足に悩む伝統工芸の技術を、現代のライフスタイルに合った商品開発に活かします。例えば、アパレル企業が地域の織物を使って新しいデザインの服や小物を開発したり、IT企業がVR/AR技術を使って伝統文化の体験コンテンツを制作したりすることが考えられます。
- 自然環境を活かしたヘルスケア・ウェルネス事業: 豊かな森林資源を活かした森林セラピープログラムの開発や、美しい景観を望む場所にヨガやリトリート施設を開設するなど、心身の健康をテーマにした事業は、都市部からの来訪者を呼び込みます。
特産品の開発やブランド化支援
地方には素晴らしい特産品がありながら、デザインやマーケティングのノウハウ不足から、その魅力が十分に伝わっていないケースが少なくありません。企業の専門知識を活かして、その価値を最大限に引き出す支援は非常に喜ばれます。
- 商品企画・デザインの刷新: 食品メーカーやデザイン会社が、地域の特産品のパッケージデザインやネーミングをリニューアルし、購買意欲を高める支援を行います。ターゲット顧客を明確にし、その心に響くストーリーを添えることで、商品の価値は大きく変わります。
- 販路開拓のサポート: 企業の持つ販売チャネルやネットワークを活かし、都市部の百貨店やセレクトショップ、自社のECサイトなどで特産品を販売します。また、海外展開を目指す地域に対しては、商社が輸出ノウハウを提供したり、翻訳会社が多言語対応を支援したりすることも有効です。
- デジタルマーケティング支援: IT企業や広告代理店が、SNS(Instagram, Facebookなど)や動画プラットフォーム(YouTubeなど)を活用した効果的なプロモーション戦略を立案・実行します。インフルエンサーを起用したPRや、ターゲットを絞ったWeb広告の運用など、デジタルならではの手法で認知度を一気に高めることが可能です。
地域の魅力を発信する観光振興
観光は、地域に直接的な経済効果をもたらす重要な産業です。従来の団体旅行や名所旧跡を巡る観光だけでなく、その地域ならではの体験ができる「コト消費」へのニーズが高まっています。
- 体験型観光プログラムの開発: 旅行会社やイベント会社が、地域住民と協力してユニークな体験プログラムを企画します。例えば、農家での収穫体験と料理教室、漁師の船に乗る漁業体験、職人と一緒に作る伝統工芸体験など、参加者の記憶に残るコンテンツが人気を集めます。自社の研修プログラムと組み合わせることも有効です。
- インバウンド観光客の誘致: 特に海外からの観光客は、日本の地方文化に強い関心を持っています。外国語対応ができる人材の育成支援や、多言語での観光案内サイトの制作、海外の旅行代理店への営業代行などが考えられます。
- デジタル技術を活用した魅力発信: 地域の美しい風景や文化を高品質なドローン映像で撮影し、プロモーションビデオを制作したり、VRコンテンツで観光地の魅力を疑似体験できるようにしたりするなど、テクノロジーを使って地域の魅力を世界に発信します。
ワーケーション制度の導入
「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせたワーケーションは、企業が比較的導入しやすく、地方創生への貢献度も高い取り組みです。
- 福利厚生として制度化: 社員が休暇や出張の前後などに、リゾート地や地方のサテライトオフィスで働くことを認める制度を導入します。これにより、社員はリフレッシュしながら効率的に働くことができ、生産性の向上が期待できます。
- 地域との連携: 自治体や現地の観光協会と連携し、ワーケーション滞在者向けの宿泊プランや体験プログラムを用意します。社員が滞在中に地域の人々と交流する機会を設けることで、新たなアイデアやビジネスチャンスが生まれることもあります。
- 地域経済への貢献: ワーケーションで社員が地域に滞在すれば、宿泊費や食費、交通費、お土産代などの消費が生まれます。多くの社員が利用すれば、その経済効果は決して小さくありません。また、ワーケーションをきっかけにその地域を気に入り、関係人口や移住に繋がるケースも期待できます。
移住や定住の支援プログラム
より本格的に地方創生に関わる方法として、企業が社員の移住・定住を支援するプログラムがあります。
- サテライトオフィスの設置: 地方に小規模なオフィスを設置し、社員が本社と同じように働ける環境を整備します。これは、Uターン・Iターン希望の社員の受け皿になるだけでなく、現地の優秀な人材を採用する拠点にもなります。
- 移住支援制度の創設: 地方拠点への異動や、テレワークでの地方移住を希望する社員に対して、引越し費用や住居探しのサポート、移住準備金などの経済的支援を行います。自治体の移住支援金と組み合わせることも可能です。
- 地域での起業・独立支援: 地方での事業展開で得たノウハウを活かし、社員がその地域で独立・起業(スピンアウト)することを支援する制度。地域に新たな事業主を生み出すことで、より直接的な雇用創出に貢献できます。
これらのアイデアはほんの一例です。重要なのは、自社の事業ドメインや経営理念と親和性の高い領域で、無理なく継続できる取り組みから始めることです。地域との対話を重ね、共に成長していくパートナーシップを築くことが、企業による地方創生を成功に導くでしょう。
地方創生とSDGsの深いつながり
「地方創生」と「SDGs(持続可能な開発目標)」は、一見すると別のテーマのように思えるかもしれませんが、実はその根底で深く結びついています。SDGsは2015年に国連で採択された、2030年までに達成すべき17の国際目標ですが、その理念は「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現です。これは、日本の各地域がそれぞれの個性を活かし、自律的で持続可能な社会を目指す地方創生の理念と完全に一致します。
地方創生の取り組みは、SDGsの多くの目標達成に直接的に貢献します。逆に、SDGsの視点を取り入れることで、地方創生の取り組みはより深化し、グローバルな文脈での価値を持つようになります。
| 地方創生の取り組み例 | 関連するSDGsの目標 |
|---|---|
| 地域資源を活かした雇用創出、起業支援 | 目標8: 働きがいも経済成長も ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の促進、持続可能な経済成長に貢献。 |
| スマート農業、再生可能エネルギー事業 | 目標7: エネルギーをみんなにそしてクリーンに 目標9: 産業と技術革新の基盤をつくろう 目標13: 気候変動に具体的な対策を クリーンエネルギーの普及、持続可能な産業化、気候変動への対応に貢献。 |
| コンパクトシティの推進、空き家活用 | 目標11: 住み続けられるまちづくりを 安全で強靭、持続可能な都市と人間居住を実現する取り組みそのもの。 |
| 子育て支援の充実、女性の活躍推進 | 目標5: ジェンダー平等を実現しよう すべての女性と女児のエンパワーメントを図り、子育てしやすい社会を実現。 |
| 関係人口の創出、官民連携プラットフォーム | 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう 国、自治体、企業、市民社会など、多様な主体が連携して目標達成を目指す。 |
| 森林保全、豊かな自然を活かした観光 | 目標15: 陸の豊かさも守ろう 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用を推進。 |
このように、地方創生における具体的なアクションの多くは、SDGsの複数の目標にまたがって貢献することがわかります。例えば、地方の森林資源を活用してバイオマス発電事業を行う企業は、雇用の創出(目標8)、クリーンエネルギーの供給(目標7)、産業基盤の構築(目標9)、気候変動対策(目標13)、森林保全(目標15)といった、非常に多くの目標達成に貢献していることになります。
企業が地方創生に取り組む際にSDGsの視点を持つことには、大きなメリットがあります。
- 事業の意義の明確化: 自社の取り組みが、地域課題の解決だけでなく、地球規模の課題解決にどう繋がっているのかを明確にできます。これは、社員のモチベーション向上や、社外への説得力ある情報発信に繋がります。
- 新たなパートナーシップの創出: SDGsという世界共通言語を使うことで、同じ志を持つ国内外の企業、NPO、投資家などとの連携が生まれやすくなります。
- 資金調達の有利化: 近年、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)やサステナビリティ・リンク・ローン(SDGs達成度に応じて金利などが変動する融資)など、SDGsへの貢献度を評価する金融の流れが世界的に加速しています。SDGsを経営に統合することは、資金調達の面でも有利に働きます。
内閣府も「地方創生SDGs」を推進しており、自治体と企業、金融機関、NPOなどが連携するための「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を運営しています。
地方創生は、日本という国の中でのローカルな課題解決であると同時に、SDGsというグローバルな目標を達成するための具体的な実践の場でもあります。この二つを統合して考えることで、企業の活動はより大きな価値と持続可能性を持つことになるでしょう。
私たち個人にもできる地方創生への貢献
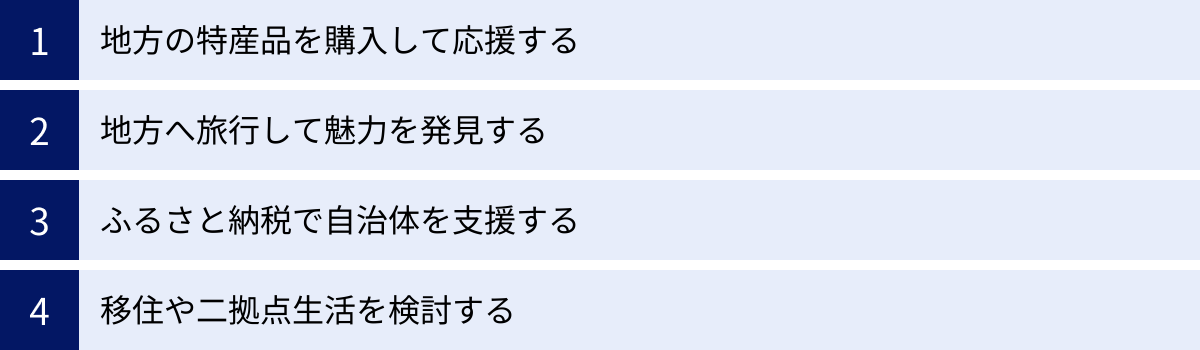
地方創生は、国や自治体、企業だけの課題ではありません。私たち一人ひとりの意識や行動が、地域の未来を支える大きな力となります。日常生活の中で少し意識を変えるだけで、楽しみながら地方を応援し、その活性化に貢献することができます。ここでは、個人でできる地方創生への貢献アイデアを紹介します。
地方の特産品を購入して応援する
最も手軽で直接的な応援方法が、地方で作られた産品を積極的に購入することです。スーパーで野菜を買うときに産地を意識してみる、インターネットの産直サイトで旬の果物を取り寄せる、都市部にあるアンテナショップを訪れてみるなど、方法は様々です。
私たちが支払ったお金は、生産者である農家や漁師、職人さんの収入に直接繋がり、彼らの生活を支え、事業を継続する力になります。それは、地域の伝統的な食文化や技術を守ることにも繋がります。また、購入した商品の美味しさや素晴らしさをSNSなどで発信すれば、それが新たなPRとなり、応援の輪が広がっていくかもしれません。一杯のジュース、一枚の皿が、地域の経済を潤し、作り手の誇りを育む一票となるのです。
地方へ旅行して魅力を発見する
旅行は、地方創生に貢献できる素晴らしい機会です。観光地を訪れ、宿泊し、食事をし、お土産を買うといった一連の消費活動は、地域の観光産業や関連産業(飲食、小売、交通など)を直接支え、多くの雇用を維持します。
ただ訪れるだけでなく、その土地の歴史や文化を学んだり、地元の人々と交流したりすることで、地域の本当の魅力を発見できます。ガイドブックに載っていないような素敵なカフェや、地元の人しか知らない絶景スポットを見つけるのも旅の醍醐味です。そうして見つけた魅力を、友人や家族に伝えたり、SNSで共有したりすることで、あなた自身がその地域の「広報大使」になることができます。一人の観光客から、地域と継続的に関わる「関係人口」への第一歩となるかもしれません。
ふるさと納税で自治体を支援する
「ふるさと納税」は、応援したい自治体を選んで寄附ができる制度です。寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除されるため、実質的な自己負担は2,000円で済みます。多くの人にとって魅力的な返礼品が注目されがちですが、その本質は「税金の使い道を指定し、地域を応援する」という点にあります。
寄附金がどのように使われるかは、自治体のウェブサイトなどで確認できます。「子育て支援の充実に使ってほしい」「美しい景観を守るために使ってほしい」「伝統文化の継承に役立ててほしい」など、自分が共感するプロジェクトを選んで寄附することができます。自分の納めた税金が、具体的な形で地域の未来のために役立てられることを実感できる、非常に意義のある制度です。
移住や二拠点生活を検討する
究極の地方創生への貢献は、その地域の一員となる「移住」です。しかし、いきなり移住するのはハードルが高いと感じる人も多いでしょう。そこで、まずは都市と地方に生活拠点を持つ「二拠点生活(デュアルライフ)」や、長期休暇を利用した「お試し移住」から始めてみるのがおすすめです。
テレワークの普及により、会社に通勤する日が減った人なら、平日の数日や週末を地方で過ごすライフスタイルも現実的になってきました。自治体によっては、お試し移住者向けに短期間滞在できる住宅や、家賃補助制度を用意しているところもあります。
地域に滞在する時間が増えれば、地域コミュニティへの参加や、副業・兼業での地域貢献など、より深い関わり方が可能になります。自分自身のライフスタイルを豊かにしながら、地域の担い手として貢献できる、新しい生き方の選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。これらの行動は、決して特別なことではありません。日々の暮らしの中での小さな選択の積み重ねが、日本の地方を元気にし、国全体の持続可能な未来を築くための大切な一歩となるのです。
まとめ
本記事では、「地方創生」という壮大なテーマについて、その定義や背景にある日本の課題、国や企業、そして個人の取り組みまで、多角的に掘り下げてきました。
地方創生とは、単なる過疎地対策ではなく、人口減少という日本全体の大きな課題に立ち向かい、それぞれの地域が持つポテンシャルを最大限に引き出すことで、国の持続可能性を確保するための国家戦略です。東京一極集中の是正、少子高齢化への対応、新たな産業の創出といった目標は、日本の未来そのものを左右する重要なテーマといえます。
国は、地方創生交付金や企業版ふるさと納税といった強力な支援策を用意し、自治体や企業の挑戦を後押ししています。企業にとっては、これらの制度を活用することで、地方の課題を新たなビジネスチャンスに変え、新規市場の開拓、ブランドイメージの向上、多様な人材の確保といった多くのメリットを享受できます。地域資源を活かした新事業、特産品のブランド化支援、ワーケーションの導入など、企業が貢献できる方法は多岐にわたります。
また、地方創生は、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現と深く結びついています。地方創生への取り組みは、ローカルな課題解決であると同時に、グローバルな目標達成への貢献でもあるのです。
そして、この大きな流れは、私たち一人ひとりの行動と無関係ではありません。地方の産品を購入すること、地域を旅してその魅力を発見・発信すること、ふるさと納税で応援すること。こうした一つひとつの小さなアクションが結集し、地域を支える大きな力となります。
人口減少という厳しい現実は、変えることのできない未来かもしれません。しかし、人口が減っても、そこに住む人々が豊かさと誇りを持って暮らし続けられる社会を創ることは可能です。地方創生は、そのための未来への投資に他なりません。この記事が、あなたやあなたの企業が、地方創生という可能性に満ちたフィールドへ一歩踏み出すきっかけとなれば幸いです。