近年、ビジネスや観光、地域振興の文脈で「MICE(マイス)」という言葉を耳にする機会が増えています。MICEは、単なる会議や展示会を越え、開催地域に大きな経済効果や新たなビジネスチャンスをもたらす可能性を秘めた、極めて戦略的な活動として世界中から注目を集めています。
しかし、その具体的な意味や構成要素、もたらされるメリットについては、まだ十分に理解されていないかもしれません。この記事では、MICEという言葉の基本的な定義から、それを構成する4つの要素、開催・誘致によって得られる多角的なメリット、そして日本のMICEが置かれている現状と今後の展望まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。
MICEの全体像を掴むことで、ビジネスパーソンにとっては新たな市場開拓のヒントに、行政や地域関係者にとっては地域活性化の有効な手段として、そしてMICE業界に関心を持つ方にとっては、そのダイナミックな世界の理解を深める一助となるでしょう。
目次
MICEとは

MICE(マイス)とは、多くの人々が集まるビジネスイベントや国際会議などの総称です。これは、4つの単語の頭文字を組み合わせた造語であり、それぞれがMICEを構成する重要な要素を示しています。具体的には、Meeting(会議・研修)、Incentive(招待・報奨旅行)、Convention(国際会議・学術会議)、Exhibition / Event(展示会・見本市)の4つを指します。
これらの活動は、単独で開催されることもあれば、複数が組み合わさって大規模なイベントとして実施されることもあります。MICEの最大の特徴は、企業や学術団体、政府機関など、様々な組織が主催者となり、国内外から多くの参加者が特定の目的を持って一箇所に集まる点にあります。
一般的な観光旅行とは異なり、MICEの参加者はビジネスや学術研究などの明確な目的を持っているため、滞在期間が比較的長く、一人あたりの消費額が高い傾向にあります。このため、開催地の経済に与える影響が非常に大きいとされています。さらに、人々の交流を通じて新たな知識や技術が共有され、イノベーションが生まれる土壌となるなど、経済的な側面以外にも計り知れない価値を創出します。
このように、MICEは単なるイベントの集合体ではなく、経済、ビジネス、科学技術、文化交流、都市開発など、多岐にわたる分野に好影響を及ぼす、戦略的な産業として位置づけられています。世界各国の都市がMICEの誘致に力を入れているのは、こうした多面的なメリットを享受できるためです。
MICEを構成する4つの要素
MICEをより深く理解するためには、その根幹をなす4つの要素、Meeting、Incentive、Convention、Exhibition / Eventについて、それぞれの特徴と目的を正確に把握することが不可欠です。以下で、各要素を詳しく見ていきましょう。
① Meeting(会議・研修)
Meetingは、MICEの「M」にあたり、主に企業や団体が主催する会議、セミナー、研修などを指します。その目的は多岐にわたり、情報共有、意思決定、問題解決、社員教育、組織内のコミュニケーション活性化などが挙げられます。
- 具体例:
- 企業の年度初めに行われるキックオフミーティングや経営戦略会議
- 新製品や新サービスの発表会、プレス向けの説明会
- 特定のテーマについて議論する社内ワーキンググループやブレインストーミング
- 新入社員研修やマネジメント層向けのリーダーシップ研修
- 顧客やパートナー企業を対象とした製品トレーニングや技術セミナー
Meetingの規模は、数名程度の小規模な打ち合わせから、数千人規模の全社総会まで様々です。Convention(国際会議)と比較すると、一般的に非公開(クローズド)で行われるものが多く、参加者も特定の組織の構成員や関係者に限定される傾向があります。
開催場所も、社内の会議室からホテルの宴会場、外部のカンファレンスセンターまで、目的や規模に応じて柔軟に選ばれます。近年では、チームビルディングや創造性の向上を目的として、日常の職場とは異なる環境、例えばリゾート地やユニークな施設で行う「オフサイトミーティング」も注目されています。これは、MICEの他の要素であるIncentive(報奨旅行)の側面を併せ持つ形態と言えるでしょう。
Meetingは、組織の方向性を定め、人材を育成し、イノベーションの種を蒔くという、企業活動の根幹を支える重要なコミュニケーションの場です。
② Incentive(招待・報奨旅行)
Incentiveは、MICEの「I」にあたり、一般的に「インセンティブツアー」や「インセンティブトラベル」と呼ばれます。これは、企業が従業員や販売代理店などに対し、目標達成や優秀な業績への報奨(ご褒美)として提供する旅行のことです。
単なる慰安旅行とは一線を画し、その最大の目的は参加者のモチベーション向上と、企業へのロイヤルティ(忠誠心)を高めることにあります。旅行という非日常的で魅力的な体験を提供することで、「次も頑張ってこの旅行に参加したい」という意欲を喚起し、組織全体の生産性向上につなげることを狙いとしています。
- 具体例:
- 年間販売目標を達成した営業チームを、海外の高級リゾートホテルに招待する。
- 優れた業績を上げた社員とその家族を対象に、豪華客船でのクルーズ旅行をプレゼントする。
- 全国のトップセールス担当者を集め、特別な観光地で表彰式や祝賀パーティーを開催する。
- チームビルディングを目的としたアクティビティ(ラフティングや料理教室など)を組み込んだ旅行プログラムを実施する。
Incentive旅行の特徴は、そのプログラム内容にあります。企業のトップからのメッセージが伝えられたり、経営理念を共有するワークショップが組み込まれたりするなど、楽しみながらも企業文化の浸透や参加者同士の一体感醸成を図る工夫が凝らされています。参加者にとっては、金銭的な報酬とは異なる「特別な経験」という価値があり、強い動機付けとなります。
企業にとっては、優秀な人材の定着(リテンション)や、組織全体の士気高揚に直結する、効果的な人的資源管理(HRM)の一手法として、その重要性が認識されています。
③ Convention(国際会議・学術会議)
Conventionは、MICEの「C」にあたり、国際機関、各国の政府、学術団体、業界団体などが主催する大規模な会議を指します。一般的に「大会」や「総会」と訳されることが多いです。
Meeting(会議)との主な違いは、その公共性と国際性、そして規模にあります。Conventionは、特定の企業や組織の利益だけでなく、科学技術の発展、国際的な課題の解決、業界標準の策定といった、より公益性の高いテーマを扱うことがほとんどです。
- 具体例:
- 国際機関・政府主催: G7やG20などの主要国首脳会議(サミット)、APEC(アジア太平洋経済協力)閣僚会議、国連の気候変動枠組条約締約国会議(COP)など。
- 学術団体主催: 世界中の医師や研究者が集まる国際医学会、特定の技術分野の最新研究を発表する国際工学会、人文科学分野の国際シンポジウムなど。
- 業界団体主催: 世界の観光業界関係者が集う国際観光会議、特定の産業の動向を話し合う世界規模の業界団体総会など。
Conventionの開催地は、世界中の都市による激しい誘致合戦を経て決定されます。開催地に選ばれることは、その都市の国際的な知名度やブランドイメージを飛躍的に高めるだけでなく、世界中から集まる専門家や研究者との交流を通じて、開催地の学術・産業レベルの向上にも大きく貢献します。
参加者は数千人から、時には1万人を超える規模に達することもあり、その経済効果はMICEの4要素の中でも特に大きいとされています。Conventionは、知の集積と交流を促し、人類社会の発展に寄与する、極めて重要な国際的プラットフォームと言えるでしょう。
④ Exhibition / Event(展示会・見本市)
Exhibition / Eventは、MICEの「E」にあたり、企業や団体が自社の製品、技術、サービスなどを展示し、プロモーションや商談、情報交換を行う場を指します。日本語では「展示会」「見本市」「トレードショー」などと呼ばれます。また、より広義には、文化・芸術・スポーツなどの大規模なイベントも含まれる場合があります。
Exhibitionの主な目的は、ビジネスチャンスの創出です。出展企業は、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化、新たな販売代理店やパートナーの発掘、ブランドイメージの向上、そして競合他社や市場の最新動向の把握などを目指します。
- 具体例:
- BtoB(Business to Business)展示会:
- 最新のIT技術やソフトウェアが一堂に会する「IT Week」
- 工作機械や製造業向けの技術が集まる「JIMTOF(日本国際工作機械見本市)」
- 食品業界向けの商談会「FOODEX JAPAN(国際食品・飲料展)」
- BtoC(Business to Consumer)展示会・イベント:
- 国内外の自動車メーカーが新型車を披露する「東京モーターショー(現:JAPAN MOBILITY SHOW)」
- 最新のゲームソフトやハードが集結する「東京ゲームショウ」
- 旅行先の情報や商品をPRする「ツーリズムEXPOジャパン」
- BtoB(Business to Business)展示会:
これらの展示会には、特定のテーマに関心を持つ多数の来場者が集まるため、出展企業にとっては効率的なマーケティング活動の場となります。また、業界の最新トレンドを一度に把握できるため、来場者にとっても有益な情報収集の機会です。
Exhibitionは、新製品や新技術が世に出る「お披露目の場」としての役割も担っており、産業の活性化とイノベーションを促進する強力なエンジンとして機能しています。MICEの他の要素、例えばConventionと併催されることも多く、学術的な発表と具体的な製品・技術の展示が連携することで、より大きな相乗効果を生み出します。
MICEがもたらす4つのメリット
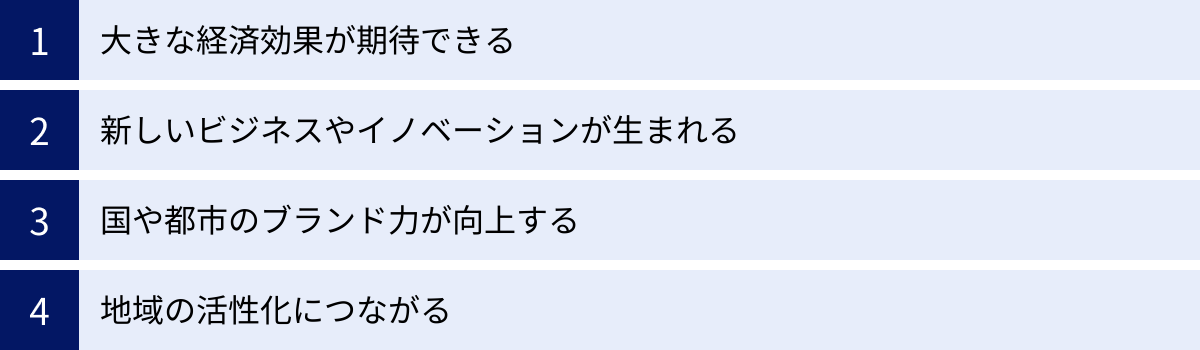
MICEを誘致・開催することは、開催地の国や都市、そして地域社会に多岐にわたる恩恵をもたらします。そのメリットは、単に多くの人が集まることによる直接的な経済効果に留まりません。ビジネスやイノベーションの創出、都市ブランドの向上、そして地域社会の活性化といった、長期的かつ無形の価値を生み出す点にこそ、MICEの真価があります。ここでは、MICEがもたらす代表的な4つのメリットについて、深く掘り下げていきます。
① 大きな経済効果が期待できる
MICEがもたらす最も分かりやすく、かつ強力なメリットは、その絶大な経済効果です。MICEの参加者は、ビジネスや学術研究といった明確な目的を持って訪れるため、一般的な観光客とは消費行動のパターンが大きく異なります。
- 一人あたりの消費額が高い:
MICE参加者は、会議参加費や出展料に加え、宿泊費、交通費、飲食費、さらには同僚や取引先との会食、お土産代、会議前後の観光(プレ・ポストコングレスツアー)など、様々な場面で支出を行います。日本政府観光局(JNTO)の調査によると、MICEで来日したビジネス目的の外国人旅行者の一人あたりの消費額は、一般の観光客の約2倍に達するというデータもあります。これは、滞在期間が比較的長いことや、企業の経費で支出する割合が高いことなどが理由として挙げられます。 - 幅広い産業への経済波及効果:
MICEの開催は、特定の産業だけでなく、地域経済全体に好影響を及ぼします。- 直接効果: 会議施設、ホテル、飲食店、交通機関、小売店などが直接得る売上。
- 間接効果(一次波及効果): MICEの運営に必要な様々なサービスや物品の需要創出。例えば、イベント設営会社、印刷会社、警備会社、通訳・翻訳サービス、ケータリング業者、清掃業者など、多岐にわたる関連産業が潤います。
- 二次波及効果: これらの直接的・間接的な経済活動によって得た所得が、地域内でさらに消費されることで生まれる効果。MICE関連産業の従業員が地域の商店で買い物をするなど、経済の好循環が生まれます。
| MICEによる経済波及効果の例 |
| :— | :— |
| 直接効果 | 会議場・展示場利用料、宿泊費、飲食費、交通費、参加登録費、観光・娯楽費、ショッピング代 |
| 間接効果(一次) | イベント企画・設営、印刷・広告、音響・映像機材、通訳・翻訳、警備・清掃、ケータリング、人材派遣、リース用品 |
| 間接効果(二次) | 上記産業の従業員による個人消費(家賃、食費、光熱費、教育費、娯楽費など) |
- 観光閑散期の需要平準化:
一般的な観光需要は、ゴールデンウィークや夏休み、年末年始などの特定の時期に集中しがちです。一方、MICEはビジネススケジュールに基づいて計画されるため、観光のオフシーズンに開催されることも少なくありません。これにより、宿泊施設や交通機関は年間を通じて安定した稼働率を維持しやすくなり、雇用の安定にも繋がります。
このように、MICEは開催地域に大規模かつ多層的な経済的インパクトをもたらす、極めて効率の良い経済活性化策なのです。
② 新しいビジネスやイノベーションが生まれる
MICEは、単なるお金の循環を生むだけでなく、新たな価値創造の触媒としての役割を果たします。世界中から多様なバックグラウンドを持つ人々が一堂に会することで、知的な化学反応が起こり、新しいビジネスやイノベーションの種が生まれるのです。
- 最先端の知識・技術の集積:
国際会議や学術大会(Convention)は、その分野における世界トップレベルの研究者や専門家が集結する場です。彼らが発表する最新の研究成果や、議論を通じて交わされる最先端の知見は、開催地の研究機関や企業にとって、他では得られない貴重な情報源となります。これにより、地域の学術・技術レベルが底上げされ、国際的な競争力向上に繋がります。 - グローバルなネットワーキングの機会:
MICEの会場では、コーヒーブレイクやレセプションパーティーなど、公式なセッション以外にも多くの交流の場が設けられています。こうしたインフォーマルなコミュニケーションの中から、思いがけない出会いが生まれ、国境を越えた共同研究、新たなビジネスパートナーシップ、新規事業への投資といった具体的な成果に発展することが少なくありません。
例えば、ある都市で開催された環境技術の国際展示会をきっかけに、地元の部品メーカーが海外の大手企業から技術力を評価され、新たなサプライヤー契約を結ぶといったシナリオが考えられます。これは、地元企業にとって、自力では開拓が難しいグローバル市場への扉を開く絶好の機会です。 - 開催地産業の振興:
開催地の強みである産業分野に関連したMICEを戦略的に誘致することで、その産業を強力にバックアップできます。例えば、自動車産業が盛んな都市でモビリティ関連の国際会議を開催すれば、地元の自動車メーカーや部品サプライヤーは、自社の技術を世界に向けて効果的にアピールできます。また、会議のプログラムとして工場見学(テクニカルビジット)などを組み込めば、参加者の理解を深め、より具体的な商談へと結びつきやすくなります。MICEは、地域産業の「ショーケース」として機能し、新たなビジネスチャンスを磁石のように引き寄せるのです。
③ 国や都市のブランド力が向上する
大規模で権威あるMICEの開催は、開催地である国や都市の国際的な認知度と評価を大きく向上させる、強力なシティプロモーションツールです。
- 世界に向けたPR効果:
G20サミットやオリンピックのようなメガイベントはもちろんのこと、特定の分野で権威のある国際会議が開催されるだけでも、その都市名は世界中のメディアで報道されます。これにより、これまでその都市を知らなかった人々にも名前が知れ渡り、「国際的なイベントを開催できる能力のある都市」というポジティブなイメージが形成されます。これは、多額の広告費を投じるよりも効率的なPR活動と言えるでしょう。 - 「知的・文化的なハブ」としてのブランディング:
特定の分野(例:医学、IT、環境、文化など)のMICEを継続的に誘致・開催することで、その都市は単なる観光地としてではなく、「その分野における世界の中心地(ハブ)」としてのブランドを確立できます。例えば、「〇〇市に行けば、医療分野の最新情報が手に入る」「△△市は、クリエイティブ産業の集積地だ」といった評判が定着すれば、世界中から優秀な人材や企業、投資が集まりやすくなります。これは、都市の長期的な発展に不可欠な知的資本の蓄積に繋がります。 - レガシー(遺産)の創出:
MICEの開催を契機として、新たなインフラが整備されたり、市民の国際交流意識が高まったりすることがあります。こうしたポジティブな変化は、イベント終了後も「レガシー」として地域に残り続けます。例えば、国際会議の開催に合わせて整備された公園や文化施設は、その後も市民の憩いの場として活用されます。また、ボランティアなどでイベント運営に関わった市民の経験は、地域のホスピタリティ向上や、将来のMICE開催を支える貴重な人材資産となります。MICEは、都市に形あるものと形のないものの両方のレガシーを残し、その魅力を永続的に高めていくのです。
④ 地域の活性化につながる
MICEは、経済やビジネスといった側面だけでなく、地域社会そのものにもポジティブな影響を与え、人々の暮らしを豊かにします。
- 文化交流と国際相互理解の促進:
世界中から訪れる多様な文化背景を持つ参加者と、地域住民が交流する機会が生まれます。参加者は、会議の合間や前後に地域の文化や歴史、食に触れることで、その土地への理解と愛着を深めます。一方、地域住民にとっても、海外からの訪問者と触れ合うことは、異文化への理解を深め、国際感覚を養う貴重な体験となります。学校での交流プログラムや、ホームステイの受け入れなどを通じて、次世代を担う子どもたちのグローバルな視野を育むことにも繋がります。 - 都市インフラ整備の促進:
大規模なMICEを誘致・開催するためには、国際基準を満たす会議施設や宿泊施設、スムーズな交通アクセスが不可欠です。MICE誘致を目標に掲げることで、国際空港とのアクセス改善、公共交通機関の多言語対応、無料Wi-Fiスポットの拡充、バリアフリー化など、都市インフラの整備や改善に弾みがつきます。これらの整備は、MICE参加者だけでなく、そこに住む住民や一般の観光客の利便性向上にも直結し、都市全体の生活の質を高めます。 - シビックプライド(地域への誇り)の醸成:
自分の住む街が、世界的なイベントの舞台となり、多くの人々から注目を浴びる。この事実は、地域住民に「自分たちの街は世界に誇れる素晴らしい場所なのだ」という自信と愛着(シビックプライド)を抱かせます。住民が一体となって訪問者を温かく迎え入れ、イベントを成功させようという機運が高まることで、地域の結束力も強まります。このシビックプライドは、地域の持続的な発展を支える、何より大切な原動力となるのです。
日本のMICEの現状と国際的な立ち位置
世界中の都市がMICE誘致にしのぎを削る中、日本はどのような立ち位置にいるのでしょうか。ここでは、客観的なデータに基づき、日本のMICEの現状と国際的なポジショニングを明らかにします。日本の強みと課題を把握することは、今後のMICE戦略を考える上で不可欠です。
世界の国際会議開催実績における日本の順位
国際会議の開催実績を測る上で最も権威のある指標の一つが、ICCA(International Congress and Convention Association / 国際会議協会)が毎年発表する統計レポートです。このレポートは、特定の基準(参加者50名以上、定期的開催、3カ国以上を巡回開催など)を満たす国際会議を対象としています。
最新の2023年実績(2024年5月発表)によると、日本の国際会議開催件数は363件で、国別ランキングでは世界第7位、アジア・太平洋地域では第1位となりました。これは、前年の世界13位(181件)からの大幅なランクアップであり、新型コロナウイルス感染症の影響からの力強い回復と、日本のMICE開催地としてのポテンシャルの高さを示しています。
| 2023年 国際会議開催件数 国別ランキング(ICCA基準) |
| :— | :— | :— |
| 順位 | 国名 | 開催件数 |
| 1位 | アメリカ | 690件 |
| 2位 | イタリア | 553件 |
| 3位 | スペイン | 505件 |
| 4位 | フランス | 472件 |
| 5位 | ドイツ | 463件 |
| 6位 | イギリス | 425件 |
| 7位 | 日本 | 363件 |
| 8位 | ポルトガル | 304件 |
| 9位 | カナダ | 296件 |
| 10位 | オランダ | 290件 |
(参照:日本政府観光局(JNTO) 報道発表資料 2024年5月16日)
この結果から、日本は欧米のMICE先進国に次ぐ、世界有数の国際会議開催国であることが分かります。特にアジア地域においては、長年のライバルであるシンガポールや韓国、中国などを抑えてトップの座を獲得したことは特筆すべき点です。この背景には、日本の持つ高い安全性、清潔さ、交通インフラの正確性、そして質の高いホスピタリティといった、開催地としての基本的な強みが国際的に高く評価されていることがあると考えられます。
また、円安が進行していることも、海外の主催者や参加者にとって日本の開催コストが相対的に割安になるため、誘致における追い風となっている側面もあります。パンデミックを経て、対面でのコミュニケーションの価値が再認識される中、リアル開催の場として日本が積極的に選ばれている状況がうかがえます。
日本国内の都市別開催件数ランキング
国全体としての実績だけでなく、国内のどの都市がMICE開催を牽引しているのかを見ることも重要です。ICCAの同統計によると、2023年の日本の都市別開催件数では、東京都区部が134件で世界14位(アジア・太平洋地域2位)と、国内トップの成績を収めました。
続いて、京都市が53件で世界40位(同7位)、横浜市が33件で世界70位(同15位)、福岡市が25件で世界92位(同21位)と、複数の都市が世界のトップ100にランクインしています。
| 2023年 日本国内 国際会議開催件数 都市別ランキング(ICCA基準) |
| :— | :— | :— |
| 国内順位 | 都市名 | 開催件数 |
| 1位 | 東京都区部 | 134件 |
| 2位 | 京都市 | 53件 |
| 3位 | 横浜市 | 33件 |
| 4位 | 福岡市 | 25件 |
| 5位 | 神戸市 | 20件 |
| 6位 | 札幌市 | 17件 |
| 7位 | 大阪市 | 16件 |
| 8位 | 名古屋市 | 14件 |
(参照:日本政府観光局(JNTO) 報道発表資料 2024年5月16日)
このランキングから、各都市が持つ独自の魅力がMICE誘致に繋がっていることが分かります。
- 東京: 日本の首都として、圧倒的な国際線のアクセス、豊富な宿泊施設、大規模なコンベンションセンターを備えており、あらゆる規模・分野のMICEに対応できる総合力が強みです。
- 京都: 世界的に有名な歴史・文化遺産が最大の魅力であり、ユニークな体験を求める参加者に強い訴求力を持ちます。学会や文化系の国際会議で特に人気が高いです。
- 横浜: 東京心臓部や羽田空港からのアクセスが良く、みなとみらい地区には大規模なMICE複合施設「パシフィコ横浜」があり、ビジネスと観光が融合した都市として評価されています。
- 福岡: アジアの主要都市への地理的な近さを活かし、「アジアへのゲートウェイ」としての地位を確立。コンパクトシティでありながら都市機能が集積しており、利便性の高さが魅力です。
このように、日本のMICEは一部の大都市に集中している傾向はありますが、それぞれの都市が独自の強みを活かして国際的な競争力を発揮しています。今後、さらに多くの地方都市がMICE誘致に成功するためには、自地域の持つユニークな資源(自然、食、文化、産業など)を再発見し、それをMICEのプログラムに組み込む戦略的な視点が求められるでしょう。
日本が抱えるMICE誘致の3つの課題
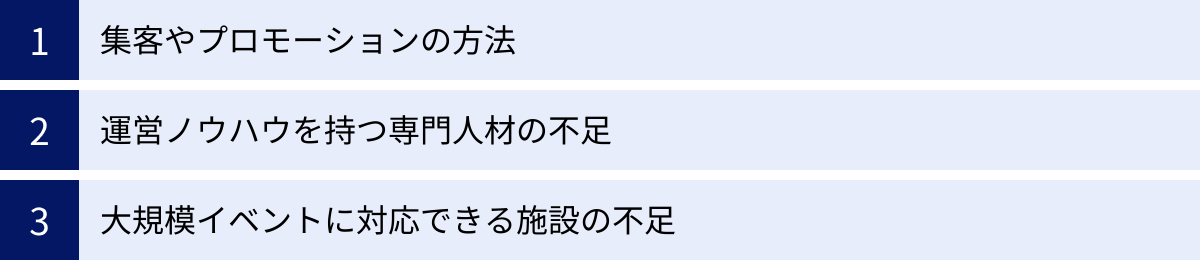
日本のMICEは国際的に高い評価を得ており、実績も回復基調にありますが、世界のトップクラス、特に欧米のMICE大国と肩を並べ、その地位を確固たるものにするためには、まだ乗り越えるべきいくつかの課題が存在します。ここでは、日本のMICE誘致が直面している代表的な3つの課題について考察します。
① 集客やプロモーションの方法
MICEの誘致は、世界中の都市との熾烈な競争です。特に近年は、シンガポール、韓国、タイ、マレーシアといったアジアの近隣諸国が、国策としてMICE産業の振興に莫大な投資を行い、最新の施設整備や大胆な支援策を打ち出しています。このような状況で日本が勝ち抜くためには、プロモーション戦略の高度化が急務です。
- ターゲットを絞った戦略的アプローチの不足:
日本のプロモーション活動は、しばしば「日本の安全性」や「おもてなし」といった、漠然としたイメージのアピールに留まりがちです。これらは確かに日本の強みですが、競争相手も同様の魅力を訴求しており、差別化が難しくなっています。今後は、誘致したい国際会議の主催団体やキーパーソンを具体的に特定し、彼らのニーズに直接響くような、オーダーメイドの提案を行う必要があります。例えば、特定の学術分野の会議であれば、その分野における日本の大学や研究機関の強み、関連企業の集積などを具体的に示し、「この会議を日本で開催する学術的・産業的意義」を説得力をもって伝えるアプローチが求められます。 - デジタルマーケティングの活用:
MICEの意思決定者は、オンラインで情報収集を行うことが一般的です。しかし、日本のMICE関連の情報発信は、まだウェブサイトやSNSの活用が十分とは言えない状況があります。海外の競合都市では、MICE専門のポータルサイトで施設情報や支援制度を分かりやすく提供したり、バーチャル視察ツアーを充実させたり、ターゲット層に合わせたデジタル広告を展開したりと、先進的な取り組みが進んでいます。多言語対応はもちろんのこと、検索エンジン最適化(SEO)を意識したコンテンツ作成や、データ分析に基づく効果的な情報発信など、デジタルマーケティングのノウハウを本格的に導入することが不可欠です。 - 官民連携のプロモーション体制:
MICE誘致は、自治体やコンベンションビューローだけで完結するものではありません。地域のホテル、旅行会社、PCO(会議運営専門会社)、さらには大学や研究機関、産業界が一体となった「オールジャパン」「オール〇〇(都市名)」でのプロモーション体制を構築することが重要です。それぞれの持つ専門知識やネットワークを結集し、一貫したメッセージを発信することで、プロモーションの説得力と効果は格段に高まります。
② 運営ノウハウを持つ専門人材の不足
MICEを成功に導くためには、施設のハード面だけでなく、それを動かすソフト面、すなわち専門的な知識と経験を持つ人材が不可欠です。しかし、日本では欧米に比べて、MICE運営を担うプロフェッショナルの層がまだ薄いという課題があります。
- PCO(Professional Congress Organizer)の不足と育成:
PCOは、国際会議の企画から誘致、準備、運営、事後処理までを一貫して手掛ける専門家集団です。複雑な予算管理、国内外からの参加者登録、プログラム調整、広報活動、当日のロジスティクス管理など、その業務は多岐にわたります。欧米ではPCOが一大産業として確立されていますが、日本ではまだ数が少なく、規模も小さい企業が多いのが現状です。国際的な大規模会議を円滑に運営できる、経験豊富で国際感覚に優れたPCOの育成と、その事業基盤の強化が求められています。 - 高度な専門スキルを持つ人材の必要性:
MICEの現場では、多様なスキルが求められます。例えば、海外の主催団体と対等に交渉を進めるための高度な語学力と交渉術。リアルとオンラインを融合させたハイブリッド会議を成功させるための最新のIT・映像技術に関する知識。参加者に特別な体験を提供するためのユニークなプログラム造成能力。そして、イベント全体を俯瞰し、無数のタスクを管理する優れたプロジェクトマネジメント能力などです。これらのスキルを持つ人材を育成するためには、大学や専門学校でのMICE専門教育プログラムの充実や、業界内での体系的な研修制度の確立、海外の先進事例を学ぶ機会の提供などが重要となります。 - 官民でのノウハウ共有:
自治体のMICE担当者と、民間のPCOやホテル、旅行会社などの間で、成功事例や失敗から得た教訓を共有する仕組みも重要です。定期的な情報交換会や共同研修などを通じて、地域全体としてMICE運営のノウハウを蓄積し、レベルアップを図っていく必要があります。属人的な経験に頼るのではなく、組織的な知識として継承していく体制づくりが、持続的な成功の鍵を握ります。
③ 大規模イベントに対応できる施設の不足
日本のMICE施設は高品質ですが、世界トップクラスの巨大な国際会議や展示会を誘致するには、施設の規模や機能の面で課題が見られます。
- 1万人規模以上のコンベンション施設の不足:
世界には、数万人規模の参加者を一度に収容できる巨大なコンベンションセンターが数多く存在します。特に、医学系やIT系の世界最大級のコングレスでは、1万人以上の参加者が集まることも珍しくありません。日本にも東京ビッグサイトや幕張メッセ、パシフィコ横浜といった大規模施設はありますが、欧米やアジアの主要な競合都市と比較すると、1万人以上を収容できる会議場と展示場が一体となった施設はまだ限られています。こうした最大級のMICEを取り込むためには、ハード面でのキャパシティ増強が避けては通れない課題です。 - 複合型MICE施設の必要性:
近年のトレンドは、会議場、展示場、ホテル、商業施設、エンターテインメント施設が一体となった「複合型MICE施設」です。参加者は、一つのエリア内を移動するだけで、会議への参加から宿泊、食事、ショッピング、娯楽まで全てを完結できます。これにより、移動のストレスが軽減され、滞在中の満足度が大きく向上します。シンガポールのマリーナベイ・サンズなどがその代表例です。日本でもIR(統合型リゾート)計画の中でこうした複合施設の整備が議論されていますが、既存の都市においても、MICE施設と周辺のホテルや商業施設が連携を強化し、一体的なサービスを提供することで、利便性を高める工夫が求められます。 - 施設の老朽化と機能更新:
既存のMICE施設の中には、建設から年数が経過し、老朽化が進んでいるものもあります。施設の改修や拡張はもちろんのこと、機能面のアップデートも重要です。例えば、全館をカバーする高速・大容量のWi-Fi環境の整備、高品質なハイブリッド配信に対応できるスタジオ設備の常設、サステナビリティに配慮した省エネ設備への更新など、時代のニーズに合わせた投資を継続的に行っていく必要があります。
これらの課題を克服することは容易ではありませんが、官民が連携し、長期的視点に立って戦略的に取り組むことで、日本はMICE大国としての地位をさらに高めることができるでしょう。
MICEの誘致を成功させるポイント
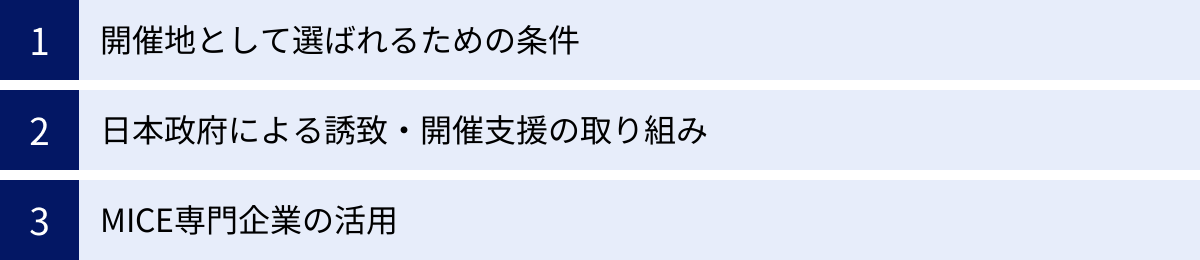
世界中の都市がしのぎを削るMICE誘致競争に勝ち抜くためには、自らの強みを最大限に活かし、弱点を克服するための戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、MICEの主催者から「開催地」として選ばれるための条件、日本政府の支援策、そして専門家の活用という3つの観点から、誘致を成功させるためのポイントを解説します。
開催地として選ばれるための条件
MICEの主催団体、特に国際会議の主催者は、開催地を決定する際に様々な要素を総合的に評価します。彼らの視点に立ち、選ばれるための条件を満たすことが誘致成功の第一歩です。
施設の充実度
まず基本となるのが、MICEを開催するためのハードウェア、すなわち施設のスペックです。
- キャパシティと柔軟性: 全体会議を行うためのメインホール、分科会用の多数の中小会議室、ポスターセッションや休憩スペースとして利用できる広いホワイエ(ロビー空間)、そして展示会を併催できる展示場など、イベントの規模と形式に合わせた十分なスペースが求められます。また、部屋のレイアウトを柔軟に変更できる可動式の間仕切りなども重要な評価ポイントです。
- 最新の設備: 高品質な音響・照明設備、大型スクリーンやプロジェクターといった映像設備は必須です。加えて、現代のMICEでは高速かつ安定したWi-Fi環境が生命線となります。数千人が同時に接続しても快適に利用できる通信インフラは、参加者満足度に直結します。ハイブリッド開催に対応できる配信機材やスタジオの有無も、近年ますます重要になっています。
治安の良さと衛生環境
世界中から多くの要人や参加者を受け入れる上で、安全・安心は何よりも優先される要素です。
- 治安の良さ: 凶悪犯罪やテロのリスクが低く、夜間でも安心して外出できる環境は、開催地選定における非常に大きなアドバンテージとなります。この点において、日本は世界トップクラスの安全性を誇り、強力なアピールポイントです。
- 衛生環境: 清潔な街並み、質の高い上下水道、そして信頼できる医療体制の存在も重要です。特にパンデミックを経て、公衆衛生に対する意識は世界的に高まっており、清潔な環境は参加者に大きな安心感を与えます。会議施設やホテルにおける高度な感染症対策も評価されます。
開催都市そのものの魅力
MICEは会議室の中だけで完結するものではありません。都市全体が持つ魅力が、参加者の体験価値を大きく左右します。
- アクセシビリティ: 国際空港からのアクセスが容易であること(所要時間、交通手段の選択肢)、そして市内の交通網(鉄道、地下鉄、バスなど)が発達しており、会場やホテル、観光地への移動がスムーズであることは必須条件です。公共交通機関の多言語対応や分かりやすい案内表示も、海外からの参加者にとって重要です。
- 宿泊・飲食施設の多様性: VIP向けの高級ホテルから、一般参加者向けの手頃なビジネスホテルまで、様々な予算に対応できる宿泊施設の選択肢が豊富にあることが求められます。また、地元の名物料理を楽しめるレストラン、ハラルやベジタリアンなど多様な食文化に対応できる飲食店、そしてレセプションや会食に利用できる魅力的な店舗の存在も、都市の評価を高めます。
会議後の観光や体験プログラム
会議の前後(プレ・ポスト)や、会議期間中の空き時間に、参加者やその同伴者が楽しめるプログラムは、開催地の付加価値を大きく高める要素です。
- プレ・ポストコングレスツアー: 会議のテーマに関連する施設(工場、研究所など)を訪れる「テクニカルビジット」や、近隣の観光地を巡るツアーは、参加者の満足度向上に大きく貢献します。
- ユニークな文化体験: 茶道、書道、着物着付け、伝統工芸体験といった日本ならではの文化プログラムは、海外からの参加者にとって忘れられない思い出となります。こうした「そこでしかできない体験」は、開催地決定の際の強力な決め手となり得ます。
- 同伴者向けプログラム: 会議に参加しない同伴者向けに、ショッピングツアーや料理教室、市内観光などの魅力的なプログラムを用意することも、主催者から高く評価されます。
日本政府による誘致・開催支援の取り組み
日本政府および日本政府観光局(JNTO)は、MICEの誘致・開催を促進するため、様々な支援プログラムを用意しています。これらの制度を積極的に活用することも、誘致成功の重要なポイントです。
JNTOは、国際MICEの誘致・開催に取り組む日本のコンベンション推進機関(都市・地域)や主催者に対し、以下のような多角的な支援を提供しています。
- 誘致活動への支援:
- 海外での誘致プロモーション活動(商談会出展など)への資金的支援
- 誘致に必要なプレゼンテーション資料やPRビデオの作成支援
- 海外の主催団体キーパーソンを日本へ招聘し、現地視察をサポート
- 開催支援:
- 開催が決定した国際会議の広報活動(ウェブサイト作成、パンフレット印刷など)への資金的支援
- 会議参加者向けの観光情報提供や伝統文化体験プログラムの提供サポート
- 海外からの参加者増加に向けたプロモーション支援
さらに、「国際会議誘致・開催貢献賞」という表彰制度も設けられています。これは、国際会議の誘致・開催に尽力し、日本のMICE振興に貢献した個人や団体を表彰するもので、MICE関係者のモチベーション向上に繋がっています。(参照:日本政府観光局(JNTO)公式サイト)
これらの支援策を最大限に活用し、官民一体となって誘致活動に取り組むことが、競争を勝ち抜く上で極めて有効です。
MICE専門企業の活用
MICEの誘致・開催は非常に専門性が高く、複雑な業務を伴います。そこで頼りになるのが、MICEを専門に取り扱うプロフェッショナル企業です。
- PCO(Professional Congress Organizer): 先述の通り、会議運営の専門会社です。企画立案、会場選定、予算管理、参加者登録システムの構築、演題管理、広報、当日の運営まで、会議運営に関するあらゆる業務を代行・サポートします。彼らの持つ豊富な経験とノウハウ、そして国内外のネットワークを活用することで、主催者は会議の中身の充実に専念でき、イベント全体の質を飛躍的に高めることができます。
- DMC(Destination Management Company): 開催地(デスティネーション)に関する深い知識を持つ専門会社です。会場やホテルの手配だけでなく、その地域ならではのユニークなパーティー会場の提案、交通手段の確保、特別な文化体験プログラムの企画・運営など、地域に根差したサービスを提供します。DMCと連携することで、参加者にとってより魅力的で記憶に残る体験を創出できます。
自前ですべてを賄おうとせず、こうした専門企業の力を借りることは、MICEを成功させるための賢明な選択と言えるでしょう。
MICEの未来と知っておきたい関連用語
MICEの世界は、社会情勢やテクノロジーの進化とともに、常に変化し続けています。ここでは、アフターコロナの新しい潮流や、MICEの可能性を広げる重要なコンセプト、そして理解を深めるために知っておきたい関連用語について解説します。
アフターコロナにおけるMICEの動向
新型コロナウイルスのパンデミックは、MICE業界に未曾有の打撃を与えると同時に、そのあり方を根本から見直すきっかけともなりました。アフターコロナの時代において、MICEはいくつかの新しい潮流のもとで進化を遂げています。
- 対面(リアル)開催の価値の再認識:
オンラインでのコミュニケーションが急速に普及した一方で、多くの人々は対面で会うことの重要性を再認識しました。画面越しでは得られない、偶発的な出会いや雑談から生まれるインスピレーション、ネットワーキングを通じて築かれる深い信頼関係、そして会場の一体感や熱気。これらはリアルなMICEならではの価値であり、今後もMICEの核であり続けるでしょう。 - 安全・安心とウェルビーイングの重視:
パンデミックを経て、参加者の安全・衛生に対する意識は恒久的に高まりました。会場の換気や消毒といった基本的な感染症対策はもちろんのこと、参加者が心身ともに健康でいられる「ウェルビーイング」への配慮が重要になっています。ストレスの少ない移動計画、健康的な食事の提供、リフレッシュできる休憩スペースの設置などが、開催地やイベントの評価を高める要素となります。 - サステナビリティ(持続可能性)への取り組み:
環境問題や社会課題への関心の高まりを受け、MICEの分野でもサステナビリティが重要なテーマとなっています。- 環境面: ペーパーレス化の推進、フードロス削減の取り組み、再生可能エネルギーの利用、公共交通機関の利用推奨など。
- 社会面: イベントを通じて地域のNPOや社会貢献活動を支援する「レガシープログラム」の実施、ダイバーシティ&インクルージョンへの配慮など。
サステナブルなMICEは、企業の社会的責任(CSR)を重視する主催者や参加者から選ばれるための必須条件になりつつあります。
オンライン・ハイブリッドMICEの可能性
パンデミック中に急速に普及したオンラインでのイベント開催は、MICEの形態に新たな選択肢をもたらしました。それが「ハイブリッドMICE」です。
ハイブリッドMICEとは、物理的な会場でのリアル開催と、インターネットを通じたオンライン配信を同時に行う形式のイベントです。この形式は、リアルとオンラインの「良いとこ取り」ができる可能性を秘めています。
| 開催形式 | メリット | デメリット・課題 |
|---|---|---|
| リアルMICE | ・深いネットワーキングが可能 ・偶発的な出会いや発見がある ・会場の一体感や熱気を共有できる |
・地理的、時間的、予算的な制約 ・参加できる人数に限りがある |
| オンラインMICE | ・地理的制約がなく世界中から参加可能 ・移動コストや時間が不要 ・コンテンツの録画・再利用が容易 |
・ネットワーキングが難しい ・一体感の醸成が困難 ・長時間の集中が難しい |
| ハイブリッドMICE | ・参加者の選択肢が広がり、参加者層が拡大する ・リアルとオンラインの長所を両立できる可能性がある ・イベントのリーチを最大化できる |
・運営が複雑でコストが高い ・リアルとオンラインの参加者の一体感をどう作るか ・高度な技術とノウハウが必要 |
ハイブリッドMICEを成功させる鍵は、単にリアルの様子を中継するだけでなく、オンライン参加者も積極的に議論に参加できる仕組みや、オンライン独自の交流の場を設けるなど、双方向性をいかに高めるかにあります。今後、イベントの目的やターゲットに応じて、リアル、オンライン、ハイブリッドの3つの形式を戦略的に使い分けることが、MICEのスタンダードとなっていくでしょう。
ユニークベニューとは
ユニークベニュー(Unique Venue)とは、その名の通り「特別な(Unique)」会場(Venue)のことです。コンベンションセンターやホテルの宴会場といったMICE専用施設ではなく、美術館、博物館、歴史的建造物、庭園、城、寺社仏閣、水族館といった、その土地ならではの特別な場所をMICEの会場として利用することを指します。
- ユニークベニューのメリット:
- 記憶に残る体験の提供: 参加者にとって、普段は入れないような特別な場所でのパーティーやレセプションは、忘れられない感動的な体験となり、イベント全体の満足度を飛躍的に高めます。
- 開催地の魅力発信: その土地の歴史や文化を象徴する場所を利用することで、言葉で説明する以上に雄弁に開催地の魅力を伝えられます。
- 高いPR効果: ユニークな場所でのイベントは話題になりやすく、参加者がSNSなどで発信する可能性も高いため、優れたPR効果が期待できます。
例えば、京都の由緒ある寺院の庭園で歓迎レセプションを開いたり、東京の美術館を貸し切ってガラディナー(晩餐会)を開催したりといった活用が考えられます。ユニークベニューは、MICEに「特別感」という付加価値を与え、他の都市との差別化を図るための強力な武器となります。
IR(統合型リゾート)とは
IR(Integrated Resort)とは、「統合型リゾート」と訳され、MICE施設(国際会議場・展示場)、ホテル、カジノ、劇場やテーマパークなどのエンターテインメント施設、ショッピングモール、レストランといった、多様な観光・商業施設が一体的に集積した大規模な複合施設を指します。
MICEの観点から見たIRの役割は非常に大きく、誘致における強力な競争力となります。
- 世界水準の大規模MICE施設: IRは、数千人~1万人以上を収容できる世界トップクラスの国際会議場や展示場を中核施設として備えていることが多く、これまで日本が誘致できなかった最大級のMICEの受け皿となり得ます。
- ワンストップでの利便性: 参加者は、同一敷地内で会議、宿泊、飲食、エンターテインメントの全てを享受できます。これにより移動の手間が省け、滞在中の利便性と満足度が大幅に向上します。
- 強力な集客力: IR自体が持つブランド力と魅力的なエンターテインメント機能により、MICEへの参加意欲を高める効果が期待できます。会議だけでなく、リゾートとしての滞在も楽しめるため、同伴者を伴った参加も促進されます。
日本では、IR整備法に基づき、大阪などでIRの開業に向けた準備が進められています。IRの誕生は、日本のMICE産業のポテンシャルを大きく引き上げ、国際競争力を新たなステージへと押し上げる起爆剤となる可能性を秘めています。
まとめ
本記事では、ビジネスと観光の交差点に位置する戦略的活動「MICE」について、その定義からメリット、日本の現状と課題、そして未来の展望までを多角的に解説してきました。
最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。
- MICEの定義: MICEとは、Meeting(会議・研修)、Incentive(招待・報奨旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition/Event(展示会)の4要素の頭文字を取った総称です。
- MICEのメリット: 開催地にもたらす恩恵は、①大きな経済効果、②新しいビジネスやイノベーションの創出、③国や都市のブランド力向上、④地域の活性化という4つの側面に大別され、その影響は非常に広範囲に及びます。
- 日本の現状: 日本は国際会議の開催実績で世界トップクラスに位置し、特にアジアでは主導的な役割を果たしています。しかし、世界のMICE大国との競争は激しく、プロモーション戦略、専門人材の育成、大規模施設の確保といった課題も抱えています。
- 成功のポイント: MICE誘致を成功させるには、施設の充実度や都市の魅力といったハード・ソフト両面の強化に加え、政府の支援策やPCOといった専門家の力を活用し、官民一体で戦略的に取り組むことが不可欠です。
- 未来の展望: 今後のMICEは、リアル開催の価値を再認識しつつ、ハイブリッド形式の可能性を追求し、サステナビリティを重視する方向へと進化していきます。また、ユニークベニューの活用やIR(統合型リゾート)の登場は、日本のMICEに新たな魅力と競争力をもたらすでしょう。
MICEは、単に多くの人々を集めるイベントではありません。それは、知と人が交流し、新たな価値を創造することで、都市や国、そして社会全体の未来を豊かにしていくための強力なエンジンです。この記事を通じて、MICEの持つ奥深い魅力と、その計り知れない可能性について、少しでも理解を深めていただけたなら幸いです。

