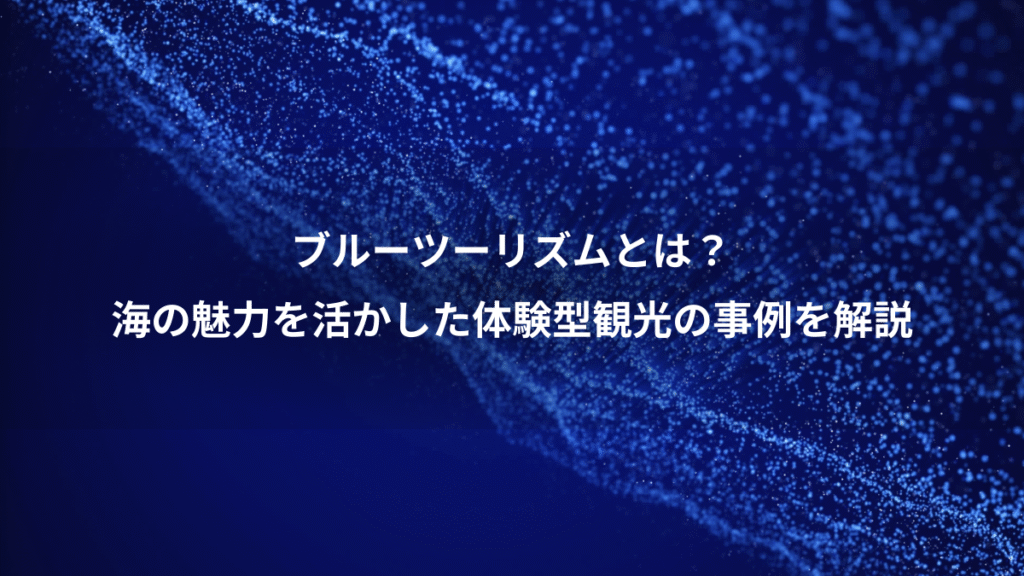日本が四方を海に囲まれた海洋国家であることは、言うまでもありません。古来より私たちは、海から食料や資源といった数多くの恩恵を受け、独自の文化や暮らしを育んできました。しかし近年、漁業者の高齢化や後継者不足、海洋環境の変化など、海と人々の関わりを取り巻く状況は大きな課題に直面しています。
こうした中、新たな希望として注目されているのが「ブルーツーリズム」です。この記事では、ブルーツーリズムの基本的な概念から、注目される背景、メリットや課題、具体的な体験内容、そして今後の展望までを網羅的に解説します。海の持つ無限の可能性を再発見し、地域を元気にする新しい旅のスタイル、ブルーツーリズムの魅力に迫っていきましょう。
目次
ブルーツーリズムとは

ブルーツーリズムという言葉を耳にする機会が増えてきましたが、具体的にどのような観光スタイルを指すのでしょうか。ここでは、その定義を明確にし、類似する観光概念である「グリーンツーリズム」や「エコツーリズム」との違いを比較しながら、ブルーツーリズムの本質を深く掘り下げていきます。
漁村地域で海の魅力を体験する観光スタイル
ブルーツーリズムとは、漁村地域(浜)に滞在し、その地域ならではの海の自然、漁業、食、文化、そして人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動を指します。単に美しい海の景色を眺めるだけでなく、漁業体験やマリンアクティビティ、郷土料理づくりといった「体験」を通じて、その土地の暮らしや文化を深く理解することを目的としています。
この観光スタイルの最大の特徴は、海とその周辺地域が持つあらゆる資源を「観光コンテンツ」として捉える点にあります。具体的には、以下のような要素が含まれます。
- 自然資源: 透明度の高い海、美しい海岸線、豊かな生態系(サンゴ礁、干潟など)、離島の景観
- 産業資源: 定置網漁や一本釣りなどの漁業活動、カキや真珠の養殖業、水産加工業(干物、塩づくりなど)
- 文化資源: 漁師飯や郷土料理、祭りや伝統行事、海女文化、漁村の歴史的な町並み
- 人的資源: 漁師、海女、水産加工業者、民宿の経営者など、地域に暮らす人々との交流
これらの資源を組み合わせた体験プログラムに参加することで、観光客は都市生活では得られない非日常的な時間と、地域の人々との温かい触れ合いを得られます。一方で、地域側にとっては、観光が新たな産業となり、地域の活性化や文化の継承につながるという大きな可能性があります。つまり、ブルーツーリズムは観光客と地域の双方に利益をもたらし、持続可能な関係を築くことを目指す観光のあり方なのです。
グリーンツーリズムとの違い
ブルーツーリズムとしばしば比較されるのが「グリーンツーリズム」です。両者は「農山漁村地域に滞在し、地域の人々と交流しながら自然や文化を体験する」という点で共通していますが、主な活動の舞台(フィールド)に明確な違いがあります。
| 比較項目 | ブルーツーリズム | グリーンツーリズム |
|---|---|---|
| 主なフィールド | 海、漁村、離島 | 山、農村、里山 |
| 主な体験内容 | 漁業体験(定置網、釣り等)、マリンアクティビティ、シーフード料理、海女文化体験、塩づくり | 農業体験(田植え、稲刈り、野菜収穫)、林業体験、酪農体験、郷土料理づくり、古民家滞在 |
| 主な地域資源 | 海の幸、漁船、漁港、海の景観、海洋生物 | 農産物、森林、田園風景、家畜 |
| 目的の共通点 | ・地域経済の活性化 ・都市住民と農山漁村住民の交流促進 ・伝統文化や自然環境の保全と継承 |
・地域経済の活性化 ・都市住民と農山漁村住民の交流促進 ・伝統文化や自然環境の保全と継承 |
簡単に言えば、グリーンツーリズムが「農山村」を舞台にするのに対し、ブルーツーリズムは「漁村」に特化した概念です。農林水産省の定義では、グリーンツーリズムは農山漁村地域での滞在型余暇活動の総称としており、広義にはブルーツーリズムもグリーンツーリズムの一種と捉えることもできます。しかし、近年では漁村地域の特性や課題により焦点を当てるため、ブルーツーリズムという言葉が独立して使われることが一般的になっています。
エコツーリズムとの違い
もう一つ、ブルーツーリズムと関連が深いのが「エコツーリズム」です。エコツーリズムは、「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、その保全に責任を持つ観光のありかた」と定義されています。(参照:環境省 エコツーリズムのススメ)
ブルーツーリズムとエコツーリズムは、「自然環境の保全」を重視する点で共通項が多く、特にサンゴ礁の保全活動や海洋ごみの清掃活動といったプログラムは、両方の性質を併せ持っています。しかし、その主眼には少し違いがあります。
| 比較項目 | ブルーツーリズム | エコツーリズム |
|---|---|---|
| 主眼(最も重視する点) | 漁業や漁村の「暮らし・文化・なりわい」の体験と地域活性化 | 自然環境や歴史文化の「保全」と「学習」 |
| 活動の対象 | 漁業、食文化、マリンスポーツなど、産業やレジャー活動を含む幅広い海の魅力 | 主に自然環境や生態系、歴史文化遺産 |
| 経済的側面 | 漁業者の所得向上や地域経済の活性化という側面が強い | 観光収益を環境保全活動に還元する仕組みを重視 |
エコツーリズムが環境保全を第一の目的とするのに対し、ブルーツーリズムは漁業という「産業」や、漁村の「生活文化」そのものを観光資源として活用し、地域の経済的な自立や活性化を目指すという側面がより強いと言えます。もちろん、ブルーツーリズムにおいても海の環境保全は不可欠な要素ですが、そのアプローチは「豊かな海がなければ漁業も成り立たない」という、生業(なりわい)と直結した視点からなされることが多いのが特徴です。
このように、ブルーツーリズムはグリーンツーリズムの「海バージョン」でありながら、エコツーリズムの「環境保全」の理念も取り入れた、複合的で奥深い観光スタイルなのです。
ブルーツーリズムが注目される背景
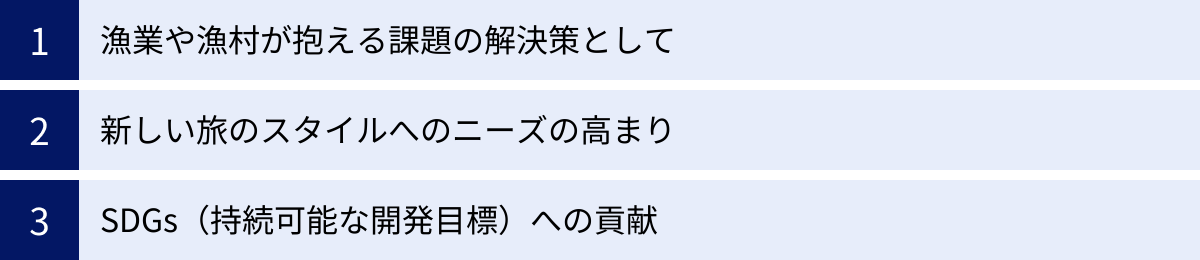
なぜ今、ブルーツーリズムがこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、漁業や漁村が直面する深刻な課題、変化する旅行者の価値観、そして世界的な潮流であるSDGsへの貢献という、3つの大きな要因が絡み合っています。
漁業や漁村が抱える課題の解決策として
現代の日本の漁業・漁村は、多くの構造的な課題を抱えています。ブルーツーリズムは、これらの課題に対する有効な処方箋の一つとして大きな期待が寄せられています。
第一に、漁業就業者の著しい減少と高齢化です。総務省の国勢調査によると、漁業就業者数は年々減少し続けており、同時に高齢化率も非常に高い水準にあります。このままでは、長年培われてきた漁業の技術や知識が途絶え、地域の水産業そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。ブルーツーリズムを通じて都市部の若者や子どもたちが漁業の現場に触れる機会が増えれば、漁業への関心が高まり、将来の担い手確保やIターン・Uターン移住につながる可能性があります。
第二に、漁業収入の不安定さです。漁業は、燃油価格の高騰、漁獲量の変動、魚価の低迷といった外部要因に大きく左右される不安定な産業です。ブルーツーリズムを導入することで、漁業者は漁業収入に加えて、観光ガイド料や体験料、民宿経営、直販による水産物販売など、新たな収入源を確保できます。これにより経営が安定し、漁業を継続していくための経済的基盤を強化できます。
第三に、漁村の活力低下です。人口減少や少子高齢化により、多くの漁村では地域コミュニティの維持が困難になりつつあります。祭りの担い手がいなくなったり、商店が次々と閉店したりと、地域の活気が失われています。ブルーツーリズムによって交流人口が増加すれば、地域に新たな賑わいが生まれます。観光客との交流は地域住民にとっても刺激となり、自分たちの地域の魅力や価値を再認識するきっかけにもなります。これが、シビックプライド(地域への誇りと愛着)の醸成につながり、地域全体の活性化を促進するのです。
新しい旅のスタイルへのニーズの高まり
観光客、つまり旅行者側の価値観の変化も、ブルーツーリズムが支持される大きな理由です。かつての団体旅行に代表されるような、名所旧跡を巡る「モノ消費」型の観光から、そこでしかできない体験や地域の人々との交流を重視する「コト消費」型の観光へと、旅のスタイルは大きくシフトしています。
現代の旅行者は、単に美しい景色を見るだけでは満足しません。その土地の歴史や文化の背景を知りたい、地元の人しか知らない穴場を訪れたい、現地の人の暮らしに触れてみたいといった、より本質的で深い学びや感動を求める傾向が強まっています。
ブルーツーリズムは、こうしたニーズにまさに合致する観光スタイルです。
- 本物志向: 漁師と一緒に船に乗り、実際に網を引く体験は、どんな観光施設よりもリアルで強烈な「本物」の体験です。
- 交流志向: 漁家民宿に泊まり、食卓を囲んで漁師の武勇伝を聞く。こうした何気ない会話の中にこそ、旅の醍醐味があります。
- 体験価値: 自分で釣った魚を、その場でさばいて食べるという一連の体験は、レストランで高級料理を食べるのとは全く異なる価値を持ちます。
さらに、SNSの普及により、誰もが知っている有名な観光地よりも、自分だけの特別な体験を写真や動画で共有したいという欲求が高まっています。漁村でのユニークな体験は、まさに「インスタ映え」するコンテンツの宝庫であり、情報発信力の高い若者層を惹きつける強い魅力を持っているのです。このような旅行者の価値観の変化が、ブルーツーリズという新しい旅の形を力強く後押ししています。
SDGs(持続可能な開発目標)への貢献
2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」は、世界が共通して目指すべき17のゴールを掲げています。ブルーツーリズムは、その理念と非常に親和性が高く、特に以下の3つの目標達成に大きく貢献する可能性を秘めています。
目標8「働きがいも経済成長も」
この目標は、すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進することを目指しています。ブルーツーリズムは、漁業という第一次産業と観光という第三次産業を融合させることで、漁村地域に新たな雇用を創出し、経済を多角化します。漁業体験のガイド、民宿の運営、特産品開発・販売など、多様な仕事が生まれることで、若者や女性が地域で働き続ける選択肢が増え、持続可能な経済成長につながります。
目標11「住み続けられるまちづくりを」
この目標は、都市や人間居住を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることを目指します。ブルーツーリズムは、都市部からの交流人口を増やすことで、人口減少に悩む漁村の活力を維持し、人々が住み続けられるまちづくりに貢献します。また、観光資源として地域の文化遺産(例:海女文化、伝統的な祭り)や自然遺産(例:美しい海岸線)の価値が再評価されることで、それらを保護・保全しようという機運が高まります。これは、地域のアイデンティティを守り、次世代に継承していく上で極めて重要です。
目標14「海の豊かさを守ろう」
この目標は、持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目指しています。ブルーツーリズムは、観光客が海の環境問題について学ぶ絶好の機会を提供します。サンゴの植え付け体験やビーチクリーン活動に参加することで、海洋プラスチック問題や生態系の重要性について当事者意識を持つことができます。また、漁業者自身も、観光客に豊かな海を見せるためには、乱獲を防ぎ、資源管理を徹底する必要があることを再認識します。このように、ブルーツーリズムは海の恵みを持続的に利用していくための意識改革を、地域住民と観光客の双方に促す力を持っています。
ブルーツーリズムの3つのメリット
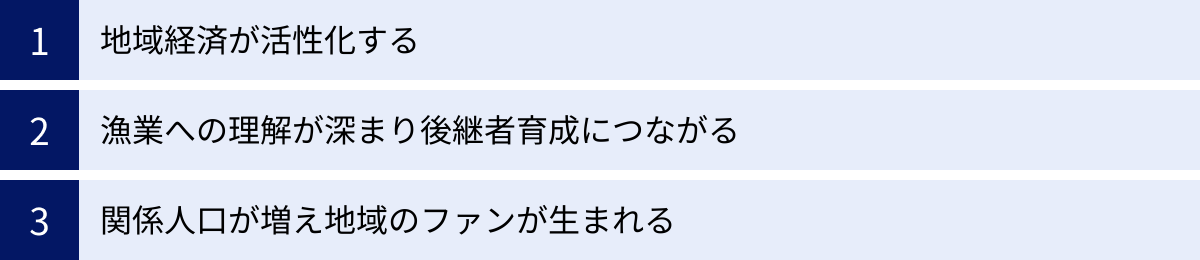
ブルーツーリズムの実践は、地域社会、漁業、そして訪れる人々に多岐にわたる恩恵をもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリット、「地域経済の活性化」「漁業理解と後継者育成」「関係人口の創出」について、具体的な効果とともに詳しく解説します。
① 地域経済が活性化する
ブルーツーリズムがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、地域経済への貢献です。これまで漁業収入に大きく依存してきた漁村に、観光という新たな収益の柱が加わることで、経済構造が強化され、地域全体が潤います。
まず、直接的な経済効果が挙げられます。観光客は地域で様々なお金を使います。
- 体験料: 漁船への乗船料、釣り体験料、料理教室の参加費など。
- 宿泊費: 漁家民宿や地域の旅館・ホテルへの支払い。
- 飲食費: 地元の食堂での食事、獲れたての魚介類の購入費。
- 交通費: 現地での移動手段(レンタカー、観光船など)の利用料。
- 土産物代: 水産加工品(干物、珍味など)や地域特産品の購入費。
これらの収入は、漁業者や民宿経営者だけでなく、飲食店、土産物店、交通事業者など、地域の幅広い業種に直接的な利益をもたらします。特に、漁業者が自ら漁獲した水産物を加工・直販することで、中間マージンを省き、より高い収益を得ることが可能になります。これは「6次産業化」(1次×2次×3次産業の融合)の好例であり、漁業の付加価値を飛躍的に高める取り組みです。
さらに、間接的な経済効果(波及効果)も無視できません。例えば、観光客の増加に伴い、飲食店が地元の農家から仕入れる野菜の量が増えたり、宿泊施設がリネン業者や清掃業者に新たな仕事を発注したりします。また、ブルーツーリズム事業を運営するために必要な資材(船の燃料、釣り具、パンフレット印刷など)の購入も、地域内の関連業者を潤します。このように、一つの観光消費が、玉突きのように地域内の様々な産業に影響を与え、経済全体を押し上げていくのです。
このようにして生まれた新たな収益は、地域のインフラ整備や後継者への投資、新たな体験プログラムの開発などに再投資され、持続的な地域発展の好循環を生み出す原動力となります。
② 漁業への理解が深まり後継者育成につながる
多くの人々、特に都市部で暮らす人々にとって、「漁業」は食卓に並ぶ魚の向こう側にある、遠い世界の出来事かもしれません。その仕事がいかに過酷で、専門的な知識と技術を要し、そして自然の恵みと隣り合わせの魅力的なものであるかを知る機会はほとんどありません。
ブルーツーリズムは、この消費者と生産者の間にある大きな隔たりを埋める架け橋となります。観光客が漁師の船に同乗し、夜明け前の暗い海へと出発する。重い網を仲間と協力して引き揚げ、キラキラと輝く魚が水揚げされる瞬間に立ち会う。こうした生々しい現場体験は、スーパーの鮮魚コーナーを眺めているだけでは決して得られない、深い感動と理解をもたらします。
この「理解の深化」は、二つの重要な効果を生み出します。一つは、水産物への価値観の変化です。魚一匹一匹が、漁師たちの厳しい労働と自然の恵みの結晶であることを実感することで、食べ物を大切にする気持ちや、適正な価格で魚を購入しようという意識が芽生えます。これは、安価な輸入品に押されがちな国産水産物の消費拡大にもつながる可能性があります。
もう一つが、漁業という仕事への関心の喚起と後継者育成への貢献です。体験に参加した若者や子どもたちの中から、「漁師ってかっこいい」「自分もこんな仕事をしてみたい」と感じる人が現れるかもしれません。すぐに就業に結びつかなくとも、漁業を将来の職業選択の一つとして意識するきっかけになるだけで、大きな一歩です。実際に、ブルーツーリズムでの体験をきっかけに漁村へ移住し、研修を経て漁師になったというケースも生まれ始めています。
漁業の魅力を、言葉だけでなく五感を通じたリアルな体験として伝えること。これこそが、深刻な後継者不足という課題に対する、ブルーツーリズムならではのユニークで効果的なアプローチなのです。
③ 関係人口が増え地域のファンが生まれる
ブルーツーリズムは、一度訪れたら終わりの「観光客」を、地域に継続的に関わる「関係人口」へと変える力を持っています。関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、その地域に多様な形で関わる人々のことを指します。
その鍵を握るのが、地域の人々との「顔の見える関係」の構築です。漁業体験を教えてくれた漁師さん、美味しい漁師飯を振る舞ってくれた民宿のおかみさん。こうした人々との間に生まれる温かい人間関係は、旅が終わった後も心に残り、「またあの人に会いにいきたい」という強い動機になります。
こうして生まれた地域の「ファン」は、様々な形で地域を応援してくれる大切な存在となります。
- リピーター化: 何度も同じ地域を訪れ、定期的にお金を使ってくれる上得意客になります。
- 特産品の購入: 旅の後も、オンラインショップなどを通じてその地域の水産物や特産品を継続的に購入してくれます。
- 情報発信: SNSや口コミで地域の魅力を発信し、新たな観光客を呼び込む「歩く広告塔」の役割を果たしてくれます。
- 地域活動への参加: 祭りの手伝いや、特産品開発のアイデア出しなど、地域づくりの活動にボランティアとして参加してくれることもあります。
このような関係人口の存在は、地域にとって計り知れない財産です。彼らは、地域住民だけでは不足しがちな「外からの視点」や専門的なスキルを提供してくれることもあり、地域づครの新たな可能性を引き出すきっかけにもなります。
一度きりの消費関係で終わらせず、人と人との繋がりを通じて長期的な応援団を育てること。これが、ブルーツーリズムがもたらす3つ目の、そして最も持続可能なメリットと言えるでしょう。
ブルーツーリズムが抱える課題
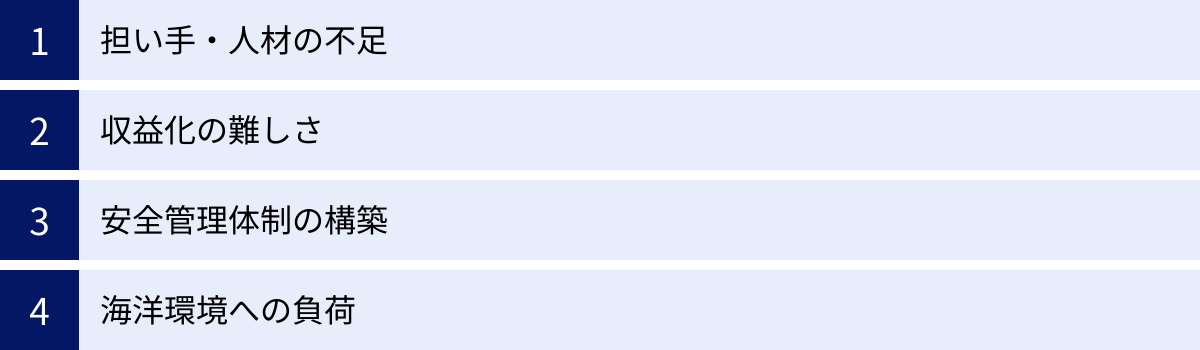
ブルーツーリズムは多くの可能性を秘めている一方で、その導入と継続にはいくつかの乗り越えるべき壁が存在します。担い手不足、収益化の難しさ、安全管理、環境負荷といった課題に真摯に向き合うことが、持続可能な取り組みを実現する上で不可欠です。
担い手・人材の不足
ブルーツーリズムを推進する上での最大の課題の一つが、企画・運営を担う人材の不足です。特に、中心的な役割を期待される漁業者は、本来の漁業活動だけでも多忙を極めています。早朝から漁に出て、日中は網の手入れや船の整備、水揚げ後の処理など、休む暇もありません。その上で、観光客の受け入れ準備、当日のガイド、予約管理といった追加業務をこなすのは、並大抵のことではありません。
また、漁業のプロフェッショナルであっても、観光事業のプロフェッショナルであるとは限りません。
- 企画・マーケティング能力: どのような体験プログラムが観光客に響くのか、どのように情報を発信して集客すればよいのか、といったノウハウが不足している場合が多い。
- 接客・ガイドスキル: 参加者に楽しんでもらい、安全を確保しながら、漁業の魅力や地域の文化を分かりやすく伝えるコミュニケーション能力が求められる。
- 多言語対応: インバウンド(訪日外国人観光客)を取り込むためには、語学力も必要となる。
これらのスキルを持つ人材は、特に高齢化が進む漁村では希少です。そのため、地域内外から多様なスキルを持つ人材を発掘・育成し、漁業者と連携する体制を築くことが急務となります。例えば、地域の観光協会やNPOが漁業者と観光客の間のコーディネーター役を担ったり、都市部から地域おこし協力隊を受け入れて企画運営を任せたりといった工夫が求められます。漁業者個人の負担に頼るのではなく、地域全体で役割分担し、サポートし合う仕組みづくりが成功の鍵を握ります。
収益化の難しさ
「観光事業を始めてみたものの、思ったように儲からない」というのも、ブルーツーリズムが直面する現実的な課題です。収益化が難しい背景には、いくつかの要因があります。
第一に、適正な価格設定の難しさです。安すぎれば労力に見合わず事業として継続できませんが、高すぎれば観光客が集まりません。体験の価値を客観的に評価し、燃料代や保険料、人件費といったコストを正確に算出した上で、ターゲット層が納得する価格を設定する必要があります。しかし、これまで「おもてなし」を無償のサービスとして提供してきた文化がある地域では、自分たちの提供する体験に値段をつけることに心理的な抵抗を感じるケースも少なくありません。
第二に、集客の不安定さです。ブルーツーリズムは、天候に大きく左右されます。悪天候が続けば、予約がすべてキャンセルになり、収入がゼロになるリスクも伴います。また、観光需要には季節変動があり、夏休みなどの繁忙期以外は閑散としがちです。年間を通じて安定した集客を実現するためには、天候に左右されない屋内プログラム(料理体験、工芸体験など)を開発したり、企業の研修や教育旅行といった新たな顧客層を開拓したりする戦略が必要です。
第三に、小規模経営の限界です。多くのブルーツーリズムは、個人経営や小規模なグループで運営されており、スケールメリットを出しにくい構造にあります。一日に受け入れられる人数に限りがあるため、売上の上限もおのずと決まってしまいます。複数の事業者が連携して広域的なツアーを組んだり、共同で広報活動や予約システムを導入したりすることで、コストを削減し、より多くの観光客を呼び込むことが可能になります。
安全管理体制の構築
海での活動は、常に危険と隣り合わせです。ブルーツーリズムを提供する事業者にとって、参加者の安全を確保することは何よりも優先されるべき絶対的な責務です。万が一にも事故が起これば、楽しいはずの体験が一転して悲劇となり、事業の存続そのものが危うくなります。
徹底した安全管理体制を構築するためには、以下のような多角的な対策が不可欠です。
- 保険への加入: 事業活動中の万一の事故に備え、適切な賠償責任保険に加入することは必須です。船を利用する場合は、遊漁船業者としての登録や、船客賠償責任保険への加入が法律で義務付けられている場合もあります。
- 緊急時対応マニュアルの整備: 落水、急病人、天候の急変など、想定されるあらゆる事態に対応するためのマニュアルを作成し、スタッフ全員で共有・訓練しておく必要があります。緊急連絡網(海上保安庁、消防、病院など)の整備も欠かせません。
- 安全装備の充実と点検: 参加者全員分のライフジャケットはもちろん、救命浮環、通信機器(無線、携帯電話)、応急手当用品などを必ず備え、定期的な点検を怠らないことが重要です。
- 催行中止基準の明確化: 波の高さ、風の強さ、視界など、体験プログラムを中止する客観的な基準をあらかじめ設定し、厳格に遵守する姿勢が求められます。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、重大な事故につながります。
- 参加者への事前説明(ブリーフィング): 体験開始前に、当日の天候や海の状況、注意事項、ライフジャケットの正しい着用方法、緊急時の行動などについて、参加者に丁寧に説明し、理解を求めることが事故防止の第一歩です。
これらの体制を整備するには専門的な知識とコストが必要であり、小規模な事業者にとっては大きな負担となります。地域の漁協や自治体が主導して安全講習会を実施したり、共通の安全基準ガイドラインを作成したりといった、地域ぐるみのサポート体制が求められます。
海洋環境への負荷
ブルーツーリズムは海の豊かさを守ることに貢献する可能性がある一方で、やり方を誤れば逆に海洋環境へ負荷をかけてしまうという、諸刃の剣の側面も持っています。観光客の増加が、意図せずしてデリケートな自然環境を損なうリスクを常に念頭に置かなければなりません。
具体的には、以下のような問題が懸念されます。
- オーバーツーリズム: 特定の地域や時間帯に観光客が集中しすぎることで、ゴミの増加、騒音、交通渋滞といった問題が発生します。
- 生態系への影響: 観光船がサンゴ礁を傷つけたり、エンジン音が海洋生物のストレスになったりする可能性があります。また、初心者が不用意に海底の生物に触れたり、踏みつけたりすることも考えられます。餌付け行為は、野生動物の生態を変えてしまう危険性もはらんでいます。
- 海洋汚染: 観光客が投棄するプラスチックごみや、船からの油の排出などが、海洋環境を汚染する原因となります。
これらのリスクを回避し、持続可能なブルーツーリズムを実現するためには、環境への影響を最小限に抑えるためのルール作りと、参加者の意識啓発が不可欠です。例えば、一日の受け入れ人数に上限を設ける(キャパシティコントロール)、環境に配慮した船の運行ルートを設定する、自然環境に触れる際の注意点をまとめたガイドラインを作成し遵守を求める、といった対策が有効です。
究極的には、ブルーツーリズムのプログラム自体に環境教育の要素を組み込むことが重要です。なぜサンゴ礁を守る必要があるのか、プラスチックごみが海洋生物にどのような影響を与えるのかを、体験を通じて学んでもらう。そうすることで、参加者は単なる消費者ではなく、海洋環境を守るパートナーへと変わっていくのです。
ブルーツーリズムで体験できることの種類
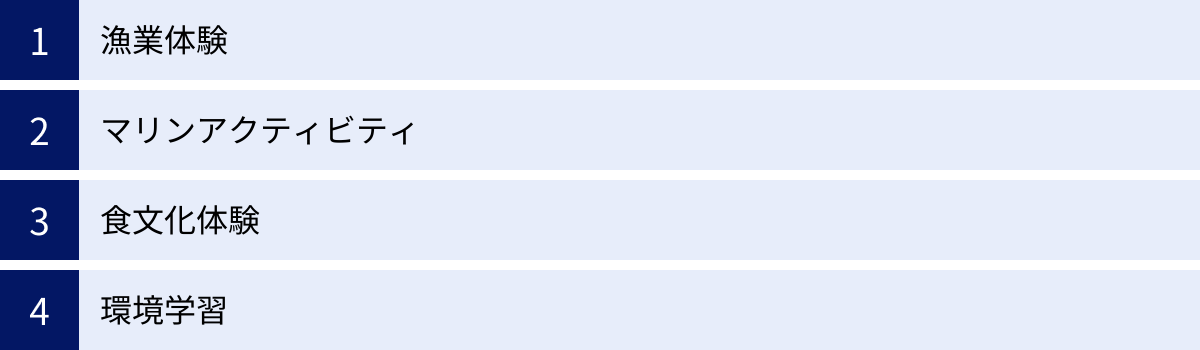
ブルーツーリズムの魅力は、その体験の多様性にあります。海という雄大な舞台で、漁業、アクティビティ、食、学びなど、様々な切り口から地域の魅力を満喫できます。ここでは、代表的な体験の種類を、具体的なプログラム例とともに紹介します。
漁業体験
ブルーツーリズムの王道とも言えるのが、現役の漁師と一緒に行うリアルな漁業体験です。地域の伝統的な漁法に触れることで、食卓に並ぶ魚がどのように獲られるのかを肌で感じられます。
定置網漁・刺し網漁体験
定置網漁は、沿岸に大規模な網を仕掛けておき、回遊してくる魚の群れを誘い込んで漁獲する方法です。体験では、早朝に漁師と共に船で漁場へ向かい、巨大な網を巻き上げていくダイナミックな水揚げ作業に立ち会ったり、手伝ったりします。網の中からアジ、サバ、イワシ、時にはブリやタイといった大物まで、多種多様な魚が現れる瞬間は圧巻です。
一方、刺し網漁は、魚の通り道にカーテンのように網を張り、網目に魚を絡ませて獲る漁法です。定置網漁ほどの規模ではありませんが、船上から網を手繰り寄せ、一匹一匹魚を外していく作業は、漁業の原始的な面白さを感じさせてくれます。いずれの体験も、漁師の熟練の技とチームワークを間近で見られる貴重な機会です。
養殖体験
天然の魚を獲るだけでなく、育てる漁業「養殖」の現場も、ブルーツーリズムの魅力的な舞台です。カキ、ホタテ、ワカメ、コンブ、モズク、真珠など、地域によって様々な養殖が行われています。
養殖体験では、船で養殖いかだまで行き、カキの殻を掃除したり、ホタテの稚貝をカゴに移し替えたりといった、育成作業の一部を体験できます。また、養殖の仕組みや、美味しいカキを育てるための工夫について、生産者から直接話を聞くこともできます。体験の最後には、獲れたてのカキやホタテをその場で焼いて味わうなど、最高の「ご褒美」が待っていることも少なくありません。食の安全やトレーサビリティ(生産履歴の追跡)への関心が高い現代において、生産の現場を自らの目で見られることは、大きな価値を持ちます。
マリンアクティビティ
海の美しさや楽しさを全身で感じるマリンアクティビティも、ブルーツーリズムの人気コンテンツです。単なるレジャーとしてだけでなく、地域の自然環境と結びつけて提供されるのが特徴です。
シーカヤック・SUP
シーカヤックやSUP(スタンドアップパドルボード)は、エンジン音のない静かな環境で、自分のペースで海上散歩を楽しめるアクティビティです。目線が水面に近いため、海との一体感を強く感じられます。普段は船では近づけないような、切り立った崖が続く海岸線や、洞窟(青の洞窟など)、無人島への上陸ツアーなどが人気です。ガイドが同行し、その土地の地形の成り立ちや、見られる動植物について解説してくれるプログラムも多く、探検気分を味わいながら自然について学べます。
ホエールウォッチング・イルカウォッチング
クジラやイルカが生息する海域では、彼らの生態を観察するウォッチングツアーが開催されています。これは、ブルーツーリズムとエコツーリズムが融合した代表的な例です。船上から、巨大なザトウクジラが潮を吹く「ブロー」や、豪快なジャンプ「ブリーチ」を目の当たりにした時の感動は、一生の思い出になるでしょう。また、船に並走して泳ぐ野生のイルカの群れとの出会いも、心躍る体験です。ツアーでは、ただ観察するだけでなく、クジラやイルカの生態、彼らを取り巻く環境問題についてガイドが解説を行い、海洋哺乳類への理解と保全意識を高める機会にもなっています。
食文化体験
「旅の楽しみは食にあり」と言われるように、その土地ならではの食文化に触れることは、ブルーツーリズムの大きな魅力です。獲れたての食材を使い、地元の人々と交流しながら楽しむ食体験は、格別の味わいがあります。
魚のさばき方教室
自分で釣ったり、漁業体験で獲ったりした魚を、プロである漁師や民宿のおかみさんから直接教わりながらさばく体験です。スーパーで切り身しか見たことがない人にとっては、魚の構造や内臓の位置など、驚きの連続でしょう。ウロコを取り、三枚におろしていくプロセスは、まさに命をいただくということを実感させてくれます。最初はぎこちなくても、自分でさばいた魚でつくる刺身や海鮮丼の味は、忘れられないものになります。この体験は、魚食文化の継承という点でも重要な役割を果たします。
郷土料理・漁師飯づくり
それぞれの漁村には、代々受け継がれてきた郷土料理や、船の上で手早く作って食べる「漁師飯(りょうしめし)」があります。例えば、新鮮な魚をご飯にのせて熱い出汁をかける「まご茶漬け」や、魚のすり身を焼いた「はんぺん」、なめろうを焼いた「さんが焼き」など、地域色豊かな料理が数多く存在します。地元の女性グループなどと一緒に、会話を楽しみながらこれらの料理を一緒に作ることで、レシピだけでなく、その料理が生まれた背景や文化まで学ぶことができます。
塩づくり体験
海水から塩をつくる体験も、人気のプログラムの一つです。汲み上げた海水を大きな釜で煮詰めたり、太陽と風の力で水分を蒸発させたりして、塩の結晶を取り出します。単純な作業に見えますが、時間と手間がかかることを実感できます。できあがったばかりの塩を舐めてみると、市販の塩とは全く異なる、まろやかでミネラル豊かな味わいに驚くはずです。自分で作った「マイソルト」は、最高のお土産になります。
環境学習
楽しみながら海の環境について学び、保全活動に参加するプログラムも、ブルーツーリズムの重要な柱です。特に、環境意識の高い層や、子どもの教育旅行などで人気を集めています。
サンゴの植え付け・保全活動
地球温暖化による海水温の上昇などで、世界的にサンゴ礁の減少が問題となっています。沖縄などサンゴ礁が豊かな地域では、サンゴの保全活動を組み込んだ観光プログラムが実施されています。陸上で育てられたサンゴの苗を、ダイビングやシュノーケリングで海中に植え付ける体験は、自らの手で海の生態系再生に貢献できる、非常にやりがいのある活動です。サンゴが海の生き物にとってなぜ重要なのか、その生態についてレクチャーを受けることで、環境問題への理解が深まります。
海岸の清掃活動
近年、世界的な問題となっている海洋プラスチックごみ。海岸に打ち上げられたごみを拾うビーチクリーン活動も、手軽に参加できる環境学習プログラムです。ただごみを拾うだけでなく、どのような種類のごみが多いのかを分類・記録することで、問題の根源が私たちの日常生活にあることに気づかされます。流れ着いた漂着物を使ってアート作品を作る「ビーチコーミング・アート」など、楽しみながら取り組める工夫も行われています。これらの活動は、持続可能な観光の実践として、地域と観光客の双方にとって意義深いものです。
日本国内のブルーツーリズムの取り組み事例5選
日本全国の沿岸地域で、その土地ならではの資源を活かしたユニークなブルーツーリズムが展開されています。ここでは、特定の事業者名ではなく、地域として行われている特徴的な取り組みを5つ紹介します。これらの事例は、ブルーツーリズムの多様性と可能性を示しています。
① 【北海道 羅臼町】世界遺産の海での漁業・観光船体験
北海道の東端、知床半島に位置する羅臼町は、世界自然遺産・知床の豊かな海を舞台にしたダイナミックなブルーツーリズムで知られています。ここは、流氷がもたらす豊富な栄養分により、多種多様な海洋生物が集まる世界有数の漁場です。
羅臼でのブルーツーリズムの主役は、野生動物との出会いです。夏にはマッコウクジラやシャチ、ミンククジラ、イシイルカなどが回遊し、冬には国の天然記念物であるオオワシやオジロワシが越冬のために集まります。これらの野生動物を間近で観察できる観光船クルーズは、国内外から多くの観光客を惹きつけています。経験豊富な船長が、動物たちの生態や知床の自然について詳しく解説してくれるため、単なる遊覧に留まらない深い学びが得られます。(参照:知床羅臼町観光協会)
また、羅臼は「羅臼昆布」で有名な昆布漁の拠点でもあります。夏には、早朝から始まる昆布漁の様子を見学できるクルーズも運航されます。漁師たちが長い竿を使って巧みに昆布を採る伝統的な漁法は、まさに職人技です。漁業の現場と、手つかずの雄大な自然が融合した羅臼のブルーツーリズムは、自然の恵みと厳しさ、そしてそれと共に生きる人々の営みを力強く感じさせてくれる、スケールの大きな取り組みと言えるでしょう。
② 【三重県 鳥羽市】海女文化に触れる体験
三重県の鳥羽・志摩地域は、日本を代表する「海女(あま)」の文化が今なお色濃く残る場所です。海女とは、素潜りでアワビやサザエ、海藻などを採る女性のことで、その歴史は数千年前に遡るとも言われています。この地域では、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指すなど、海女文化の保存・継承に力を入れており、ブルーツーリズムがその重要な役割を担っています。
観光客は、「海女小屋」と呼ばれる海女たちが漁の合間に体を温め、休息をとる小屋で、現役の海女さんや元海女さんたちと交流する体験ができます。囲炉裏で焼かれる獲れたての伊勢海老やアワビ、サザエといった海の幸に舌鼓を打ちながら、海女漁の厳しさや喜び、海での不思議な体験談などを直接聞くことができます。この温かいおもてなしとコミュニケーションが、海女文化への深い理解と共感を育みます。(参照:鳥羽市観光協会)
また、海女が身につける「イソノミ」や「タンガ」といった道具に触れたり、海女漁の際に安全を祈願する神社の話を聞いたりと、文化的な側面を深く学べるのも特徴です。ひとつの職業が持つ歴史や信仰、生活様式そのものを観光資源として磨き上げた鳥羽市の取り組みは、文化継承型のブルーツーリズムの優れたモデルケースです。
③ 【福井県 若狭町】常神半島での漁村生活体験
福井県の若狭湾に突き出た常神(つねかみ)半島は、リアス式海岸が織りなす風光明媚な景観と、昔ながらの漁村の風情が残るエリアです。ここでは、「まるごと漁村体験」をコンセプトに、地域全体で観光客を受け入れる体制が整えられています。
中心となるのは、漁家民宿での滞在です。訪れた人々は、民宿を営む漁師の家に宿泊し、家族同然に過ごします。日中は、主人である漁師と一緒に船に乗って定置網漁や釣り、タコかご漁などを体験。夜は、自分たちで獲った魚を含む、若狭湾の新鮮な海の幸を使った家庭料理を囲み、漁のことや地域の暮らしについて語らいます。
この取り組みの特徴は、単発の漁業体験で終わらせるのではなく、漁村の日常にどっぷりと浸かる滞在型プログラムである点です。朝起きてから夜眠るまで、漁村の時間の流れに身を任せることで、都市生活の喧騒を忘れ、心からリフレッシュできます。子どもたちにとっては、魚が食卓に上るまでの過程を学び、自然の恵みに感謝する心を育む絶好の食育の機会となります。(参照:若狭町観光協会) 地域の人々との深い人間関係の構築を重視した常神半島のスタイルは、リピーターを生み出し、地域のファンを育てる「関係人口」創出の成功例と言えます。
④ 【長崎県 五島市】漁家民泊「しま宿」での交流
長崎県の西方に浮かぶ五島列島は、美しい海と数多くの教会群で知られる場所です。この島々では、「泊まる」ことを通じて島の暮らしや人々と深く交流する「民泊」を中心としたブルーツーリズムが盛んです。
特に「漁家民泊(しま宿)」では、漁業を営む家庭に宿泊し、島ならではの時間を過ごすことができます。体験内容は宿によって様々で、釣り船で大物を狙ったり、キビナゴの刺身づくりを教わったり、あるいは特定の体験プログラムはなくとも、食卓を囲んで島の言葉で語り合う時間そのものが貴重な体験となります。五島は魚種の豊富さでも知られ、季節ごとに異なる旬の魚を、最も美味しい食べ方で味わえるのも大きな魅力です。(参照:五島市観光協会)
五島のブルーツーリズムは、「何もしない贅沢」を提供してくれる点に特徴があります。プログラムに追われるのではなく、ただ美しい海を眺めたり、島の人々とゆったりとした会話を楽しんだりする。そうした時間を通じて、訪れた人々は島のファンになり、島との継続的な関わりを持つようになります。観光客を「お客様」としてではなく、「家族」や「友人」のように迎える島民の温かさが、五島のブルーツーリズムの根幹を支えています。
⑤ 【沖縄県 読谷村】サンゴ礁の再生と環境学習
沖縄本島中部に位置する読谷(よみたん)村は、沖縄有数のリゾート地であると同時に、環境保全を核とした先進的なブルーツーリズムを実践している地域です。美しいサンゴ礁は沖縄の海の象徴ですが、近年の環境変化により大きなダメージを受けています。
読谷村では、地域の漁業協同組合が中心となり、サンゴの養殖と植え付け活動を観光プログラムとして提供しています。参加者は、まずサンゴの生態や、サンゴ礁が海の生態系に果たす役割、そして現在直面している危機についてレクチャーを受けます。その後、陸上で育てられたサンゴの苗を、インストラクターの指導のもと、自分たちの手で海の中に植え付けます。
この体験は、単なるレジャーダイビングとは一線を画し、「海の環境再生に自ら貢献する」という強い目的意識と達成感を参加者にもたらします。自分が植えたサンゴが成長し、そこに魚たちが集まる未来を想像することは、環境問題への当事者意識を芽生えさせる強力なきっかけとなります。(参照:読谷村観光情報サイト) 楽しみながら学び、行動する「エデュテインメント(教育+エンターテインメント)」の要素を取り入れた読谷村の取り組みは、観光の力を利用して環境保全の輪を広げる、未来志向のブルーツーリズムの形を示しています。
ブルーツーリズムを始めるための3ステップ
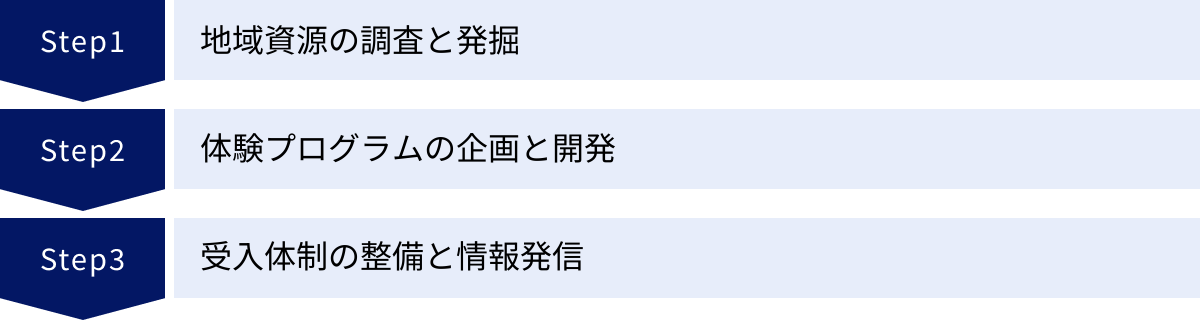
ブルーツーリズムを地域に導入し、成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、地域がブルーツーリズムを立ち上げる際の基本的なプロセスを「調査」「企画」「整備」の3つのステップに分けて解説します。
① 地域資源の調査と発掘
すべての始まりは、自分たちの足元にある「宝物」を見つけることです。地域住民にとって当たり前すぎて見過ごしている日常風景や日常作業の中に、都市部の観光客にとっては新鮮で魅力的な「非日常」が隠されています。このステップでは、先入観を捨て、徹底的に地域資源を洗い出すことが重要です。
- 自然資源の棚卸し:
- 景観:美しい夕日が見える岬、透明度の高い入り江、奇岩が連なる海岸線、歴史を感じさせる漁港の風景など。
- 生態系:どのような魚や貝、海藻が生息しているか。野鳥や海洋哺乳類が観察できるスポットはあるか。干潟や藻場の存在。
- 季節性:季節ごとに海の色や景観はどう変わるか。旬の魚介類は何か。
- 産業・文化資源の棚卸し:
- 漁業:地域に伝わる伝統的な漁法(一本釣り、海女漁など)や、特徴的な養殖業はあるか。漁師が使う独特の道具や船は。
- 食文化:漁師飯、郷土料理、祭りや祝いの席で食べられる特別な料理、水産加工品(干物、塩辛など)のレシピや製法。
- 歴史・文化:地域の成り立ちに関する伝説や物語、神社仏閣、祭りや伝統行事、歴史的な建造物(舟屋、灯台など)。
- 人的資源の棚卸し:
- 「語り部」になれる人は誰か。漁の達人、料理上手なおかみさん、地域の歴史に詳しい長老、祭りの中心人物など。
- 特技を持つ人はいるか。船の操船、魚のさばき方、郷土料理づくり、民謡や踊りなど。
これらの資源をリストアップする際には、地域住民を巻き込んだワークショップを開催するのが効果的です。様々な年代や職業の人が集まり、自分たちの地域の良いところを出し合うことで、予想もしなかった魅力的な資源が発掘されることがあります。また、「よそ者」の視点を取り入れることも重要です。観光の専門家や、地域外から来た移住者、あるいはモニターツアーで訪れた観光客の意見を聞くことで、「内輪の常識」では気づかなかった価値を発見できます。
② 体験プログラムの企画と開発
地域資源の洗い出しができたら、次のステップはそれらを観光客が楽しめる「体験プログラム」という形に組み立てる作業です。単に資源を並べるだけでなく、ストーリー性やターゲット顧客を意識した魅力的な商品として磨き上げる必要があります。
- ターゲット設定:
- 誰に来てほしいのかを明確にします。アクティブな体験を求める若者グループ、子どもの教育を重視するファミリー層、ゆったりとした時間を過ごしたいシニア夫婦など、ターゲットによってプログラムの内容や価格、情報発信の方法は大きく変わります。
- コンセプトとストーリーの構築:
- プログラム全体を貫くテーマや物語を設定します。「伝説の漁師に弟子入りする一日」「失われた海の幸を求めて冒険クルーズ」など、参加者がワクワクするようなコンセプトを考えます。資源を点ではなく線でつなぎ、一連の体験として提供することで、満足度が高まります。
- 具体的な内容の設計:
- プログラム名: 魅力的で分かりやすい名前をつけます。
- 所要時間: 2〜3時間の短時間コース、半日コース、1泊2日の滞在型など、ターゲットのニーズに合わせて設定します。
- 料金: 燃料代、保険料、食材費、人件費などのコストを積み上げ、適正な利益を確保できる価格を設定します。競合となる他のレジャーの価格も参考にします。
- 定員: 安全性や体験の質を考慮し、一度に受け入れられる最大人数と最少催行人数を決めます。
- 準備物: 参加者に用意してもらうもの(着替え、タオルなど)と、こちらで用意するもの(ライフジャケット、長靴、道具一式など)を明確にします。
- 安全対策の組み込み:
- 企画段階から安全管理を最優先に考えます。危険な場所や作業はプログラムから除外する、天候による中止基準を設ける、緊急時の連絡体制を確認するなど、リスクを徹底的に洗い出し、対策を講じます。
開発したプログラムは、まず地域住民や関係者を対象にモニターツアーを実施し、フィードバックを得ることが重要です。時間の配分は適切か、説明は分かりやすいか、料金は妥当か、といった点を実際に体験してもらい、改善を重ねて完成度を高めていきます。
③ 受入体制の整備と情報発信
魅力的なプログラムが完成しても、それをお客様に届け、満足して帰ってもらうための「受け皿」がなければ事業として成り立ちません。最後のステップは、組織づくり、連携、そして情報発信といった事業を円滑に運営するための基盤整備です。
- 運営組織の構築:
- 誰が予約を受け付け、誰が会計を行い、誰が当日のガイドを担当するのか、といった役割分担を明確にします。個人で全てを担うのが難しい場合は、地域の有志でグループを結成したり、漁協や観光協会、NPOなどが事務局機能を担ったりする体制を検討します。
- 地域内連携の強化:
- ブルーツーリズムは、体験プログラム提供者だけで完結するものではありません。宿泊施設、飲食店、交通事業者、土産物店など、地域の様々な事業者と連携することが不可欠です。例えば、体験プログラムと宿泊をセットにしたプランを造成したり、飲食店で使えるクーポンを配布したりと、地域全体で観光客をもてなす「面」での対応を目指します。
- 人材育成:
- ガイドを担当する人材には、接客マナー、安全管理、地域の知識などに関する研修を実施します。お互いのプログラムを見学し合い、良い点や改善点を学び合う機会を設けるのも効果的です。
- 情報発信:
- ターゲット顧客にプログラムの存在を知ってもらうための広報活動を行います。
- Webサイト・SNS: プログラムの魅力が伝わる写真や動画を多用し、詳細な情報や予約方法を掲載します。体験者の声を掲載するのも有効です。
- パンフレット・チラシ: 道の駅や観光案内所、連携する宿泊施設などに設置します。
- プレスリリース: 地元の新聞社やテレビ局に情報を提供し、取材を依頼します。
- 旅行会社との連携: 大手や地域の旅行会社にプログラムを売り込み、ツアー商品に組み込んでもらいます。
これらのステップを着実に踏むことで、地域に根ざした持続可能なブルーツーリズム事業を立ち上げることが可能になります。
ブルーツーリズムの今後の展望
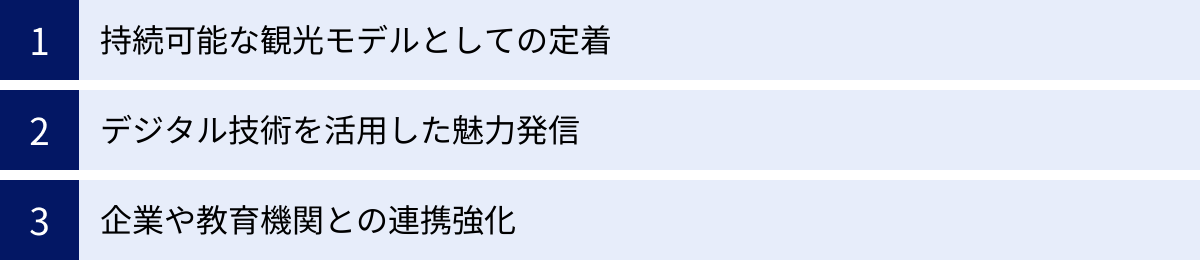
ブルーツーリズムは、まだ発展途上の分野であり、大きな可能性を秘めています。今後、持続可能な観光モデルとして社会に定着していくためには、どのような視点が重要になるのでしょうか。ここでは、3つのキーワード「持続可能性」「デジタル技術」「連携」から、ブルーツーリズムの未来を展望します。
持続可能な観光モデルとしての定着
ブルーツーリズムが単なる一過性のブームで終わらないためには、経済、社会、環境の3つの側面で「持続可能」であることが絶対条件となります。
経済的な持続可能性のためには、前述の通り、安定した収益を確保し、事業として自立できるモデルを構築することが不可欠です。これに加え、観光による収益が、事業者だけでなく地域全体に公平に分配される仕組みが求められます。例えば、売上の一部を地域の環境保全活動や文化継承のための基金として積み立てる、といった取り組みが考えられます。
社会的な持続可能性のためには、地域コミュニティとの共存が鍵となります。観光客の増加が、地域住民の静かな生活を脅かす「観光公害」になってはなりません。受け入れ人数の上限設定や、観光客が立ち入るエリアのルール作りなど、地域住民の合意形成を丁寧に行いながら進める必要があります。観光が、地域住民の誇りや生きがいにつながるような形を目指すべきです。
環境的な持続可能性のためには、ツーリズムの発展と環境保全を両立させることが不可欠です。むしろ、豊かな自然環境こそがブルーツーリズムの最大の資本であるという認識のもと、観光活動そのものが環境保全に貢献する「リジェネラティブ・ツーリズム(環境再生型観光)」へと進化していくことが期待されます。サンゴの植え付けやビーチクリーン活動への参加をプログラムの必須項目にしたり、電気推進船など環境負荷の低い機材を導入したりといった、より積極的な取り組みが広がるでしょう。
デジタル技術を活用した魅力発信
デジタル技術の進化は、ブルーツーリズムの魅力を伝え、体験の質を高める上で強力な武器となります。
まず、情報発信の高度化です。高画質のドローン映像で、上空から見た美しい海岸線や漁のダイナミックな様子を発信すれば、視覚的なインパクトは絶大です。360度カメラやVR(仮想現実)技術を使えば、まるでその場にいるかのような没入感のある「バーチャル漁業体験」を提供でき、実際の訪問への意欲を掻き立てることができます。
次に、体験の質の向上です。AR(拡張現実)技術を活用し、スマートフォンやスマートグラスを海にかざすと、そこに生息する魚の名前や生態が表示される、といったアプリケーションが考えられます。これにより、ガイドがいなくても、参加者はより深く自然について学ぶことができます。また、多言語翻訳アプリを活用すれば、外国人観光客とのコミュニケーションの壁も低くなります。
さらに、関係人口との継続的なつながりにもデジタル技術は有効です。体験後、参加者限定のオンラインコミュニティに招待し、地域の最新情報や旬の魚介類のECサイト(通販サイト)での販売情報などを提供することで、継続的な関係を維持できます。旅が終わった後も、デジタルを通じて地域との接点を持ち続けることができるのです。
企業や教育機関との連携強化
ブルーツーリズムの新たな市場を開拓するためには、一般の観光客だけでなく、企業や教育機関といった組織との連携を強化していくことが重要です。
企業に対しては、社員研修や福利厚生プログラムとしての活用が期待できます。チームで協力して網を引く漁業体験は、チームビルディングに最適です。また、自然の中でリフレッシュすることは、社員のメンタルヘルス向上にもつながります。企業のCSR(社会的責任)活動の一環として、環境保全プログラムに参加してもらうという連携も考えられます。
教育機関に対しては、修学旅行や総合的な学習の時間における体験プログラムとしての価値を訴求できます。ブルーツーリズムは、水産業、環境問題、食育、地域創生など、多くの学習テーマを内包する生きた教材です。子どもたちが漁業の現場に触れ、地域の人々と交流することは、キャリア教育の観点からも非常に有意義です。
これらの組織との連携は、平日の集客を安定させ、事業の収益基盤を強化することにもつながります。企業や学校のニーズを的確に捉え、カスタマイズされたプログラムを提案していく力が、今後のブルーツーリズムの発展には不可欠となるでしょう。
持続可能性を追求し、デジタル技術を賢く活用し、そして多様なパートナーと連携すること。この3つの方向性を見据えることで、ブルーツーリズムは日本の漁村を元気にする、未来への希望の光であり続けることができるはずです。
まとめ
本記事では、「ブルーツーリズム」をテーマに、その定義から注目される背景、メリットと課題、具体的な体験内容、国内外の事例、そして今後の展望まで、多角的に掘り下げてきました。
ブルーツーリズムとは、単に海で遊ぶだけの観光ではありません。それは、漁村という地域に深く入り込み、漁業という「なりわい」、地域に根付く「文化」、そしてそこに暮らす「人々」との交流を通じて、海の恵みと人々の営みの尊さを体感する、学びと感動に満ちた旅のスタイルです。
漁業者の高齢化や地域の過疎化といった深刻な課題への解決策として、また、本物の体験を求める旅行者の新たなニーズに応える形として、そしてSDGsが示す持続可能な社会の実現に貢献するアプローチとして、ブルーツーリズムの重要性はますます高まっています。
地域経済の活性化、漁業への理解促進と後継者育成、そして地域を愛する「関係人口」の創出といった数多くのメリットがある一方で、担い手不足や収益化の難しさ、安全管理、環境負荷といった乗り越えるべき課題も存在します。これらの課題に真摯に向き合い、地域全体で知恵を出し合いながら、持続可能なモデルを構築していくことが成功の鍵となります。
漁業体験からマリンアクティビティ、食文化体験、環境学習まで、ブルーツーリズムが提供する体験は実に様々です。次の休日には、少し足を伸ばして、日本のどこかの海辺の町を訪れてみてはいかがでしょうか。そこにはきっと、スーパーマーケットの鮮魚コーナーでは決して感じることのできない、海と人が織りなす豊かで力強い物語があなたを待っているはずです。