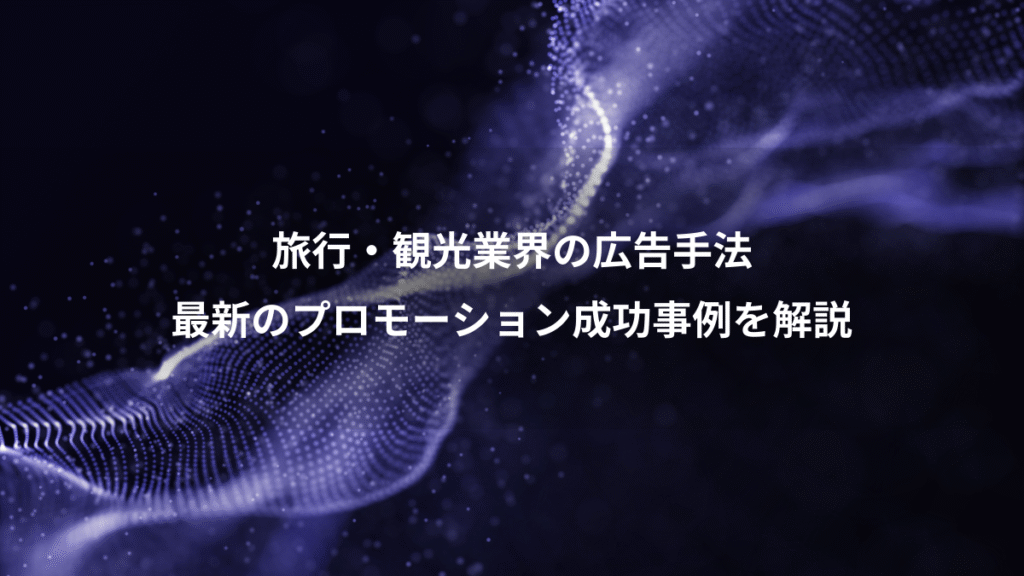旅行・観光業界は、国内外の旅行需要の回復という大きな追い風を受け、活気を取り戻しています。しかし、その一方で競争は激化しており、数ある観光地や宿泊施設、アクティビティの中から自社を選んでもらうためには、戦略的な広告プロモーションが不可欠です。
かつて主流だったパンフレットや雑誌広告といった手法に加え、現代ではスマートフォンの普及に伴い、Web広告やSNS、動画コンテンツなどを活用したデジタルマーケティングの重要性が飛躍的に高まっています。また、消費者の価値観も「モノ消費」から、その場でしか得られない体験を重視する「コト消費」へとシフトしており、広告で伝えるべきメッセージも変化しています。
この記事では、旅行・観光業界を取り巻く最新の動向を踏まえ、効果的な広告手法をオンライン・オフラインに分けて網羅的に解説します。明日から実践できる具体的なプロモーションのポイントから、広告運用をサポートするおすすめの広告代理店まで、貴社の集客とブランディングを成功に導くための知識を詳しくご紹介します。
目次
旅行・観光業界の広告を取り巻く現状
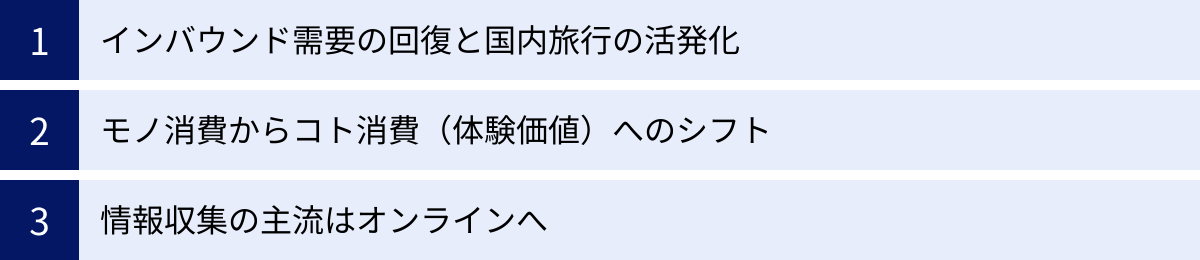
効果的な広告戦略を立てるためには、まず現在の市場環境を正しく理解することが不可欠です。ここでは、旅行・観光業界が直面している3つの大きな変化、「インバウンド需要の回復と国内旅行の活発化」「モノ消費からコト消費へのシフト」「情報収集のオンライン化」について詳しく解説します。
インバウンド需要の回復と国内旅行の活発化
コロナ禍で大きな打撃を受けた旅行・観光業界ですが、現在、急速な回復を見せています。特にインバウンド(訪日外国人旅行)需要の伸びは著しく、広告戦略を考える上で最も重要な要素の一つです。
日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年5月の訪日外客数は304万100人となり、2019年の同月比で9.6%増と、5月として過去最高を記録しました。 これは3ヶ月連続で300万人を超える水準であり、インバウンド市場が完全に回復軌道に乗ったことを示しています。(参照:日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数(2024年5月推計値))
この背景には、水際対策の緩和や、歴史的な円安が海外からの旅行者にとって大きな魅力となっていることがあります。特に、韓国、台湾、中国、香港、米国からの訪日客が多く、これらの国・地域をターゲットとした広告プロモーションの重要性が高まっています。
一方で、国内旅行も活発です。働き方改革による休暇の取得しやすさや、全国各地での魅力的な観光キャンペーンの展開が、国内の旅行意欲を刺激しています。観光庁の「旅行・観光消費動向調査」を見ても、日本人の国内旅行消費額は回復傾向にあり、日本人旅行者をターゲットとした広告も依然として重要です。
このような状況は、観光事業者にとって大きなチャンスであると同時に、厳しい競争に直面していることも意味します。国内外から押し寄せる旅行者の需要をいかにして自社のサービスに取り込むか。そのためには、誰に(ターゲット)、何を(魅力)、どのように(広告手法)伝えるかという、緻密な広告戦略がこれまで以上に求められています。
例えば、インバウンド向けには多言語対応のWebサイトやSNSでの情報発信はもちろん、各国の文化や好みに合わせたコンテンツの提供が必要です。欧米の富裕層にはプライベートな体験や高級感を、アジアからの旅行者にはショッピングやグルメ情報を強調するなど、ターゲットに応じた訴求が効果的です。
国内旅行者向けには、週末や連休に合わせたキャンペーン広告や、まだ知られていない地域の魅力を掘り起こすようなコンテンツマーケティングが有効でしょう。オーバーツーリズム(観光公害)が問題となる一部の有名観光地を避け、地方の魅力を発信することで、新たな顧客層を開拓するチャンスも生まれています。
モノ消費からコト消費(体験価値)へのシフト
現代の旅行者は、単に有名な観光地を訪れたり、ブランド品を買ったりする「モノ消費」から、その土地ならではのユニークな体験や学び、人との交流を求める「コト消費」へと価値観をシフトさせています。
「コト消費」とは、商品やサービスを購入することで得られる「体験」に価値を見出す消費行動のことです。 旅行においては、以下のような体験が「コト消費」の具体例として挙げられます。
- 文化体験: 着物レンタル、茶道体験、伝統工芸(陶芸、染物など)のワークショップ
- アクティビティ: ラフティング、SUP(スタンドアップパドルボード)、星空観賞ツアー
- 食体験: 農家での収穫体験、市場での食べ歩き、ご当地グルメの料理教室
- 学び・交流: 地元のガイドと巡る街歩きツアー、地域のお祭りへの参加
この価値観の変化は、広告で伝えるべきメッセージに大きな影響を与えます。これまでは、ホテルの豪華な設備や景色の美しさといった「モノ」の魅力を中心に訴求するのが一般的でした。しかし、今の旅行者は「その場所で何ができるのか」「どんな特別な体験が待っているのか」という「コト」の情報を求めています。
したがって、広告プロモーションでは、いかにして「体験価値」を臨場感たっぷりに、そして魅力的に伝えるかが成功の鍵を握ります。
例えば、宿泊施設の広告であれば、ただ客室の写真を載せるだけでなく、併設されたスパでのリラクゼーション体験や、地元の食材をふんだんに使った料理をシェフが語る動画などを加えることで、顧客の「泊まってみたい」という気持ちを強く刺激できます。
観光地のプロモーションでは、美しい風景写真に加えて、その場所で楽しんでいる人々の生き生きとした表情を捉えた動画や、ドローンを使ったダイナミックな映像を用いることで、視聴者は自分がそこにいるかのような没入感を得られます。
この「コト消費」へのシフトは、特にSNSとの親和性が非常に高いという特徴があります。感動的な体験や写真映えする体験は、ユーザー自身がInstagramやTikTokなどで発信したくなるため、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)が生まれやすくなります。このUGCは、企業発信の広告よりも信頼性が高い情報として他のユーザーに受け入れられ、自然な形で拡散していくという強力な広告効果を持ちます。
魅力的な「コト」を提供し、それを体験したくなるような広告を展開し、さらに体験した顧客が自発的に情報を発信したくなるような仕掛けを用意すること。 このサイクルを創り出すことが、現代の観光マーケティングにおける王道と言えるでしょう。
情報収集の主流はオンラインへ
旅行の計画から予約、そして現地での情報収集に至るまで、そのプロセスの中心は完全にオンラインへと移行しました。スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも、手軽に旅行情報を検索し、比較検討できるようになっています。
観光庁が発表した「令和5年度 旅行・観光消費動向調査(年次報告)」によると、旅行者が旅行中に利用した情報源として「スマートフォン(インターネット・アプリ)」が突出して高く、多くの年代でトップとなっています。 また、出発前の情報収集においても、「個人のブログ・SNS」や「旅行予約サイト(OTA)」、「宿泊施設や交通機関のホームページ」といったオンライン媒体が上位を占めており、従来の旅行雑誌やパンフレット、テレビ番組などの影響力は相対的に低下しています。(参照:観光庁 令和5年度 旅行・観光消費動向調査 年次報告)
この変化は、広告戦略においてデジタルマーケティングを主軸に据える必要性を明確に示しています。ユーザーが情報を探す「場」がオンラインである以上、企業もその「場」で効果的にアプローチしなければ、そもそも選択肢にすら入ることができません。
具体的には、以下のようなユーザー行動の変化に対応する必要があります。
- 検索エンジンでの情報収集: 「沖縄 2泊3日 モデルコース」「京都 穴場 カフェ」のように、具体的なキーワードで検索するユーザーに対し、自社の情報が検索結果の上位に表示されるためのSEO対策(検索エンジン最適化)が不可欠です。
- SNSでの情報収集: Instagramのハッシュタグ「#箱根旅行」で宿やグルメを探したり、TikTokで旅先のVlog動画を見て行き先を決めたりする若年層が増えています。各SNSの特性に合わせた情報発信や広告展開が求められます。
- マップアプリの活用: 「近くの レストラン」「現在地から 〇〇駅」など、Googleマップをはじめとする地図アプリで情報を探す行動は、特に旅行中において頻繁に行われます。店舗や施設の情報を正確に登録し、口コミ評価を高めるMEO対策(マップエンジン最適化)が、来店を促す上で極めて重要です。
- 口コミ・レビューの重視: OTA(Online Travel Agent)やGoogleマップ、SNS上の口コミは、ユーザーが予約を決定する際の最終的な後押しとなります。良い口コミを増やす努力と同時に、ネガティブな口コミにも真摯に対応する姿勢がブランドの信頼性を左右します。
このように、ユーザーの複雑なオンライン行動(カスタマージャーニー)の各段階で、適切な情報を適切な形で提供できるかどうかが、広告の成果を大きく左右します。 オンラインでの接点をいかに増やし、そこから自社の予約サイトや実店舗へスムーズに誘導できるか、その導線設計が広告戦略の核となるのです。
旅行・観光業界の広告手法7選【オンライン編】
情報収集の主戦場がオンラインである今、デジタル広告を使いこなすことは旅行・観光業界にとって必須のスキルです。ここでは、特に重要度の高い7つのオンライン広告・マーケティング手法について、その仕組みやメリット、具体的な活用方法を詳しく解説します。
① Web広告
Web広告は、インターネット上の様々な媒体に掲載される広告の総称です。ユーザーの行動や属性に応じて多様なアプローチが可能で、旅行・観光業界においても中心的な役割を担います。ここでは代表的な4つのWeb広告を紹介します。
| 広告の種類 | 主なターゲット | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| リスティング広告 | 顕在層(今すぐ客) | 即効性が高い、費用対効果の測定が容易 | 運用ノウハウが必要、クリック単価が高騰しやすい |
| ディスプレイ広告 | 潜在層(これから客) | 視覚的な訴求力、リターゲティングが可能 | コンバージョン率は低め、クリエイティブの質が重要 |
| SNS広告 | 潜在層・顕在層 | 精緻なターゲティング、拡散が期待できる | プラットフォームの理解が必要、炎上リスク |
| ジオターゲティング広告 | 特定エリアのユーザー | 店舗への直接誘導、リアルタイムな訴求 | プライバシーへの配慮、リーチ数が限定的 |
リスティング広告
リスティング広告(検索連動型広告)は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、ユーザーが検索したキーワードに連動して表示されるテキスト形式の広告です。
最大のメリットは、「今、まさに旅行の情報を探している」という購買意欲の非常に高い顕在層に直接アプローチできる点です。 例えば、「箱根 温泉 旅館 個室露天風呂」と検索したユーザーに対して、条件に合致する自社旅館の広告を表示できれば、予約に繋がる可能性は非常に高くなります。
- 活用例:
- 地域名×目的: 「京都 紅葉 ライトアップ」「北海道 スキー場 ファミリー向け」
- イベント名: 「〇〇花火大会 周辺 ホテル」「〇〇フェス 会場 アクセス」
- お悩み・課題: 「子連れ旅行 持ち物」「雨の日 デート 関西」
- 注意点:
人気のキーワードは競合が多く、クリック単価(広告が1回クリックされるごとにかかる費用)が高騰しがちです。そのため、費用対効果を最大化するには、広告文の工夫や、より具体的なニーズを捉えた「スモールワード」(例:「箱根 旅館 記念日 サプライズ」など)を狙う戦略、そしてランディングページ(広告クリック後の遷移先ページ)の最適化といった専門的な運用ノウハウが求められます。
ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像(バナー)や動画形式の広告です。リスティング広告が「探している人」にアプローチするのに対し、ディスプレイ広告は様々なサイトを閲覧している潜在層、つまり「まだ具体的な旅行先は決めていないが、どこかに行きたいな」と考えている層に広くアプローチするのに適しています。
美しい風景写真や、楽しそうなアクティビティの動画など、視覚的なインパクトでユーザーの旅行意欲を掻き立てることができます。また、「リターゲティング」という機能が非常に強力です。これは、一度自社のWebサイトを訪れたものの予約には至らなかったユーザーを追跡し、別のサイトを閲覧中に自社の広告を再度表示させる手法です。これにより、ユーザーに自社のことを思い出してもらい、再検討を促す効果が期待できます。
- 活用例:
- 過去に沖縄のホテルページを見たユーザーに、沖縄の絶景写真を使ったバナー広告を表示する。
- 旅行関連のニュースサイトやブログに、季節のおすすめツアーの動画広告を配信する。
- 注意点:
関連性の低いサイトに表示されると無視されやすいため、どのようなユーザー層の、どのようなサイトに配信するかのターゲティング設定が重要です。クリエイティブ(バナーや動画)の質がクリック率を大きく左右するため、A/Bテストを繰り返して効果の高いデザインを見つける必要があります。
SNS広告
Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokといったSNSプラットフォームに配信する広告です。SNS広告の最大の強みは、ユーザーが登録したプロフィール情報(年齢、性別、居住地など)や、興味・関心(「旅行」「グルメ」「アウトドア」など)に基づいた精緻なターゲティングが可能な点です。
特に、ビジュアルが重視される旅行・観光コンテンツはInstagramやTikTokとの相性が抜群です。息をのむような絶景動画や、シズル感あふれるグルメ写真などは、ユーザーの「いいね!」や「シェア」を誘発しやすく、広告費を払って表示される範囲を超えて情報が拡散される可能性があります。
- 活用例:
- Instagramストーリーズで、縦長の動画広告を配信し、スワイプアップで予約サイトに誘導する。
- Facebookで、過去に自社のツアーに参加した顧客と類似した行動特性を持つユーザー層(類似オーディエンス)に広告を配信する。
- TikTokで、流行りの音楽に合わせたダンスやチャレンジ企画で地域の魅力をアピールする。
- 注意点:
各SNSのユーザー層や文化が異なるため、プラットフォームの特性を理解した上で広告クリエイティブを作成する必要があります。また、広告色が強すぎるとユーザーに敬遠される傾向があるため、いかに自然な形でコンテンツに溶け込ませるかが腕の見せ所です。
ジオターゲティング広告
ジオターゲティング広告は、スマートフォンのGPSなどの位置情報を活用し、「今、特定のエリアにいる人」や「過去に特定のエリアにいた人」をターゲットに広告を配信する手法です。
店舗や施設への直接的な集客(来店促進)に絶大な効果を発揮します。例えば、自社のレストランの近くを歩いている人にランチのクーポン広告を配信したり、空港に到着した訪日観光客に、市内へ向かうバスの案内広告を表示したりといった活用が可能です。
さらに、競合のホテルや観光施設の周辺にいるユーザーに自社の広告を配信し、顧客を奪うといった攻撃的な使い方も可能です。
- 活用例:
- スキー場の近隣エリアにいるユーザーに対し、リフト券の割引情報をプッシュ通知で配信する。
- 大規模イベントの開催日に、会場周辺にいるユーザーに周辺の飲食店情報や宿泊施設の空室情報を配信する。
- 注意点:
位置情報の利用にはユーザーの許諾が必要であり、プライバシーへの配慮が不可欠です。また、ターゲティングエリアを絞りすぎると広告の配信対象者が少なくなり、十分なリーチを確保できない場合があります。
② SEO対策(検索エンジン最適化)
SEO(Search Engine Optimization)とは、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトが検索結果の上位に表示されるように行う一連の施策のことです。広告費を払って上位表示させるリスティング広告とは異なり、良質なコンテンツを作成・最適化することで、無料で継続的なアクセスを獲得することを目指します。
旅行・観光業界においてSEOは極めて重要です。なぜなら、多くの旅行者は「〇〇(地名) おすすめ 観光」「〇〇(アクティビティ) コツ」といった形で、能動的に情報を探しているからです。こうした検索意図に応える質の高い記事(コンテンツ)を自社のブログやオウンドメディアで提供できれば、広告費をかけずに多くの見込み客を集客し続けることができます。
- メリット:
- 資産性: 一度上位表示されれば、中長期的に安定した集客効果が見込める。
- 費用対効果: 広告費が不要なため、CPA(顧客獲得単価)を大幅に下げられる可能性がある。
- ブランディング: 有益な情報を提供することで、その分野の専門家としての信頼性や権威性が高まる。
- 具体的な施策:
- キーワード選定: ターゲットユーザーがどのような言葉で検索するかを調査・選定する。
- コンテンツ作成: 選定したキーワードの検索意図を満たす、網羅的で質の高い記事を作成する。
- 内部対策: サイト構造を分かりやすくしたり、表示速度を改善したりして、検索エンジンがクロールしやすいサイトを作る。
- 外部対策: 他の信頼性の高いサイトからリンク(被リンク)を獲得する。
- 注意点:
SEOは効果が現れるまでに数ヶ月から1年以上の時間がかかることも珍しくありません。また、Googleの検索アルゴリズムは常に変動しているため、継続的な情報収集と改善努力が必要です。専門的な知識が求められるため、自社での対応が難しい場合は専門業者への依頼も視野に入れましょう。
③ MEO対策(マップエンジン最適化)
MEO(Map Engine Optimization)は、主にGoogleマップを対象とした地図エンジン最適化のことです。「ローカルSEO」とも呼ばれ、「地域名+業種名」(例:「渋谷 レストラン」「新宿 ホテル」)などで検索された際に、自社の店舗や施設情報をマップ検索結果の上位に表示させるための施策です。
スマートフォンを持って街を歩きながら「近くのカフェ」を探すといった行動が一般的になった現在、ホテル、旅館、飲食店、観光施設など、実店舗を持つビジネスにとってMEOは死活問題と言えるほど重要性を増しています。
MEOの核となるのが「Googleビジネスプロフィール」の活用です。これは、Google検索やGoogleマップ上に自社のビジネス情報を無料で掲載できるツールです。
- メリット:
- 来店促進: マップ上に表示されることで、ユーザーの来店や電話での問い合わせ、予約に直接繋がりやすい。
- 高い費用対効果: 基本的に無料で実施でき、かつ購買意欲の高いユーザーにアプローチできる。
- 信頼性向上: 正確な情報や多くの好意的な口コミは、ユーザーに安心感を与える。
- 具体的な施策:
- 情報の充実: Googleビジネスプロフィールに、店名、住所、電話番号、営業時間、WebサイトURLなどの基本情報を正確に登録する。
- 写真の追加: 外観、内観、商品、メニュー、スタッフなど、魅力的で最新の写真を数多く登録する。
- 口コミの管理: 投稿された口コミには、良い内容にも悪い内容にも丁寧に返信する。利用者には口コミの投稿を積極的に依頼する。
- 最新情報の投稿: 「投稿」機能を活用し、新メニューやイベント、キャンペーン情報などを定期的に発信する。
- 注意点:
ネガティブな口コミも表示されてしまうため、日々の丁寧な顧客対応が口コミ評価に直結します。また、情報の鮮度も評価に影響するため、営業時間や休業日などの情報は常に最新の状態に保つ必要があります。
④ SNSマーケティング
SNSマーケティングとは、SNS広告とは異なり、自社の公式アカウント(Facebook、Instagram、X、TikTokなど)を運用して、ユーザーと直接コミュニケーションを取りながらファンを増やし、最終的に自社のサービス利用に繋げる活動全般を指します。
最大の目的は、一方的な情報発信ではなく、ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じて「エンゲージメント(愛着や絆)」を深め、強力なファンコミュニティを形成することです。
- メリット:
- ファン育成・ブランディング: 企業の「中の人」の個性や想いを伝えることで、親近感や共感を醸成し、ファンを育てることができる。
- リアルタイムな情報発信: イベントの告知や施設の混雑状況、天候による影響など、最新情報を迅速に伝えられる。
- UGCの創出: ユーザー参加型のキャンペーン(フォトコンテストなど)を実施することで、自社に関する投稿(UGC)を増やし、自然な口コミ拡散を狙える。
- 具体的な施策:
- プラットフォームの選定: 自社のターゲット層が多く利用しているSNSを選ぶ。ビジュアル重視ならInstagram、若年層向けならTikTok、リアルタイムな情報発信ならXなど。
- コンテンツ戦略: ターゲットが興味を持つであろうコンテンツを企画・投稿する(例:地域の絶景写真、舞台裏の紹介、スタッフのおすすめ情報、旅行の豆知識など)。
- コミュニケーション: ユーザーからのコメントやDMには丁寧に返信する。ハッシュタグで自社について投稿してくれたユーザーにお礼を言うなど、積極的な交流を心がける。
- 注意点:
成果が出るまでには地道で継続的な運用が必要です。すぐにフォロワーが増えなくても諦めずに続ける忍耐力が求められます。また、不適切な投稿や対応は「炎上」に繋がるリスクがあるため、運用ルールやガイドラインを定めておくことが重要です。
⑤ 動画マーケティング
YouTubeやTikTok、Instagramリールなどの動画プラットフォームを活用して、旅行の魅力を伝えるマーケティング手法です。写真やテキストだけでは伝えきれない現地の雰囲気、スケール感、体験の楽しさといった「空気感」を、映像と音で臨場感たっぷりに伝えられるのが最大の強みです。
特に、前述の「コト消費」の魅力を伝える上で、動画は最強のツールと言えます。ラフティングの激しい水しぶき、満点の星空の美しさ、料理から立ち上る湯気など、五感に訴えかける映像は、ユーザーの「行ってみたい」「体験してみたい」という感情を強く揺さぶります。
- メリット:
- 情報伝達力: 短時間で多くの情報を伝えることができ、ユーザーの記憶に残りやすい。
- 感情への訴求: ストーリー性を持たせることで、共感や感動を生み出しやすい。
- 汎用性: 作成した動画は、自社サイト、SNS、Web広告、デジタルサイネージなど、様々な媒体で活用できる。
- 具体的なコンテンツ例:
- プロモーションビデオ: ドローンなどを活用し、観光地や施設の魅力を凝縮した映像。
- Vlog(ビデオブログ): スタッフやインフルエンサーが実際に旅行やアクティビティを体験する様子を記録したドキュメンタリー風の動画。
- ハウツー・TIPS動画: 「〇〇(アクティビティ)の上手なやり方」「旅のパッキング術」など、ユーザーの役に立つ情報を提供する動画。
- インタビュー動画: 旅館の女将やシェフ、地元の職人など、「人」にフォーカスし、その想いやこだわりを伝える動画。
- 注意点:
クオリティの高い動画を制作するには、企画、撮影、編集に専門的なスキルと機材、そしてコストがかかります。必ずしもプロ仕様の機材が必要なわけではありませんが、視聴者がストレスを感じない程度の画質や音質、テンポの良い編集は最低限求められます。
⑥ インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングとは、特定のコミュニティにおいて強い影響力を持つ「インフルエンサー」(YouTuber、インスタグラマー、ブロガーなど)に自社のサービスや商品を体験してもらい、その感想や魅力を自身のSNSやブログで発信してもらうマーケティング手法です。
企業が発信する広告に比べて、消費者目線に近い第三者からの情報であるため、ユーザーに受け入れられやすく、高い信頼性と説得力を持つのが特徴です。
- メリット:
- ターゲットへの的確なリーチ: インフルエンサーのフォロワーは、その人の発信する情報(例:旅行、グルメ、ファッション)に興味を持つ層で構成されているため、自社のターゲット層と合致するインフルエンサーを起用することで、効率的にアプローチできる。
- 信頼性の高い口コミ効果: ファンにとってインフルエンサーは憧れの存在であり、その人が「おすすめ」するものは強い訴求力を持つ。
- 質の高いコンテンツ: プロのインフルエンサーが作成する写真や動画はクオリティが高く、企業の二次利用(広告素材としての利用など)が可能な場合もある。
- インフルエンサーの選び方:
単にフォロワー数が多いだけでなく、エンゲージメント率(投稿に対する「いいね」やコメントの割合)が高いか、フォロワー層が自社のターゲットと合っているか、過去の投稿内容が自社のブランドイメージと合致しているか、などを総合的に判断する必要があります。 - 注意点:
ステルスマーケティング(広告であることを隠して宣伝すること)は景品表示法で禁止されています。インフルエンサーに依頼する場合は、必ず「#PR」「#広告」「#タイアップ」といった表記を付けてもらい、広告であることを明示する必要があります。また、インフルエンサーの選定や依頼、効果測定にはノウハウが必要なため、専門のキャスティング会社を利用するのも一つの手です。
⑦ コンテンツマーケティング(オウンドメディア運用)
コンテンツマーケティングとは、前述のSEOとも密接に関連しますが、より広範な概念です。ターゲットユーザーにとって価値のある、有益なコンテンツ(ブログ記事、導入事例、ホワイトペーパー、動画など)を自社で制作・発信(オウンドメディア運用)し続けることで、潜在的な見込み客との接点を作り、時間をかけて信頼関係を構築し、最終的にファンになってもらうことを目指すマーケティング戦略です。
単に商品を売り込むのではなく、まずユーザーの抱える疑問や悩みを解決する情報を提供することから始めます。
- メリット:
- 潜在層へのアプローチ: 「まだ旅行の予定はないが、いつか行ってみたい」と考えている層に、有益な情報提供を通じて自社の存在を認知させることができる。
- 専門性の確立: 質の高い情報を発信し続けることで、「この地域の旅行のことなら、このサイトが一番詳しい」という専門家としてのポジションを築ける。
- 長期的な資産形成: 作成したコンテンツはWebサイト上に蓄積され、企業の永続的な資産となる。
- コンテンツの具体例:
- ノウハウ系: 「初めてのひとり旅!準備と注意点完全ガイド」「子連れ旅行を120%楽しむための持ち物リスト」
- まとめ系: 「〇〇エリアのおすすめ日帰り温泉10選」「〇〇駅で買える人気お土産ランキング」
- 深掘り系: 「知られざる〇〇城の歴史秘話」「地元民しか知らない絶景ハイキングコース」
- 注意点:
コンテンツマーケティングは、短期的な成果を求める手法ではありません。コンテンツの企画、執筆、効果測定、リライト(改善)というサイクルを地道に回し続けるための体制とリソースが必要です。成果が出るまで時間がかかることを理解し、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵です。
旅行・観光業界で活用したいオフライン広告
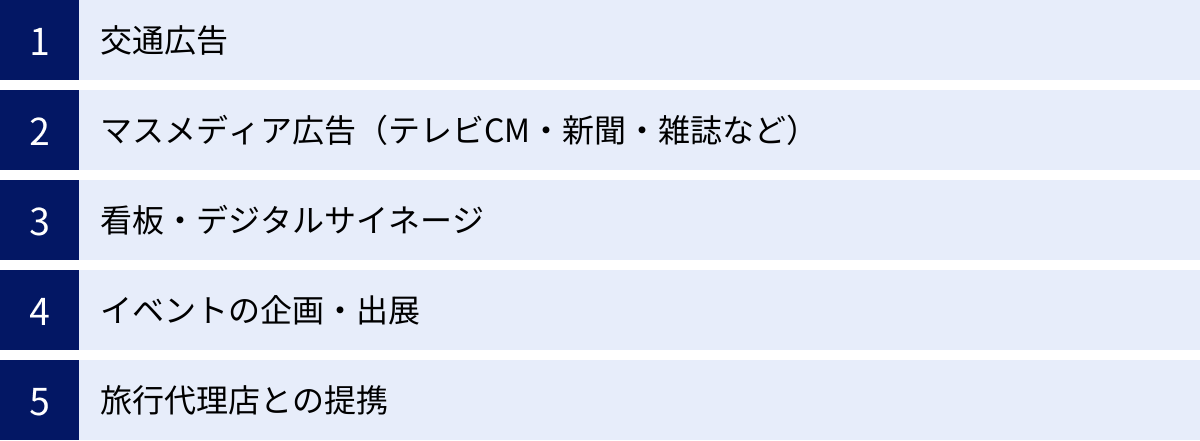
デジタルマーケティングが主流となる中でも、オフライン広告(インターネットを介さない広告)が持つ独自の価値は依然として健在です。特に、オンライン施策と連携させることで、その効果を最大化できます。ここでは、旅行・観光業界で有効な5つのオフライン広告手法を紹介します。
交通広告
交通広告は、電車、バス、タクシー、駅、空港など、公共交通機関やその関連施設に掲出される広告です。特定のエリアを日常的に利用する人や、まさに今移動中の旅行者に対して、反復的にアピールできるのが大きな特徴です。
- 種類と活用例:
- 中吊り広告・窓上広告(電車): 通勤・通学で利用する層に繰り返し訴求できる。観光地へ向かう路線の場合は、旅行者の期待感を高めるようなクリエイティブが効果的です。
- 駅ポスター・駅看板: 駅を利用する不特定多数の人々の目に留まる。QRコードを掲載してWebサイトへ誘導するなど、オンラインとの連携がしやすいです。
- ラッピングバス・バス車内広告: 特定の路線を走行するため、地域住民への刷り込み効果が高い。観光地を巡る周遊バスであれば、観光客への直接的なアピールになります。
- タクシー広告: 車内のタブレットで動画広告を流すタイプが主流。ビジネス層や富裕層へのアプローチに適しています。
- メリット:
- エリアターゲティング: 特定の沿線や地域にターゲットを絞って広告を展開できる。
- 反復訴求効果: 日常生活の動線上で繰り返し接触することで、無意識のうちにブランド名やメッセージを記憶させることができる(ザイオンス効果)。
- 注意点:
Web広告のように詳細な効果測定(クリック数など)を行うのは難しいです。また、広告のデザイン制作から掲出までに時間がかかるため、スピーディーな情報発信には向きません。
マスメディア広告(テレビCM・新聞・雑誌など)
テレビ、新聞、雑誌、ラジオといった、いわゆる「マスメディア」への広告出稿です。広範囲の不特定多数の人々に対して、一気に情報を届けられるリーチ力と、メディア自体が持つ高い信頼性が最大の武器です。
- 種類と活用例:
- テレビCM: 映像と音で強いインパクトを与え、ブランドの認知度やイメージを飛躍的に高める効果がある。全国的な知名度を持つ観光地や大手旅行会社、航空会社などが活用します。
- 新聞広告: 社会的な信頼性が高く、特にシニア層へのリーチに強い媒体です。シニア向けのバスツアーや、落ち着いた旅行プランの広告と相性が良いです。
- 雑誌広告: 「旅行」「グルメ」「アウトドア」など、特定の趣味・関心を持つ読者にターゲットを絞ってアプローチできます。旅行専門誌への出稿は、意欲の高い読者に直接情報を届けられるため非常に効果的です。
- メリット:
- 圧倒的なリーチ力と認知度向上: 短期間で多くの人にブランドを知ってもらうことができる。
- 高い信頼性: マスメディアに広告が掲載されていること自体が、企業の信頼性の証となる。
- 注意点:
他の広告手法に比べて費用が非常に高額になるため、体力のある大企業向けの施策と言えます。また、効果測定が難しく、費用対効果を厳密に検証しにくいという側面もあります。
看板・デジタルサイネージ
看板広告は、屋外の特定の場所に設置され、その場所を通る人々に向けた広告です。近年では、静止画だけでなく動画も表示できるデジタルサイネージ(電子看板)の活用が急速に進んでいます。
特定のロケーションに紐づいたメッセージを発信し、その場にいる人々の行動を喚起するのに適しています。
- 種類と活用例:
- 屋外看板: 高速道路沿いや、観光地の入り口、繁華街のビルなどに設置される。地域のランドマークとして、長期間にわたり認知を高める効果があります。
- デジタルサイネージ: 駅の構内、空港、ショッピングモール、大型ビジョンのある交差点などに設置される。時間帯や天候に応じて表示コンテンツを切り替えられるため、タイムリーな情報発信が可能です。例えば、空港の到着ロビーで、フライト情報に合わせて多言語で歓迎メッセージや交通案内を表示するといった活用が考えられます。
- メリット:
- ロケーションの優位性: 狙った場所で、24時間365日(稼働時間内)、継続的に情報を発信し続けることができる。
- 視認性の高さ: 特に大型の看板や、動きのあるデジタルサイネージは人々の注意を惹きつけやすい。
- 注意点:
設置できる場所が限られており、人気のロケーションはコストも高くなります。また、通行人は一瞬しか広告を見ないため、シンプルで分かりやすいメッセージとデザインが求められます。
イベントの企画・出展
物産展や観光PRイベント、旅行博覧会への出展など、見込み客と直接顔を合わせてコミュニケーションを取ることができる手法です。商品やサービスを実際に体験してもらうことで、その魅力を深く理解してもらい、熱量の高いファンを獲得する機会となります。
- 種類と活用例:
- 旅行博への出展: 国内外の旅行会社や自治体が一堂に会するイベント。旅行に関心の高い来場者に対し、パンフレット配布や相談会、VRによる現地体験などを通じて直接アピールできます。
- 物産展・観光PRイベント: 都市部の百貨店やイベントスペースで開催。特産品の試食・販売や、伝統芸能の披露などを通じて、地域の魅力を五感で感じてもらうことができます。
- 自社主催の体験イベント: ワークショップやセミナーなどを開催し、見込み客との関係性を深める。
- メリット:
- 直接的なコミュニケーション: 顧客の生の声を聞くことができ、ニーズや疑問にその場で応えられる。
- 体験の提供: 商品やサービスを実際に試してもらうことで、オンラインでは伝えきれない価値を実感してもらえる。
- メディア露出: ユニークなイベントは、テレビや新聞などのメディアに取り上げられ、ニュースとして報道される可能性もある。
- 注意点:
企画から準備、当日の運営まで、多くの手間とコストがかかります。また、集客が天候や他のイベントの状況に左右されるリスクもあります。イベントで獲得した見込み客の連絡先をリスト化し、後日メールマガジンなどでフォローアップするなど、オンライン施策と連携させて効果を最大化することが重要です。
旅行代理店との提携
JTBやHISといった大手から、地域に密着した中小の旅行代理店まで、彼らの持つ販売チャネルや顧客基盤を活用させてもらう、古くからある強力なオフライン施策です。
特に、自分での情報収集やオンライン予約が苦手なシニア層や、団体旅行などをターゲットとする場合に非常に有効です。
- 提携の形態:
- パンフレット設置: 店頭のラックに自社のパンフレットを置いてもらう。
- 共同でのツアー造成: 旅行代理店の商品企画担当者と協力し、自社の施設やアクティビティを組み込んだオリジナルツアーを作ってもらう。
- 販売研修: 代理店の販売スタッフ向けに研修会を開き、自社の魅力やセールスポイントを深く理解してもらう。
- メリット:
- 販売網の活用: 自社だけではアプローチできない広範な顧客層にリーチできる。
- プロによる販売: 旅行のプロである販売スタッフが、顧客のニーズに合わせて自社の商品を推薦してくれるため、成約率が高い。
- 注意点:
ツアーに組み込んでもらったり、販売してもらったりする際には、販売手数料(コミッション)が発生します。また、価格や販売方法などが代理店の意向に左右される場合があり、自社でのブランドコントロールが難しくなる側面もあります。どの代理店と、どのような条件で提携するかが重要になります。
旅行・観光の広告効果を高める3つのポイント
これまで様々な広告手法を紹介してきましたが、それらをやみくもに実施するだけでは十分な成果は得られません。広告効果を最大化するためには、戦略的な視点が必要です。ここでは、特に重要な3つのポイントについて深掘りします。
① ターゲット層を具体的に設定する
広告戦略を立てる上で、すべての起点となるのが「誰に伝えたいのか」を明確にすること、すなわちターゲット設定です。ターゲットが曖昧なままでは、広告メッセージは誰の心にも響かず、貴重な予算を無駄にしてしまいます。「万人受け」を狙った広告は、結果的に「誰にも刺さらない」広告になりがちです。
ターゲット設定で有効な手法が「ペルソナ」の作成です。ペルソナとは、自社の商品やサービスにとって最も重要で象徴的な顧客像を、架空の人物として具体的に設定するマーケティングの手法です。
- ペルソナ設定の項目例:
- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成
- ライフスタイル: 趣味、価値観、休日の過ごし方、よく見るメディア
- 旅行に関する行動: 旅行の頻度、予算、誰と行くか、情報収集の方法、予約方法、旅行に求めるもの(癒やし、刺激、学びなど)
【ペルソナ設定の具体例】
| 項目 | ペルソナA:アクティブな若者グループ向け | ペルソナB:記念日を祝うカップル向け | ペルソナC:三世代ファミリー向け |
|---|---|---|---|
| 人物像 | 24歳、都内在住の会社員、佐藤美咲さん | 32歳、都内IT企業勤務、高橋健一さん | 45歳、主婦、田中良子さん |
| 旅行の目的 | 友人と3人で週末リフレッシュ旅行 | 彼女との3年記念日をお祝いする特別な旅行 | 両親の古希祝いを兼ねた家族旅行 |
| 情報収集 | Instagram、TikTok、旅行系Webメディア | 一休.com、OZmall、グルメサイトのレビュー | 旅行代理店のパンフレット、Yahoo!検索 |
| 重視する点 | 写真映え、非日常感、アクティビティ | プライベート感、高級感、サプライズ演出 | バリアフリー、個室での食事、子供向け設備 |
| 予算(1泊) | 1人2万円〜3万円 | 1人5万円〜8万円 | 1人3万円〜4万円 |
| 有効な広告 | SNS広告、インフルエンサーマーケティング | リスティング広告、雑誌広告(高級志向) | MEO対策、新聞広告、旅行代理店提携 |
このようにペルソナを具体的に設定することで、チーム内での顧客イメージが統一され、「この人(ペルソナ)なら、どんな言葉が心に響くだろうか?」「この人は、どんな媒体で情報を集めるだろうか?」といった具体的な議論ができるようになります。
例えば、ペルソナAの佐藤さんには、Instagramで「#週末旅行」「#女子旅」といったハッシュタグを付けた、写真映えする体験アクティビティの広告を見せるのが効果的でしょう。一方、ペルソナCの田中さんには、Googleマップで「バリアフリーの宿」と検索した際に自社の情報が上位に表示されるMEO対策や、旅行代理店のカウンターで「三世代で楽しめるプラン」として推薦してもらうのが有効です。
このように、ターゲットを具体的に絞り込むことで、訴求すべきメッセージ、最適な広告媒体、そして投下すべき予算の配分が自ずと明確になります。 これが、広告効果を高めるための最も重要な第一歩です。
② オンラインとオフラインの施策を連携させる
現代の消費者は、一つの媒体だけで情報を完結させることはほとんどありません。スマートフォンの画面(オンライン)と現実世界(オフライン)を自由に行き来しながら、情報を収集し、購買を決定します。この複雑な消費者行動に対応するためには、オンライン広告とオフライン広告を個別の施策として捉えるのではなく、相互に連携させて相乗効果を生み出す「O2O(Online to Offline)」や「OMO(Online Merges with Offline)」の視点が不可欠です。
O2Oは、オンラインからオフラインへ顧客を誘導する流れを指します。例えば、Webサイトで割引クーポンを発行し、実店舗への来店を促すのが典型的な例です。一方、OMOはオンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客データを統合して一人ひとりに最適化された一貫した体験を提供しようとする考え方です。
【オンラインとオフラインの連携 具体策】
- オフラインからオンラインへ
- QRコードの活用: 電車の車内広告や、観光地のパンフレット、店舗のメニューなどにQRコードを印刷しておきます。ユーザーがスマートフォンで読み取ると、より詳細な情報が掲載されたWebサイトや、多言語対応の解説ページ、予約フォーム、SNSの公式アカウントなどに誘導できます。これにより、オフライン広告で興味を持ったユーザーを、コンバージョン(予約など)に近いオンラインの接点へとスムーズに繋ぐことができます。
- ハッシュタグの告知: イベント会場や店舗内に、「#〇〇旅館の思い出」といったオリジナルのハッシュタグを掲示します。来場者にSNS投稿を促すことで、オフラインでの体験がオンライン上のUGC(口コミ)へと変換され、情報が拡散していきます。
- オンラインからオフラインへ
- Web広告でのイベント告知: SNS広告やリスティング広告で、期間限定の物産展や体験イベントの情報を発信し、実際の会場への来場を促進します。
- ジオターゲティング広告の活用: 観光地周辺にいるユーザーのスマートフォンに、近隣の実店舗で使えるクーポンや、これから始まるイベントの情報を配信し、リアルタイムに来店・来場を促します。
- オンライン予約→オフライン体験: Webサイトで予約した顧客情報をもとに、当日の受付をスムーズにしたり、過去の利用履歴に基づいて特別な「おもてなし」を提供したりします。
これらの施策を組み合わせることで、顧客のカスタマージャーニー(認知から検討、予約、体験、共有までの道のり)全体にわたって、切れ目のないアプローチが可能になります。重要なのは、各広告媒体が持つ役割を明確にし、顧客が次のステップに進みやすいような「橋渡し」を設計することです。 この連携がうまく機能すれば、顧客満足度の向上と広告効果の最大化の両方を実現できます。
③ 魅力的な体験価値を伝え、口コミを促す
「モノ消費からコト消費へ」のセクションでも触れた通り、現代の旅行者は「そこでしかできない体験」に価値を見出しています。したがって、広告で伝えるべきは、単なるスペックや価格ではなく、顧客がそのサービスを利用することで得られる「感情的な便益(ベネフィット)」や「感動的な体験価値」です。
そして、その体験価値を最も効果的に伝えるのは、企業からの一方的な宣伝文句ではなく、実際に体験した他の顧客による「本音の口コミ(UGC)」です。広告の最終ゴールは、広告をきっかけに訪れた顧客に最高の体験を提供し、その感動が新たな口コミを生み、その口コミが次のお客様を呼ぶ、という好循環を創り出すことにあります。
【体験価値を魅力的に伝える方法】
- ストーリーテリング: 商品やサービスの背景にある物語を語ることで、顧客の感情に訴えかけます。
- (悪い例)「地元の食材を使った料理です」
- (良い例)「このお魚は、毎朝〇〇漁港で船長の田中さんが水揚げしたものを、料理長が自ら目利きして仕入れています。野菜は、隣町の鈴木さんが無農薬で育てた旬のものだけを使いました。」
- 五感に訴える表現: 映像や言葉で、顧客がその場にいるかのような感覚を呼び起こします。
- (例)「パチパチと音を立てる暖炉の炎」「焼きたてのパンの香ばしい匂い」「鳥のさえずりしか聞こえない静寂の森」
- 「人」にフォーカスする: サービスの提供者であるスタッフの顔や想いを見せることで、親近感や信頼感を醸成します。旅館の女将、ホテルのコンシェルジュ、アクティビティのガイドなどが主役のコンテンツは、温かみがあり共感を呼びやすいです。
【口コミ(UGC)を促すための仕掛け】
- フォトジェニックな環境づくり: 思わず写真を撮って誰かにシェアしたくなるような場所やモノを用意します。美しい景色を望むテラス、ユニークなデザインの客室、見た目にも華やかな料理やデザート、おしゃれな看板などが挙げられます。
- ハッシュタグキャンペーン: 特定のハッシュタグ(例:「#〇〇で夏休み」)を付けて投稿してくれた人の中から、抽選で宿泊券などをプレゼントするキャンペーンを実施します。これにより、楽しみながらUGCを増やせます。
- 直接的な依頼: 満足度の高そうな顧客に対して、チェックアウト時やアンケートで「もしよろしければ、Googleマップや予約サイトへの口コミ投稿をお願いします」と丁寧にお願いすることも有効です。その場で投稿できるQRコードを用意しておくと、さらにハードルが下がります。
- 口コミへの丁寧な返信: 投稿された口コミには、一つひとつ丁寧に返信します。感謝の気持ちを伝えたり、指摘された点を改善する姿勢を見せたりすることで、他のユーザーへの印象も良くなります。
広告はあくまで顧客との最初の接点です。その後の体験が期待外れであれば、二度と利用してもらえないばかりか、ネガティブな口コミが広がるリスクさえあります。最高の広告とは、最高の顧客体験そのものであるという意識を持ち、サービス品質の向上と、その魅力を伝える努力、そして感動を共有してもらうための仕組みづくりを三位一体で進めていくことが、持続的な成功への唯一の道です。
旅行・観光業界の広告に強いおすすめ広告代理店3選
自社で広告を運用するリソースやノウハウがない場合、専門の広告代理店に依頼するのも有効な選択肢です。旅行・観光業界のプロモーションには特有の知見が求められるため、この分野に強みを持つ代理店を選ぶことが成功の鍵となります。ここでは、それぞれ異なる強みを持つ代表的な3社を紹介します。
① 株式会社ジェイアール東日本企画(jeki)
株式会社ジェイアール東日本企画(通称:jeki)は、JR東日本グループのハウスエージェンシー(特定の企業グループを専門に扱う広告代理店)です。その出自から、交通広告、特にJR東日本が保有する駅や車両といった膨大なメディア資産を活用したプロモーションに圧倒的な強みを持っています。
- 強み・特徴:
- 交通メディアの網羅性: 首都圏をはじめとするJR東日本エリアの駅構内ポスター、デジタルサイネージ、電車内の中吊り広告やトレインチャンネル(車内ビジョン)など、多様な交通メディアを駆使した広告展開が可能です。これにより、沿線の住民やビジネスパーソン、旅行者など、特定のエリアを移動する人々へ集中的かつ反復的にアプローチできます。
- 「移動者データ」の活用: jekiは独自の「jeki移動者調査」を実施しており、交通機関利用者の属性や行動、意識に関する深い知見を蓄積しています。さらに、Suicaの利用履歴データを個人が特定できない形で統計的に分析し、マーケティングに活用するサービスも提供しています。 これにより、「どの駅から乗ってどの駅で降りたか」「どの店舗で購買したか」といったリアルな移動・購買データに基づいた、精度の高いターゲティングや広告効果の可視化が可能です。(参照:株式会社ジェイアール東日本企画 公式サイト)
- 総合的なソリューション: 交通広告だけでなく、マス広告、デジタルマーケティング、イベントの企画・運営まで、幅広い領域をカバーしています。交通広告を起点としながら、Web広告やSNS施策を連携させるといった、統合的なコミュニケーションプランの設計を得意としています。
- こんな企業におすすめ:
- JR東日本沿線の観光地、宿泊施設、商業施設など、特定のエリアへの集客を強化したい企業・自治体。
- 通勤・通学者やビジネスパーソン、訪日外国人など、首都圏の「移動者」をメインターゲットとする企業。
- Suicaなどの移動データを活用した、データドリブンなマーケティング戦略に関心のある企業。
② 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
株式会社JTBコミュニケーションデザインは、日本最大の旅行会社であるJTBグループの一員です。その最大の強みは、長年にわたり旅行・観光業界の最前線で培ってきた深い業界知識と、国内外に広がる広範なネットワークです。
- 強み・特徴:
- 旅行業界への深い知見: JTBグループとして蓄積してきた旅行者の動向、消費者インサイト、観光地のトレンドに関する膨大なデータと知見に基づいた、的確なプロモーション戦略の立案が可能です。旅行という商品の特性を熟知しているため、机上の空論ではない、実効性の高い提案が期待できます。
- MICE領域での圧倒的な実績: MICE(ミーティング・インセンティブ・コンベンション・エキシビション)と呼ばれる、ビジネスイベント領域で国内トップクラスの実績を誇ります。 国際会議や学術大会、企業のインセンティブ旅行(報奨旅行)、大規模な展示会などの企画・運営を数多く手掛けており、これらのイベントと連動した観光プロモーションや地域活性化事業を得意としています。(参照:株式会社JTBコミュニケーションデザイン 公式サイト)
- グローバルなプロモーション対応: JTBのグローバルネットワークを活かし、インバウンド(訪日旅行)およびアウトバウンド(海外旅行)双方のプロモーションに精通しています。海外の旅行博への出展サポート、海外メディアやインフルエンサーを起用したPR、多言語でのコンテンツ制作など、グローバルな視点でのコミュニケーション戦略をワンストップで提供できます。
- こんな企業におすすめ:
- インバウンド需要の取り込みを本格的に強化したい観光地、自治体、DMO(観光地域づくり法人)。
- 国際会議や大型イベントの開催をフックに、地域の魅力を国内外に発信したい企業・団体。
- 旅行業界のプロフェッショナルによる、質の高いコンサルティングや企画力を求める企業。
③ 株式会社アドウェイズ
株式会社アドウェイズは、インターネット広告事業を中核とする大手広告代理店です。特に、スマートフォン向けの広告やアプリのプロモーションに強みを持ち、最新のテクノロジーを駆使したデータドリブンな広告運用を得意としています。
- 強み・特徴:
- Web・アプリマーケティングの専門性: 創業以来、PC・スマートフォン向けの広告事業を展開しており、デジタルマーケティングに関する高い専門性と運用ノウハウを蓄積しています。特に、旅行予約アプリのダウンロード促進や、OTAサイトへの送客といった、Web上でのコンバージョンを最大化する施策に長けています。
- データとテクノロジーの活用: 広告効果測定ツール「UNIBIRD」を自社で開発・提供するなど、テクノロジーへの投資を積極的に行っています。データに基づいた論理的な広告運用により、広告費用の最適化と効果の最大化を目指します。広告の成果を可視化し、PDCAサイクルを高速で回していくことを重視しています。
- アジア市場を中心とした海外展開: 中華圏や東南アジアなど、アジア各国に拠点を持ち、現地の市況や文化に精通したスタッフによるプロモーションが可能です。 WechatやWeiboといった中国独自のSNSを活用したマーケティングや、現地インフルエンサー(KOL)を起用した施策など、特に訪日客の多いアジア圏からのインバウンド集客に強みを発揮します。(参照:株式会社アドウェイズ 公式サイト)
- こんな企業におすすめ:
- 若年層やアジアからの訪日客をメインターゲットとし、SNS広告やWeb広告を主軸にプロモーションを展開したい企業。
- 自社の予約サイトやアプリへの直接的な流入・コンバージョンを最重要視する企業。
- 広告の費用対効果を厳密に管理し、データに基づいた合理的な意思決定を行いたい企業。
これらの代理店はそれぞれに得意な領域が異なります。代理店を選ぶ際には、自社のターゲット、目的、予算を明確にした上で、複数の代理店から提案を受け、自社の課題解決に最も貢献してくれるパートナーを見極めることが重要です。
まとめ
本記事では、旅行・観光業界における最新の広告手法について、オンラインとオフラインの両面から網羅的に解説しました。
現在の旅行・観光業界は、インバウンド需要の回復と国内旅行の活発化という大きな追い風の中にあります。しかし、その一方で消費者の価値観は「モノ」から「コト(体験)」へと移り、情報収集の手段は完全にオンライン中心へとシフトしました。このような環境変化に適応できなければ、激化する競争の中で埋もれてしまう可能性があります。
成功への鍵は、リスティング広告やSNS広告といったオンライン施策と、交通広告やイベントといったオフライン施策を、自社のターゲットに合わせて戦略的に組み合わせることです。そして、すべての広告活動の根底には、「そこでしかできない魅力的な体験価値」を伝え、顧客に最高の満足を提供し、その感動が自然な口コミ(UGC)として拡散していくという好循環を生み出す視点を持つことが不可欠です。
広告は、単なる宣伝ではありません。未来のお客様との最初のコミュニケーションであり、素晴らしい旅の始まりを約束するものです。
この記事で紹介した手法やポイントを参考に、まずは自社の強みと課題を整理し、ターゲット顧客のペルソナを明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。そこから、自社に最適な広告戦略が見えてくるはずです。変化の激しい時代だからこそ、挑戦できることは無限にあります。貴社のプロモーション活動が、多くの旅行者に素晴らしい体験を届ける一助となれば幸いです。