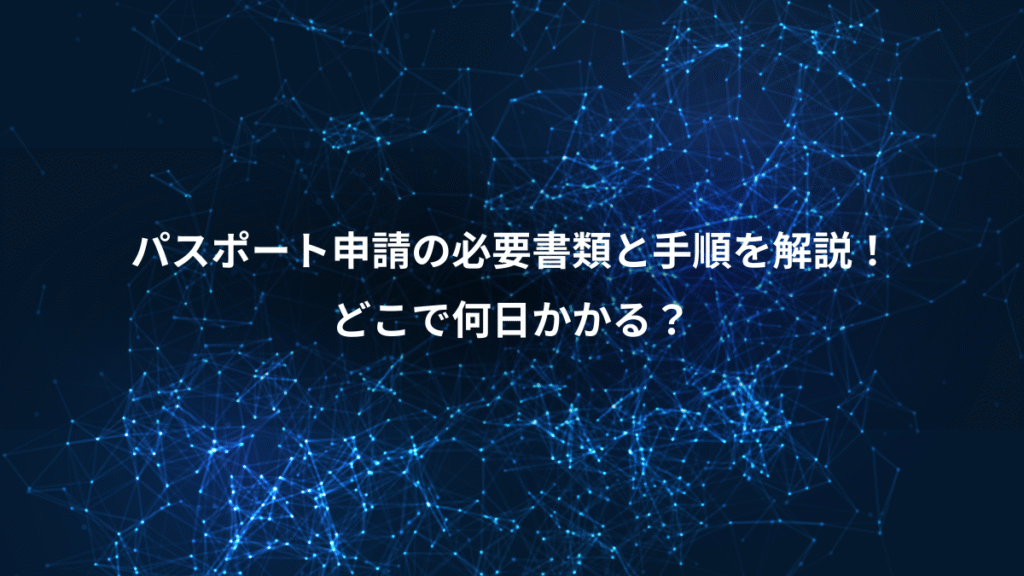海外旅行や海外出張に欠かせない身分証明書、それがパスポート(旅券)です。初めて海外へ行く方はもちろん、有効期限が迫っている方も、スムーズに手続きを進めるためには事前の準備が欠かせません。しかし、「どんな書類が必要なの?」「どこで申請すればいいの?」「申請してから受け取りまで何日かかる?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
パスポート申請には、いくつかの種類があり、ご自身の状況によって必要な書類や手続きが異なります。また、申請方法も従来の窓口申請に加え、近年ではマイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能になり、利便性が向上しています。
この記事では、パスポート申請の種類から、具体的な申請ステップ、必要書類の詳細、申請場所、日数、手数料に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。これからパスポートを申請する方が、この記事を読むだけで全ての疑問を解消し、安心して手続きに臨めるよう、分かりやすく丁寧にガイドします。
目次
まずは確認!パスポート申請の3つの種類
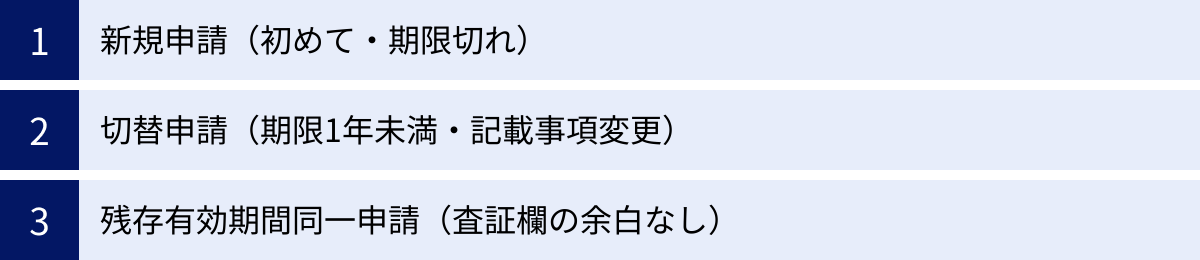
パスポートの申請手続きは、大きく分けて「新規申請」「切替申請」「残存有効期間同一申請」の3種類に分類されます。ご自身がどの申請に該当するのかを最初に正しく理解することが、スムーズな手続きの第一歩です。ここでは、それぞれの申請がどのようなケースで必要になるのか、その違いと特徴を詳しく解説します。
新規申請:初めて作る・有効期限が切れている場合
新規申請は、文字通り「初めてパスポートを作る」場合、または「所持しているパスポートの有効期限が完全に切れてしまった」場合に該当する手続きです。
対象となる主なケース
- これまでに一度もパスポートを取得したことがない方
- 以前パスポートを持っていたが、有効期限が1日でも過ぎてしまった方
有効期限が切れたパスポートは、身分証明書としての効力を失います。そのため、たとえ1日でも期限を過ぎていれば、後述する「切替申請」ではなく、全く新しいパスポートを作成する「新規申請」の扱いとなります。この場合、以前のパスポート番号は引き継がれず、新しい番号が発給されます。
手続きにおいては、戸籍や本人確認をゼロから行う必要があるため、必ず「戸籍謄本(または戸籍抄本)」の提出が求められます。 有効期限が切れた古いパスポートは、申請窓口で返却を求められることは基本的にありませんが、失効しているため本人確認書類としては使用できません。ただし、氏名のローマ字表記などを確認するために、参考資料として持参すると手続きがスムーズに進む場合があります。
申請時には、10年有効なパスポートと5年有効なパスポートのどちらかを選択できます。ただし、申請日時点で18歳未満の方は、5年有効なパスポートしか申請できないというルールがあるため注意が必要です。
新規申請は、パスポート取得の最も基本的な形であり、身分事項を公的に証明するための最初のステップと位置づけられています。海外渡航の予定が具体的に決まっていなくても、将来のために取得しておくことも可能です。いざという時に慌てないよう、余裕を持った準備を心がけましょう。
切替申請:有効期限が1年未満・記載事項に変更がある場合
切替申請は、「現在有効なパスポートを持っていて、その有効期間の残りが1年未満になった」場合や、「氏名や本籍地の都道府県など、パスポートの記載事項に変更が生じた」場合に行う手続きです。 新規申請とは異なり、既存のパスポート情報を更新するイメージに近い手続きです。
対象となる主なケース
- パスポートの残存有効期間が1年未満になった方
- 結婚や養子縁組などにより、氏名(姓または名)に変更があった方
- 本籍地の都道府県名に変更があった方(例:東京都から神奈川県へ変更)
- 国際結婚などで配偶者の姓を別名として追記または削除したい方
特に注意したいのが「残存有効期間」です。海外の多くの国では、入国時にパスポートの残存有効期間が「3ヶ月以上」や「6ヶ月以上」あることを条件としています。たとえパスポートの有効期限がまだ先でも、この条件を満たしていないと飛行機の搭乗を拒否されたり、入国審査で入国を拒否されたりする可能性があります。そのため、海外渡航の計画がある場合は、有効期間が1年を切った段階で早めに切替申請を行うことが強く推奨されます。
記載事項に変更があった場合も、速やかな切替申請が必要です。パスポートは国際的な身分証明書であり、その記載事項は戸籍などの公的書類と一致している必要があります。氏名や本籍地が変わったにもかかわらず古い情報のままのパスポートを使用し続けると、出入国審査や各種手続きでトラブルの原因となりかねません。
切替申請の大きなメリットは、氏名や本籍地の都道府県名に変更がない場合に限り、原則として戸籍謄本(または戸籍抄本)の提出が省略できる点です。これにより、書類準備の手間が大幅に軽減されます。ただし、変更がある場合は、その事実を証明するために新しい戸籍謄本の提出が必須となります。
申請手続きの際は、現在お持ちの有効なパスポートを必ず持参し、窓口に提出する必要があります。この古いパスポートは、申請時に失効処理(VOIDパンチによる穴あけ)を施された上で、新しいパスポートの受け取り時に返却されます。
残存有効期間同一申請:査証欄(ビザページ)の余白がなくなった場合
残存有効期間同一申請は、「パスポートの有効期間はまだ十分に残っているものの、海外への渡航が多く、査証(ビザ)や出入国スタンプを押すための査証欄の余白がなくなった」場合に行う特別な申請です。
以前は、査証欄を増やす「増補」という制度がありましたが、2014年3月20日をもって廃止されました。その代替措置として導入されたのが、この「残存有効期間同一申請」です。
対象となる主なケース
- 有効なパスポートの査証欄のページが、スタンプやビザで埋まってしまい、余白がほとんどなくなった方
この申請の特徴は、新しく発行されるパスポートの有効期間満了日が、元のパスポートの有効期間満了日と同一になる点です。例えば、有効期間満了日が2030年5月1日のパスポートの査証欄がなくなった場合、この申請を行うと、新しく発行されるパスポートの有効期間満了日も同じく2030年5月1日となります。
この申請の最大のメリットは、手数料が通常の新規・切替申請よりも安価であることです。有効期間を延長するわけではないため、比較的低いコストで新しい冊子(査証欄が十分にあるパスポート)を手に入れることができます。海外出張が多いビジネスパーソンや、世界一周旅行をしている方など、短期間に多くの国を訪れる方にとっては非常に便利な制度です。
ただし、注意点も存在します。この申請によって発行されるパスポートは、冊子自体は新しくなるため、パスポート番号(旅券番号)が変更されます。 航空券の予約やビザの申請、マイレージプログラムの登録情報などで古いパスポート番号を使用している場合は、すべて新しい番号に更新する手続きが必要になることを覚えておく必要があります。
申請手続きは切替申請とほぼ同様で、現在お持ちの有効なパスポートを提出する必要があります。査証欄の余白が残り少なくなってきたと感じたら、次の渡航計画に支障が出ないよう、早めにこの申請を検討しましょう。
パスポート申請から受け取りまでの簡単4ステップ
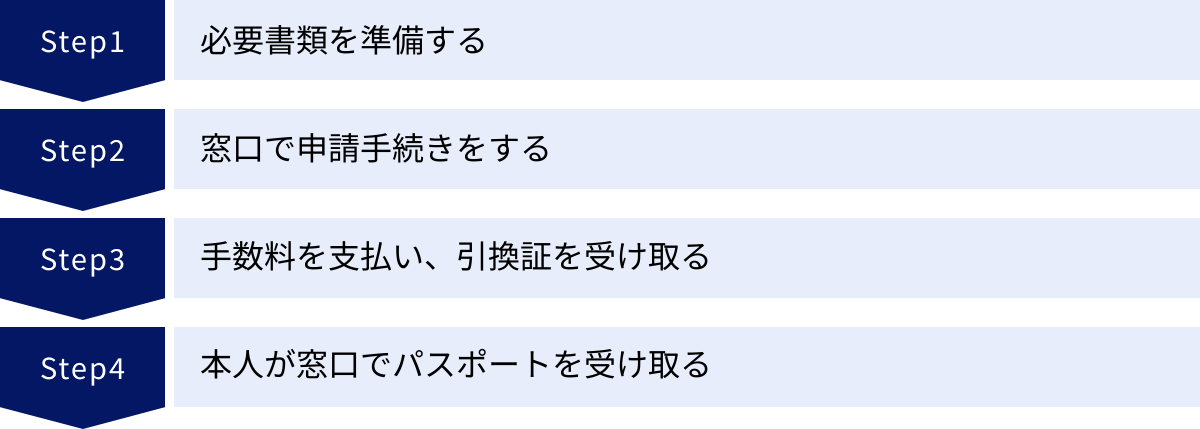
パスポート申請の全体像を把握するために、ここでは「必要書類の準備」から「パスポートの受け取り」までの一連の流れを、4つの簡単なステップに分けて解説します。この流れを頭に入れておけば、次に何をすべきかが明確になり、迷うことなく手続きを進めることができます。
① 必要書類を準備する
パスポート申請において、最も重要かつ時間がかかる可能性があるのが、この「必要書類の準備」ステップです。必要な書類は、後述の「パスポート申請に必要な書類一覧」で詳しく解説しますが、主に以下のものが挙げられます。
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
- パスポート用の写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 本人確認書類
- 前回取得したパスポート(お持ちの方のみ)
これらの書類を一つでも忘れたり、規格に合わないものを用意したりすると、申請が受理されず、再度窓口へ足を運ぶことになります。特に注意が必要なのは「戸籍謄本」と「写真」です。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できません。住民票のある場所と本籍地が異なる方は、郵送で取り寄せる必要があり、1〜2週間程度の時間がかかることもあります。ご自身の本籍地がどこか分からない場合は、住民票を取得して確認することから始めましょう。
また、パスポート用の写真は、サイズや顔の向き、背景など、国際基準で非常に厳格なルールが定められています。規格外の写真は受理されないため、スピード写真機や写真店で「パスポート用」と指定して撮影するのが確実です。
全ての書類が不備なく揃っているか、有効期限は切れていないかなどを事前にリスト化してチェックすることが、スムーズな申請への鍵となります。
② 窓口で申請手続きをする
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ申請窓口へ向かいます。申請場所は、原則として住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口(パスポートセンターなど)です。一部の市や町でも申請可能な場合がありますので、お住まいの自治体のウェブサイトで事前に確認しておきましょう。
窓口での手続きは、以下のような流れで進みます。
- 受付で番号札を取る(混雑時)
- 自分の番号が呼ばれたら、窓口で準備した書類一式を提出する
- 職員が書類の内容を一点ずつチェックする
- 申請書の記入漏れや誤りはないか
- 戸籍謄本や写真、本人確認書類は規定を満たしているか
- 氏名のローマ字表記は正しいか など
- 内容に問題がなければ、申請が受理される
窓口は、ゴールデンウィーク前や夏休み、年末年始といった海外旅行シーズン前は特に混雑する傾向があります。時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。また、申請書の記入で不明な点があれば、無理に自分で埋めずに空けておき、窓口の職員に質問しながら記入することも可能です。
申請が受理されると、パスポートの受け取り日や注意事項が記載された「受理票(旅券引換書)」が渡されます。 この書類は、パスポートを受け取る際に必ず必要になる非常に重要なものです。絶対に紛失しないよう、大切に保管してください。
③ 手数料を支払い、引換証を受け取る
ここで注意したいのは、パスポート申請の費用(手数料)は、申請時に支払うのではなく、後日パスポートを受け取る際に支払うという点です。
申請手続きが完了し、受理票を受け取った段階では、まだお金を支払う必要はありません。手数料の支払いは、収入印紙と都道府県収入証紙を所定の金額分購入し、受理票に貼り付けて行います。
これらの印紙・証紙は、パスポートセンター内に併設されている販売所や、郵便局、一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。受け取りに行く直前に購入しても問題ありませんが、場所によっては取り扱いがない場合もあるため、事前にパスポートセンター内で購入できるか確認しておくと安心です。
このステップは、厳密には「受け取り直前の準備」にあたりますが、申請が完了した時点で「次にやるべきこと」として認識しておくことが大切です。受理票を受け取ったら、そこに記載されている手数料の金額(収入印紙〇〇円、収入証紙〇〇円)をしっかり確認しておきましょう。
④ 本人が窓口でパスポートを受け取る
受理票に記載された交付予定日以降に、申請したのと同じ窓口へパスポートを受け取りに行きます。ここで最も重要なルールがあります。それは、「パスポートの受け取りは、年齢に関わらず必ず申請者本人が行かなければならない」という点です。
代理人による申請は可能ですが、受け取りは代理人では一切認められません。乳幼児であっても、必ず本人を連れて窓口に行く必要があります。これは、パスポートが国際的な身分証明書であり、最終的な本人確認を厳格に行うためです。
受け取り時に必要なものは、以下の2点です。
- 受理票(旅券引換書)
- 手数料(指定された金額の収入印紙と都道府県収入証紙を貼り付けたもの)
窓口で受理票と手数料を提出し、本人確認が行われた後、いよいよパスポートが交付されます。パスポートを受け取ったら、その場で必ず以下の点を確認してください。
- 顔写真が自分のものか
- 氏名、生年月日、性別、本籍地の都道府県などの記載事項に誤りはないか
- 署名欄(所持人自署)以外のページに書き込みがないか
万が一、記載内容に誤りがあった場合は、その場で職員に申し出る必要があります。問題がなければ、最後に「所持人自署」欄にサインをして、すべての手続きは完了です。この署名は、海外でクレジットカードを使用する際のサインと同じものにしておくと、本人確認がスムーズになるためおすすめです。
パスポート申請に必要な書類一覧
パスポート申請を成功させるためには、正確な書類準備が不可欠です。ここでは、申請に必要な各書類について、その入手方法や注意点を一つひとつ詳しく解説していきます。ご自身の状況に合わせて、どの書類が必要になるかを確認しながら準備を進めましょう。
一般旅券発給申請書
これは、パスポートを発行してもらうためのメインとなる申込用紙です。申請書には、10年有効なパスポート用の「10年用」と、5年有効なパスポート用の「5年用」の2種類があります。
- 10年用申請書:表紙上部の色が赤色
- 5年用申請書:表紙上部の色が紺色(または緑色)
申請日時点で18歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかを選択できますが、18歳未満の方は5年用しか申請できません。 間違った申請書を使用すると受理されないため、注意が必要です。
申請書の入手方法
申請書は、主に以下の場所で入手できます。
- パスポート申請窓口(パスポートセンターなど):各都道府県の申請窓口には必ず備え付けられています。
- 市区町村の役所・役場:住民登録をしている地域の役所・役場でも配布している場合があります。
- 外務省ウェブサイトからのダウンロード:外務省のウェブサイトには「ダウンロード申請書」というPDF形式の申請書があります。これをダウンロードしてパソコンで必要事項を入力し、印刷して署名すれば、窓口で手書きする手間が省けます。ただし、印刷する際の用紙のサイズや品質には規定があるため、サイトの注意事項をよく読んでから利用しましょう。(参照:外務省「パスポート申請書ダウンロード」)
申請書には、氏名、生年月日、本籍、現住所、緊急連絡先などを記入します。特に「所持人自署」欄は、代筆が認められていません。小学生以上の方は、原則として本人が署名する必要があります。まだ漢字が書けないお子様の場合は、ひらがなで名前を書く練習をしておくとよいでしょう。
戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
戸籍謄本は、申請者の身分事項(氏名、生年月日、本籍、親子関係など)を公的に証明するための重要な書類です。必ず発行日から6ヶ月以内のものを用意してください。
戸籍抄本では申請できないので注意
ここで非常に重要な注意点があります。それは、2023年3月27日から、パスポート申請に必要な書類が「戸籍抄本」から「戸籍謄本」に変更されたことです。(参照:外務省「戸籍謄本(全部事項証明書)の提出」)
- 戸籍謄本(全部事項証明書):その戸籍に入っている全員の情報が記載されたもの。
- 戸籍抄本(個人事項証明書):その戸籍に入っている特定の一人の情報のみを抜粋したもの。
以前は戸籍抄本でも申請可能でしたが、現在は戸籍謄本でなければ受理されません。 これは、申請者の身分事項をより正確に確認するための変更です。市区町村の役所で取得する際は、必ず「戸籍謄本」または「全部事項証明書」を請求してください。
なお、同一戸籍に属する家族(例:夫婦と未婚の子)が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出するだけで全員分の申請が可能です。
パスポート用の写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)
パスポートの写真は、国際民間航空機関(ICAO)の国際基準に基づいて厳格な規格が定められています。規格に合わない写真は、申請が受理されない最大の原因の一つです。必ず撮影から6ヶ月以内の新しい写真を用意してください。
写真のサイズや規格に関する細かいルール
写真を用意する際は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
| 項目 | 規格 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 写真全体のサイズ | 縦45ミリメートル × 横35ミリメートル | 縁なしで、顔の大きさとのバランスが重要。 |
| 顔のサイズ | 頭頂からあごまでが34±2ミリメートル(32~36mm) | 顔が大きすぎても小さすぎてもNG。 |
| 向き・表情 | 正面向き、無表情(口角が上がらない程度) | 横を向いたり、歯が見えるほど笑ったりしている写真は不可。 |
| 背景 | 無地で均一な淡い色(白、薄いグレー、薄いブルーなど) | 影があったり、グラデーションや柄のある背景は不可。 |
| 装飾品など | 無帽、マスク・サングラス不可、色付きコンタクト不可 | 前髪が目や顔の輪郭にかからないようにする。ピアスやイヤリングは光を反射しない、顔の輪郭を隠さないものであれば可。 |
| その他 | 目が開いていること、ピントが合っていること、平常時の顔貌と著しく異ならないこと |
これらの規格を個人で完璧に満たすのは難しいため、証明写真の専門ボックス(スピード写真機)の「パスポートモード」で撮影するか、写真スタジオで「パスポート用」と伝えて撮影してもらうのが最も確実で安心です。撮影した写真は、申請書に貼らずに、そのまま窓口へ持参しましょう。
本人確認書類
申請者が本人であることを証明するための書類です。有効な原本の提示が必要で、コピーは認められません。本人確認書類は、その信頼度に応じて「1点の提示で良いもの」と「2点の提示が必要なもの」に分かれています。
1点の提示で良い書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
顔写真付きで、公的機関が発行した信頼性の高い身分証明書がこれに該当します。以下のいずれか1点を提示すれば問題ありません。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード) ※通知カードは不可
- 写真付き住民基本台帳カード
- 船員手帳
- 宅地建物取引士証
- 身体障害者手帳(写真付き) など
これらの書類は、記載されている氏名、生年月日、住所などが、申請書の内容と一致している必要があります。引っ越しなどで住所が変わっている場合は、事前に書き換え手続きを済ませておきましょう。
2点の提示が必要な書類(健康保険証+年金手帳など)
上記「1点の提示で良い書類」を持っていない場合は、以下のA群とB群の書類を組み合わせて2点提示する必要があります。組み合わせは「A群から2点」または「A群から1点+B群から1点」のいずれかです。「B群から2点」の組み合わせは認められないので注意してください。
- 【A群】
- 健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
- 国民年金手帳、年金証書
- 印鑑登録証明書(と実印) など
- 【B群】
- 写真付きの学生証、会社の身分証明書
- 公的機関が発行した資格証明書(写真付き)
- 失効したパスポート(失効後6ヶ月を超えたもの) など
具体的な組み合わせ例
- 良い例①:健康保険証 + 国民年金手帳 (A群+A群)
- 良い例②:健康保険証 + 写真付き学生証 (A群+B群)
- 悪い例:写真付き学生証 + 写真付き会社の身分証明書 (B群+B群)→ 不可
中学生以下のお子様の場合は、法定代理人(親権者)の本人確認書類(運転免許証など)を提示することで、お子様の本人確認とすることも可能です。
前回取得したパスポート(お持ちの方のみ)
有効期間が残っているパスポートをお持ちで「切替申請」や「残存有効期間同一申請」を行う場合は、そのパスポートを必ず提出しなければなりません。 提出されたパスポートは失効処理が行われ、新しいパスポートの交付時に返却されます。もし有効なパスポートを紛失している場合は、通常の申請はできず、後述する紛失の手続きが必要になります。
有効期限が切れたパスポートについては、提出義務はありません。しかし、本人確認の一助となったり、氏名のローマ字表記を確認したりするために役立つことがあるため、もし手元にあれば持参するとよいでしょう。
【ケース別】住民票の写しが必要になる場合
通常、パスポート申請において「住民票の写し」は原則として不要です。これは、各都道府県のパスポート申請窓口が「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」を利用して申請者の住所情報を確認できるためです。しかし、特定の条件下では、例外的に住民票の写しの提出が求められることがあります。
住民基本台帳ネットワークを利用しない場合
申請者の中には、個人的な理由などから、自身の情報を住基ネットで照会されることを希望しない方もいるかもしれません。その場合、住基ネットの利用を希望しない旨を窓口で申し出ることで、住基ネットを使わずに申請手続きを進めることができます。
ただし、この選択をした場合は、住基ネットに代わって住所情報を証明する書類として、「住民票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの)」を自ら用意し、提出しなければなりません。 この住民票には、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを用意するのが一般的です。
基本的には住基ネットを利用する方が手間が省けて便利ですが、このような選択肢もあることを覚えておくとよいでしょう。
他の都道府県に住民登録しているが、一時的に住んでいる場所で申請する場合(居所申請)
パスポート申請は、原則として住民登録をしている都道府県で行います。しかし、学生や単身赴任者など、住民票を移さずに別の都道府県で生活している方も少なくありません。このような方々のために「居所(きょしょ)申請」という制度が設けられています。
居所申請とは、住民登録地とは異なる、実際に住んでいる場所(居所)の都道府県のパスポート申請窓口で申請を行うことです。 この居所申請を行う場合は、通常の必要書類に加えて、以下の2つの書類が追加で必要になります。
- 住民票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 住民登録地で取得した住民票が必要です。遠隔地の場合は郵送での取り寄せが必要になるため、早めに準備を始めましょう。
- 居所を証明する書類
- 現在住んでいる場所が確かに生活の本拠地であることを証明するための書類です。具体的には、以下のようなものが該当します。
- 学生・生徒の場合:在学証明書、学生証(現住所が記載されたもの)
- 単身赴任者・長期出張者の場合:会社の居所証明書、公共料金の領収書(本人名義)、アパートの賃貸借契約書など
- 船員の場合:船員手帳、船長の証明書など
- 現在住んでいる場所が確かに生活の本拠地であることを証明するための書類です。具体的には、以下のようなものが該当します。
居所申請が認められるのは、あくまで一時的に住民登録地を離れて生活している場合に限られます。 恒常的にその場所に住んでいるのであれば、本来は住民票を移すべきとされています。ご自身が居所申請の対象になるかどうか不明な場合は、申請を希望する都道府県のパスポートセンターに事前に問い合わせて確認することをおすすめします。この制度により、学業や仕事の都合で地元に帰れない方でも、現住所の近くでスムーズにパスポートを申請できます。
パスポートの申請場所・申請にかかる日数・手数料
パスポート申請の準備が整ったら、次に気になるのは「どこで」「何日で」「いくらで」手続きができるのか、という実務的な情報です。ここでは、申請場所、受け取りまでの所要日数、そして必要な手数料について、具体的な情報を分かりやすくまとめます。
どこで申請できる?
原則は住民登録している都道府県のパスポート申請窓口
パスポートの申請と受け取りは、原則として住民登録(住民票)がある都道府県の申請窓口で行います。これらの窓口は「パスポートセンター」や「旅券事務所」といった名称で、主に都道府県庁や主要都市の駅ビルなどに設置されています。
また、住民の利便性を高めるため、一部の市役所や町役場でも申請・受け取りの窓口業務を行っている場合があります。ただし、全ての自治体で対応しているわけではなく、申請のみ可能で受け取りは都道府県のセンターで行う必要があるなど、対応範囲が異なることもあります。
最も確実な方法は、お住まいの都道府県の公式ウェブサイトで「パスポート」と検索し、最寄りの申請窓口の場所、受付時間、休業日などを事前に確認することです。 これにより、無駄足を踏むのを防ぐことができます。
オンライン申請も可能
2023年3月27日から、マイナンバーカードを利用したパスポートのオンライン申請が本格的に導入されました。 これにより、従来のように申請時に窓口へ出向く必要がなくなりました。
オンライン申請は、政府のオンラインサービス「マイナポータル」を通じて行います。スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請手続きができ、窓口へ行くのはパスポートを受け取る時の1回のみとなります。この方法は、日中忙しくて窓口に行けない方や、できるだけ外出を減らしたい方にとって非常に便利な選択肢です。オンライン申請の詳細については、後ほど詳しく解説します。
申請から受け取りまで何日かかる?
目安は申請から1週間〜2週間程度
パスポートを申請してから受け取れるようになるまでの期間は、申請する都道府県や窓口、申請の種類によって異なりますが、一般的には申請日を含めずに6〜10営業日(土・日・祝日、年末年始を除く)が目安です。
例えば、東京都では新規・切替申請の場合、通常は申請日から6日目以降(土・日・祝日等を除く)に受け取れます。一方、他の県では8〜10日程度かかる場合もあります。
重要なのは、ここでいう日数は「営業日」でカウントされるという点です。 週の後半に申請した場合や、間に祝日を挟む場合は、暦のうえでの日数よりも長くかかります。
海外への渡航日が決まっている場合は、不測の事態(書類の不備による再申請など)も考慮し、出発日の最低でも3週間前、できれば1ヶ月以上の余裕を持って申請手続きを完了させることを強くお勧めします。特に、ゴールデンウィーク前や夏休み期間、年末年始は申請が集中し、通常より日数がかかる可能性もあるため、早めに行動しましょう。正確な交付予定日は、申請が受理された際に渡される「受理票(旅券引換書)」に記載されています。
費用・手数料はいくら?
パスポートの発給手数料は、申請の種類と有効期間によって異なります。手数料は、「国に納める収入印紙」と「都道府県に納める収入証紙」の2種類を組み合わせて支払います。これらの印紙・証紙は、パスポートを受け取る際に窓口で提出します。
以下に、主な申請ケースごとの手数料をまとめます。(参照:外務省「国内でパスポートを申請する場合の手数料」)
【10年用】新規・切替申請の手数料
| 対象 | 合計手数料 | 収入印紙 | 都道府県収入証紙 |
|---|---|---|---|
| 18歳以上 | 16,000円 | 14,000円 | 2,000円 |
【5年用】新規・切替申請の手数料
| 対象 | 合計手数料 | 収入印紙 | 都道府県収入証紙 |
|---|---|---|---|
| 12歳以上 | 11,000円 | 9,000円 | 2,000円 |
| 12歳未満 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
※年齢は「年齢計算に関する法律」に基づき、誕生日の前日に1歳加算されます。例えば、12歳の誕生日の前日に申請する場合、12歳として扱われます。
残存有効期間同一申請の手数料
| 対象 | 合計手数料 | 収入印紙 | 都道府県収入証紙 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
手数料の支払い方法
前述の通り、手数料はパスポートの受け取り時に、収入印紙と都道府県収入証紙で支払うのが基本です。これらの印紙・証紙は、パスポートセンター内の販売所、郵便局、一部の役所やコンビニエンスストアなどで購入できます。
近年、オンライン申請の普及に伴い、クレジットカードによる手数料のオンライン決済も可能になりました。オンライン申請を行った場合、審査完了の通知後にマイナポータル上でクレジットカード情報を入力して支払うことができます。この場合、受け取り時に印紙や証紙を用意する必要がなく、非常にスムーズです。ただし、窓口申請の場合は依然として印紙・証紙での支払いが主流ですので、ご自身の申請方法に合わせて準備しましょう。
知っておきたい!パスポート申請に関するQ&A
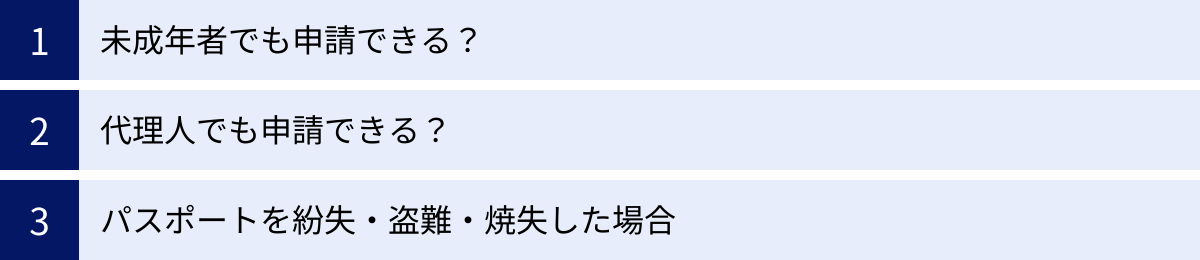
ここまでパスポート申請の基本的な流れや必要書類について解説してきましたが、個別のケースではさらに細かい疑問が生じることもあります。ここでは、特によくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
未成年者でも申請できる?
はい、未成年者でも年齢に関わらずパスポートを申請・取得できます。 赤ちゃんでも海外へ行くためにはパスポートが必要です。ただし、未成年者(申請日時点で18歳未満の方)の申請には、いくつか特別な注意点があります。
法定代理人(親権者など)の署名が必要
未成年者がパスポートを申請する場合、申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に、親権者(通常は父または母)または後見人が自署(サイン)する必要があります。この署名がないと、申請は受理されません。
もし親権者が遠方に住んでいるなど、直接署名をもらうのが難しい場合は、事前に申請書を送付して署名してもらい、返送してもらうといった準備が必要です。
また、親権の状況について窓口で確認される場合があるため、念のため親権者との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)の提示を求められることもあります。申請には戸籍謄本が必須なので、基本的にはそれで証明が可能です。
なお、前述の通り、18歳未満の方が申請できるのは5年有効なパスポートのみです。10年用は選択できません。
代理人でも申請できる?
はい、パスポートの「申請」手続きは、代理人が行うことが可能です。 これを「代理提出」と呼びます。病気や仕事の都合で本人が平日に窓口へ行けない場合に便利な制度です。
代理申請に必要な追加書類
代理提出を行う場合、通常の必要書類に加えて、以下の対応が必要です。
- 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入
- この欄は、申請者本人(パスポートを必要とする人)が「引受人(代理人)に申請を委任します」という意思を示す部分です。申請者本人が記入し、代理人の氏名や連絡先などを書きます。
- 代理人の本人確認書類
- 窓口へ行く代理人自身の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の原本が必要です。
注意点として、申請書内にある「所持人自署」欄や、申請者本人が記入すべき箇所は、必ず事前に本人が記入しておく必要があります。 代理人が代筆することはできません。
パスポートの受け取りは代理人不可
代理提出で申請した場合でも、パスポートの「受け取り」は、いかなる理由があっても代理人ではできず、必ず申請者本人が窓口へ行く必要があります。 これは、最終的な本人確認を厳格に行うためです。乳幼児であっても、本人を連れて行かなければパスポートは交付されません。この「申請は代理可、受け取りは本人必須」というルールは、絶対に覚えておきましょう。
パスポートを紛失・盗難・焼失した場合はどうする?
パスポートをなくしてしまった場合、それが国内か海外かによって手続きが大きく異なります。パスポートの不正利用を防ぐためにも、紛失に気づいたら速やかに手続きを行うことが重要です。
国内でなくした場合の手続き
- 警察への届出:まず最寄りの警察署または交番に「遺失物届」を提出します。このとき発行される「届出受理番号」は、後の手続きで必要になるので必ず控えておきましょう。
- 紛失届の提出:住民登録のある都道府県のパスポート申請窓口へ行き、「紛失一般旅券等届出書」を提出します。これにより、紛失したパスポートは正式に失効処理されます。
- 新規発給申請:紛失届と同時に、新しいパスポートの新規発給申請を行うことができます。その際は、以下の書類が必要です。
- 紛失一般旅券等届出書
- 新規発給用の一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
- パスポート用の写真(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 本人確認書類
- 警察の遺失物届受理番号
一度紛失届を提出すると、後から紛失したパスポートが見つかっても、そのパスポートを再度使用することはできません。
海外でなくした場合の手続き
海外でのパスポート紛失は、不法滞在や帰国不能につながる一大事です。パニックにならず、落ち着いて以下の手順で行動してください。
- 現地警察への届出:まず滞在国の警察へ行き、パスポートを紛失・盗難された旨を届け出て、「ポリスレポート(紛失・盗難証明書)」を発行してもらいます。これがなければ、大使館・総領事館での手続きができません。
- 日本国大使館・総領事館へ連絡:最寄りの在外公館(日本国大使館または総領事館)へ連絡し、必要な手続きを確認します。
- 在外公館での手続き:以下の書類を持参して、在外公館で手続きを行います。
- 紛失一般旅券等届出書
- ポリスレポート(紛失・盗難証明書)
- 戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
- パスポート用の写真
- その他、本人確認ができる書類
このとき、滞在日数やその後の予定に応じて、「新規パスポートの発給」または「帰国のための渡航書」の発給を申請します。
- 新規パスポートの発給:滞在が長く、他の国へも渡航する予定がある場合に申請します。発給には1〜2週間程度かかります。
- 帰国のための渡航書:日本へ直行で帰国する場合にのみ有効な、パスポートの代わりとなる書類です。通常は即日〜数日で発給されますが、これを使って他の国へ周遊することはできません。
海外で戸籍謄本をすぐに入手するのは難しいため、日本にいる家族に連絡して取得・送付してもらう必要があります。万一の事態に備え、海外へ行く際はパスポートのコピーや写真データ、戸籍謄本のコピーなどを別途保管しておくと、手続きがスムーズに進みます。
マイナンバーカードで簡単!パスポートのオンライン申請とは

従来の窓口申請に加え、2023年3月から本格的にスタートしたのが、マイナンバーカードを活用したパスポートのオンライン申請です。これにより、申請手続きがこれまで以上に手軽で便利になりました。ここでは、オンライン申請のメリットや必要なもの、具体的な手順について詳しく解説します。
オンライン申請のメリット
オンライン申請には、従来の窓口申請にはない多くのメリットがあります。
- 24時間365日いつでも申請可能:スマートフォンのアプリ「マイナポータル」を使えば、深夜や休日でも、自宅や好きな場所から申請手続きができます。
- 窓口へ行くのは受け取り時の1回だけ:申請のために平日に仕事を休んだり、時間を調整したりする必要がありません。窓口での待ち時間も大幅に削減できます。
- 手書き不要で入力が簡単:申請書を手書きする必要がなく、画面の指示に従って情報を入力していくだけで完了します。入力ミスも減らせます。
- 写真のアップロードが便利:スマートフォンで撮影した顔写真データをそのままアップロードして使用できます。背景などの規格は守る必要がありますが、写真店に行く手間が省けます。
- 手数料のクレジットカード決済が可能:審査完了後、マイナポータル上で手数料をクレジットカードで支払うことができます。受け取り時に収入印紙や証紙を用意する必要がなくなり、キャッシュレスで完結します。
これらのメリットにより、特に日中忙しい方や、手続きの手間を少しでも減らしたい方にとって、オンライン申請は非常に魅力的な選択肢となっています。
オンライン申請に必要なもの
パスポートのオンライン申請を行うためには、以下のものが必要です。
- 有効なマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)と署名用電子証明書(6〜16桁の英数字のパスワード)が有効な状態である必要があります。
- マイナポータルアプリに対応したスマートフォン
- マイナンバーカードのICチップを読み取れるNFC機能が搭載されたスマートフォンが必要です。または、ICカードリーダライタを接続したパソコンでも可能です。
- マイナポータルアプリ
- 事前にスマートフォンにインストールし、利用者登録を済ませておきます。
- パスポート用の顔写真データ
- 6ヶ月以内に撮影したもので、ファイル形式やサイズなどの規格を満たす必要があります。スマートフォンで自撮りする場合は、背景や明るさなどに十分注意しましょう。
- 有効期間内のパスポート(切替申請の場合のみ)
- 申請手続き中に、パスポートに内蔵されているICチップの情報をスマートフォンで読み取る工程があります。
これらの準備が整っていれば、すぐにでもオンライン申請を始めることができます。
オンライン申請の手順
オンライン申請の基本的な流れは、以下の通りです。
- マイナポータルにログイン
- スマートフォンでマイナポータルアプリを起動し、マイナンバーカードを読み取ってログインします。
- パスポート申請メニューを選択
- トップページから「パスポート取得・更新」のメニューを選択します。
- 申請情報の入力
- 画面の指示に従い、申請の種類(新規・切替など)、氏名、本籍、連絡先などの必要情報を入力していきます。
- 顔写真のアップロード
- 用意しておいた顔写真データをアップロードします。マイナポータルの顔認証機能で、写真が規格に合っているかある程度のチェックが行われます。
- 自署画像のアップロード
- 白い紙に署名したものを撮影し、その画像をアップロードします。(所持人自署の代わりとなります)
- パスポート情報の読み取り(切替申請の場合)
- 現在お持ちのパスポートの顔写真ページを開き、ICチップの情報をスマートフォンで読み取ります。
- 電子署名の付与
- 最後に、マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁)を入力し、電子署名を行います。
- 申請完了と審査
- 以上で申請データの送信は完了です。その後、パスポートセンターで審査が行われ、修正が必要な場合はマイナポータルを通じて通知が来ます。
- 手数料の支払いと受け取り
- 審査が完了すると、交付予定日と手数料の納付依頼が通知されます。クレジットカードでオンライン決済を行った後、指定された期間内に本人が窓口へ行き、パスポートを受け取ります。
オンライン申請は、パスポート取得のあり方を大きく変える画期的なシステムです。 マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひこの便利な方法の活用を検討してみてはいかがでしょうか。