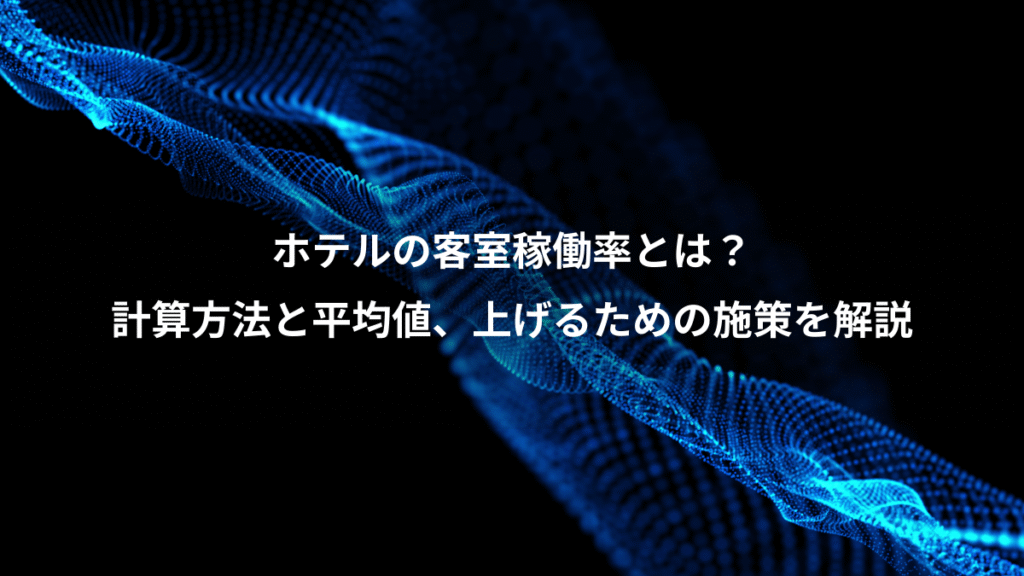ホテル経営において、収益性を測るための指標は数多く存在します。その中でも、最も基本的かつ重要な指標の一つが「客室稼働率」です。この数値は、ホテルの人気度や集客力を直接的に示すバロメーターであり、経営の健全性を判断する上で欠かせません。
しかし、単に稼働率の数字を追うだけでは、経営の全体像を把握することは困難です。なぜ稼働率が重要なのか、他の指標とどう関係するのか、そして具体的にどうすれば稼働率を向上させられるのかを体系的に理解することが、持続的な成長の鍵となります。
この記事では、ホテルの客室稼働率の基本的な定義から、経営分析に不可欠な関連指標、稼働率の計算方法、日本のホテルの平均値までを網羅的に解説します。さらに、稼働率が伸び悩む原因を分析し、明日から実践できる具体的な改善施策7選、そしてそれらを支える便利なITシステムまで、詳しくご紹介します。
目次
ホテルの客室稼働率(OCC)とは

ホテルの客室稼働率(Occupancy Rate、略してOCC)とは、ホテルが販売できる状態にある全客室のうち、実際に顧客に販売された客室が占める割合を示す指標です。この数値は、ホテルの集客力や人気度を測るための最も基本的で重要なバロメーターとして、世界中のホテルで広く用いられています。
例えば、100室の客室を持つホテルで、ある日に80室が販売された場合、その日の客室稼働率は80%となります。この率が高いほど、多くの客室が利用されていることを意味し、ホテルの収益性が高いと判断できます。
客室稼働率がホテル経営において極めて重要視される背景には、ホテルビジネスの持つ特有の性質があります。ホテルの「客室」という商品は、一般的な商品とは異なり、「在庫の繰り越しができない」という大きな特徴を持っています。これは「消滅可能性(Perishability)」と呼ばれ、その日に売れなかった客室は、翌日に持ち越して販売することができません。その日の分の価値は完全に失われてしまうのです。飛行機の座席やコンサートのチケットと同じ性質を持っていると考えると分かりやすいでしょう。
このため、ホテルは一日でも多くの客室を販売し、空室を最小限に抑えることが至上命題となります。客室稼働率は、この「在庫をどれだけ効率的に販売できたか」を直接的に示す成績表であり、日々の収益に直結する最重要指標なのです。
高い客室稼働率を維持することは、ホテル経営に多くのメリットをもたらします。第一に、直接的な収益の増加です。客室売上はホテルの収益の根幹をなすため、稼働率の向上は経営基盤の安定に直結します。第二に、付帯施設の利用促進です。宿泊客が増えれば、レストランやバー、スパ、売店といった付帯施設の利用機会も自然と増え、ホテル全体の総収益(TRevPAR)向上に貢献します。
第三に、ブランドイメージの向上です。「いつも賑わっている人気のホテル」という印象は、市場におけるホテルの評価を高め、さらなる集客を呼び込む好循環を生み出します。口コミサイトやSNSでの評判も高まりやすくなり、広告宣伝に頼らずとも顧客を引きつける力が強まります。
一方で、稼働率が高ければ高いほど良い、というわけでもありません。常に100%に近い稼働率を維持しようとすると、いくつかの課題が生じる可能性があります。例えば、清掃やメンテナンスの時間が十分に確保できず、客室の品質が低下するリスクがあります。また、フロントやレストランのスタッフに過度な負担がかかり、サービスの質が落ちて顧客満足度の低下を招くことも考えられます。さらに、満室が続くことで、急な宿泊希望やリピーターの予約を受け入れられず、販売機会を損失する可能性も出てきます。
したがって、ホテル経営においては、単に稼働率の最大化を目指すだけでなく、サービスの品質や従業員の負担、そして後述する平均客室単価(ADR)とのバランスを取りながら、最適な稼働率の水準を見極めることが求められます。
初心者が抱きがちな疑問として、「稼働率と客室利用率は同じ意味ですか?」というものがあります。一般的に、これらはほぼ同義で使われることが多いですが、厳密には文脈によって使い分けられることもあります。客室稼働率は、特定の期間(日、月、年)における「販売可能な客室」に対する「販売済み客室」の割合を指す経営指標として定着しています。一方で「利用率」は、より広い意味で使われることがあります。この記事では、ホテル業界の標準的な用語である「客室稼働率(OCC)」として統一して解説します。
まとめると、客室稼働率(OCC)は、ホテルの収益性と集客力を測るための根幹的な指標です。在庫の繰り越しができない客室という商品の特性上、この数値をいかに高めるかが経営の鍵となります。ただし、その追求は他の重要指標やサービス品質とのバランスを考慮しながら、戦略的に行う必要があります。次の章では、この稼働率とセットで理解すべき、さらに重要な経営指標について詳しく見ていきましょう。
稼働率とあわせて理解したいホテル経営の重要指標(KPI)
ホテルの経営状況を正確に把握するためには、客室稼働率(OCC)だけを追っていては不十分です。たとえ稼働率が100%であっても、不当に安い価格で販売していれば、十分な利益は得られません。逆に、稼働率が多少低くても、高い客単価を維持できていれば、収益性は高くなります。このように、ホテルの収益性は「販売した客室の数(量)」と「1室あたりの販売価格(質)」の掛け算で決まります。
ここでは、客室稼働率と合わせて分析することで、より多角的かつ正確に経営状態を評価できる3つの重要なKPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)を解説します。
| 指標名 | 略称 | 計算式 | 概要と分析のポイント |
|---|---|---|---|
| 平均客室単価 | ADR (Average Daily Rate) | 客室売上合計 ÷ 販売した客室数 | 販売された客室1室あたりの平均価格。「質」を測る指標。稼働率(OCC)とのバランスが重要。 |
| 販売可能な客室あたりの収益 | RevPAR (Revenue Per Available Room) | 客室売上合計 ÷ 販売可能な総客室数 (または ADR × OCC) | 販売可能な全客室1室から得られる収益。「量」と「質」を掛け合わせた、ホテル収益性の最重要指標。 |
平均客室単価(ADR)
平均客室単価(ADR:Average Daily Rate)は、その日に販売した客室1室あたりの平均販売価格を示す指標です。これは、ホテルの価格設定戦略やブランド価値がどれだけ市場に受け入れられているかを示す「質」の指標と言えます。
計算式は非常にシンプルです。
ADR = 客室売上合計 ÷ 販売した客室数
例えば、ある日の客室売上合計が1,000,000円で、販売した客室数が80室だった場合、その日のADRは以下のようになります。
1,000,000円 ÷ 80室 = 12,500円
このホテルのADRは12,500円となります。この数値が高いほど、1室あたりの販売価格が高く、収益性が高いことを意味します。
ADRを分析する際には、いくつかの注意点があります。まず、ADRはあくまで「平均」の単価であるという点です。ホテルには、スタンダードルームからスイートルームまで様々なタイプの客室があり、それぞれ料金が異なります。また、同じ客室タイプでも、予約経路(公式サイト、OTA、法人契約など)や宿泊プランによって販売価格は変動します。したがって、ホテル全体のADRを見るだけでなく、客室タイプ別、予約経路別、市場セグメント(国内レジャー、インバウンド、ビジネスなど)別にADRを分析することで、どの分野が収益に貢献しているのか、あるいはどの分野に課題があるのかをより詳細に把握できます。
ADRと客室稼働率(OCC)は、密接な関係にあり、多くの場合、トレードオフの関係になります。一般的に、宿泊料金を上げれば(ADR上昇)、需要が減って客室稼働率(OCC)は下がる傾向にあります。逆に、料金を下げれば(ADR下落)、需要が喚起されて客室稼働率(OCC)は上がりやすくなります。
ホテル経営の難しさは、この二律背反の関係にあるADRとOCCの最適なバランスポイントを見つけることにあります。安易な値下げで稼働率を上げる戦略は、一時的な売上増には繋がるかもしれませんが、ブランドイメージの低下を招き、長期的に見ると収益性を悪化させる危険性があります。重要なのは、自社のブランド価値や提供する体験に見合った価格設定を維持しつつ、需要を予測しながら価格を最適化していくレベニューマネジメントの実践です。
販売可能な客室あたりの収益(RevPAR)
販売可能な客室あたりの収益(RevPAR:Revenue Per Available Room)は、ホテル経営において最も重要視される指標の一つです。その理由は、RevPARが「販売数(量)」を示す客室稼働率(OCC)と、「販売単価(質)」を示す平均客室単価(ADR)の両方の要素を統合した、極めてバランスの取れた収益性指標だからです。
RevPARの計算方法は2通りあります。
- RevPAR = 客室売上合計 ÷ 販売可能な総客室数
- RevPAR = ADR(平均客室単価) × OCC(客室稼働率)
どちらの式を使っても同じ結果が得られます。2つ目の式を見ると、RevPARがADRとOCCの掛け算で成り立っていることがよく分かります。
ここで、なぜOCCやADR単体ではなく、RevPARが重要なのかを具体例で見てみましょう。ここにAとB、2つの競合ホテルがあるとします。(販売可能な総客室数はどちらも100室とします)
- ホテルA:
- 客室稼働率(OCC): 90%
- 平均客室単価(ADR): 10,000円
- RevPAR = 10,000円 × 90% = 9,000円
- ホテルB:
- 客室稼働率(OCC): 70%
- 平均客室単価(ADR): 15,000円
- RevPAR = 15,000円 × 70% = 10,500円
この例では、ホテルAは稼働率が90%と非常に高く、一見すると非常に好調に見えます。一方、ホテルBの稼働率は70%と、Aに比べて見劣りします。しかし、RevPARを比較すると、ホテルB(10,500円)の方がホテルA(9,000円)よりも高いことが分かります。これは、ホテルBが高い客室単価を維持することで、客室1室あたりの収益力を最大化できていることを示しています。つまり、経営の効率性という観点では、ホテルBの方が優れていると評価できるのです。
このように、RevPARは、空室も含めた全客室が平均していくらの収益を生み出しているかを示す指標であり、ホテルの真の収益力を測るための最も信頼性の高いものさしとなります。ホテル経営者は、日々のオペレーションにおいて、常にこのRevPARを最大化することを目標に、価格設定や販売戦略を練る必要があります。
RevPARを向上させるためには、OCCを上げるか、ADRを上げるか、あるいはその両方を同時に上げる戦略が考えられます。例えば、閑散期には価格を多少調整してでもOCCを高めてRevPARの底上げを図り、繁忙期には強気の価格設定でADRを最大化し、高いRevPARを実現するといった、需要に合わせた柔軟な戦略が求められます。
客室稼働率(OCC)、平均客室単価(ADR)、そしてRevPAR。これら3つの指標をセットで定点観測し、それぞれの相関関係を理解することが、データに基づいた的確な経営判断を下すための第一歩となるのです。
ホテルの稼働率が重要視される理由
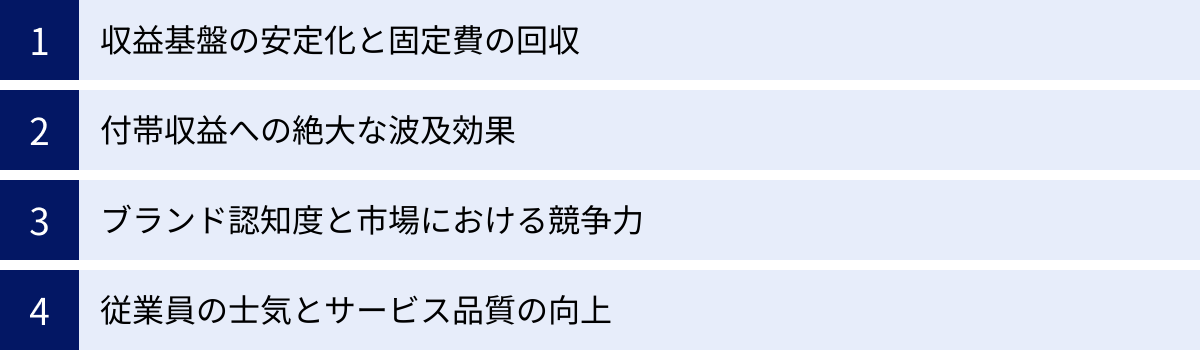
前述の通り、客室稼働率はRevPARを構成する一要素であり、ADRとのバランスが重要です。しかし、それでもなお、稼働率という指標そのものに注目が集まり、重要視され続けるのには、単なる計算式以上の深い理由があります。稼働率は、ホテルの収益性だけでなく、ブランド力、組織力といった経営の根幹を支える生命線ともいえる存在なのです。
ここでは、ホテルの稼働率がなぜこれほどまでに重要視されるのか、その理由を4つの側面に分けて深掘りします。
1. 収益基盤の安定化と固定費の回収
ホテル経営は、典型的な固定費ビジネスです。建物の減価償却費、土地の賃料、正社員の人件費、水道光熱費の基本料金、各種システムの利用料など、宿泊客が一人もいなくても毎日発生するコスト(固定費)が非常に大きいという特徴があります。
稼働率は、この莫大な固定費を回収し、利益を生み出すための源泉となります。客室が1室売れるごとに得られる売上から、リネン代やアメニティ代といった変動費を差し引いた利益(限界利益)が、固定費の回収に充てられます。稼働率が損益分岐点(利益がゼロになる点)を超えて初めて、ホテルは利益を生み出すことができるのです。
例えば、損益分岐点稼働率が60%のホテルであれば、稼働率が50%の日が続くと赤字が膨らみ、経営は立ち行かなくなります。逆に、常に70%、80%といった高い稼働率を維持できれば、安定的に利益を積み上げることができ、将来の設備投資や人材育成への再投資も可能になります。このように、安定した高水準の稼働率を確保することは、経営の土台を固め、持続的な成長を可能にするための絶対条件なのです。
2. 付帯収益への絶大な波及効果
ホテルの収益源は、客室販売だけではありません。レストランやバーでの飲食、宴会場の利用、スパやフィットネスジム、お土産などを販売する売店など、様々な付帯施設からの収益も経営を支える重要な柱です。
客室稼働率は、これらの付帯収益を左右する最も強力なドライバーとして機能します。当然のことながら、ホテルに滞在する宿泊客の数が増えれば増えるほど、館内施設が利用される機会も格段に増えます。稼働率が10%向上すれば、それは単に客室売上が増えるだけでなく、朝食の利用者数、ディナーの予約数、バーでの一杯の注文、お土産の購入額といった、あらゆる収益機会の増加に繋がるのです。
あるビジネスホテルでは、平日の稼脱率が低いことが課題でした。そこで、近隣企業向けの研修付き宿泊プランを開発し、平日の稼働率を20ポイント向上させたところ、客室売上の増加分以上に、夕食時のレストラン利用や夜のバーカウンターの売上が大幅に増加したというケースもあります。これは、稼働率の向上がホテル全体の経済を活性化させることを示す好例です。宿泊客という「分母」を増やすことが、ホテル全体の収益を最大化するための最も効果的なアプローチの一つと言えるでしょう。
3. ブランド認知度と市場における競争力
稼働率は、ホテルの「人気」を可視化する指標です。高い稼働率を維持しているホテルは、それだけで「多くの人に選ばれている、価値のあるホテル」という強力なメッセージを市場に発信します。これは、潜在的な顧客に対して大きな安心感と魅力を与えます。
消費者は、ホテルを選ぶ際にOTA(オンライントラベルエージェント)のレビューやSNSの評判を参考にします。高い稼働率を誇るホテルは、それだけ多くの宿泊体験が生まれているということであり、結果として口コミの数も増えやすくなります。「いつも予約でいっぱい」「活気がある」といった評判は、さらなる顧客を呼び込む好循環を生み出します。このようなポジティブなブランドイメージは、価格競争から一線を画し、適正な価格(高いADR)を維持するための大きな助けとなります。
逆に、稼働率が低い状態が続くとどうなるでしょうか。「いつも空室がある」「閑散としている」というイメージは、顧客に「何か問題があるのではないか」という不安を抱かせかねません。その結果、集客のために値下げに踏み切らざるを得なくなり、ブランド価値の毀損と収益性の低下という悪循環に陥ってしまうリスクがあります。
4. 従業員の士気とサービス品質の向上
稼働率は、顧客だけでなく、ホテルで働く従業員のモチベーションにも大きな影響を与えます。自分たちの働くホテルが多くの顧客で賑わい、活気に満ちている状況は、スタッフにとって大きなやりがいと誇りに繋がります。日々の業務に手応えを感じることができ、チームの一体感も醸成されやすくなります。
また、安定した稼働率と収益は、雇用の維持や安定的な昇給、福利厚生の充実といった形で従業員に還元されます。これにより、従業員満足度(ES)が向上し、離職率の低下にも繋がります。満足度の高い従業員は、より質の高いサービスを顧客に提供する傾向があり、それが顧客満足度(CS)の向上、そしてリピート利用の促進へと繋がっていくのです。稼働率の向上は、ESとCSの好循環を生み出すための重要な起点となり、ホテル全体の組織力を強化します。
以上のことから、客室稼働率は単なる経営指標の一つに留まらず、収益、ブランド、組織というホテル経営の根幹をなす要素すべてに深く関わる、極めて重要な指標であると言えるのです。
ホテルの客室稼働率の計算方法
ホテルの客室稼働率(OCC)を正確に把握し、日々の経営分析に活かすためには、その計算方法を正しく理解しておくことが不可欠です。計算式自体は非常にシンプルですが、計算に用いる各項目の定義を社内で統一し、一貫したルールで運用することが重要になります。
基本となる計算式は以下の通りです。
客室稼働率(%) = (販売した客室数 ÷ 販売可能な総客室数) × 100
この計算式を構成する2つの重要な要素、「販売した客室数」と「販売可能な総客室数」について、詳しく見ていきましょう。
1. 販売した客室数 (Rooms Sold / Occupied Rooms)
これは、文字通り、特定の日に料金が発生して顧客に販売・利用された客室の総数を指します。一般的には「有料で稼働した部屋の数」と考えると分かりやすいでしょう。
ただし、カウントする際にはいくつかの注意点があります。
- 長期滞在: 2週間滞在している顧客がいる場合、その客室は滞在期間中の14日間、毎日「1室」としてカウントされます。
- デイユース(休憩利用): 宿泊を伴わない数時間の利用については、ホテルの会計基準や方針によって扱いが異なります。一般的には、客室稼働率の計算からは除外し、「客室回転率」といった別の指標で管理することが多いです。これは、1泊の宿泊と数時間の休憩を同列に「1室」とカウントすると、収益の実態が正しく反映されないためです。
- 無料宿泊: ポイントプログラムを利用した無料宿泊や、ホテル側の都合による招待(コンプリメンタリー)など、売上が発生しない客室については、通常「販売した客室数」には含めません。これも、収益性を測るという本来の目的から逸れてしまうためです。
2. 販売可能な総客室数 (Available Rooms)
これは、ホテルがその日に販売することができる状態にある客室の総数を指します。ここで重要なのは、ホテルが物理的に保有する全客室数(総客室数)とは必ずしも一致しないという点です。
販売可能な総客室数は、以下の計算で求められます。
販売可能な総客室数 = ホテルの総客室数 – 販売停止客室数 (Out of Order Rooms)
「販売停止客室数(OOOルーム)」とは、改装、大規模な修繕、清掃の遅れ、水漏れなどの設備不良といった理由により、物理的に顧客に提供できない状態にある客室のことです。これらの客室は、そもそも販売の土俵に上がっていないため、稼働率を計算する際の分母から除外するのが一般的です。これにより、純粋に「販売できる状態の客室のうち、どれだけ売れたか」という、より実態に即した稼働率を算出できます。
■ 具体的な計算例
それでは、具体的なシナリオで稼働率を計算してみましょう。
【条件】
- ホテルの総客室数: 200室
- その日の販売停止客室数(OOOルーム): 10室(うち5室は改装中、5室は空調設備の故障)
- その日に販売した客室数: 152室
【計算ステップ】
ステップ1: 販売可能な総客室数を計算する
販売可能な総客室数 = 200室 (総客室数) – 10室 (販売停止客室数) = 190室
ステップ2: 客室稼働率を計算する
客室稼働率 = (152室 (販売した客室数) ÷ 190室 (販売可能な総客室数)) × 100
= 0.8 × 100
= 80%
この日の客室稼働率は80%となります。
もし、分母に販売停止客室を考慮せず、総客室数(200室)を使って計算してしまうと、(152 ÷ 200) × 100 = 76% となり、実際の販売パフォーマンスよりも低い数値が出てしまいます。正確な経営判断のためには、販売停止客室を適切に管理し、日々の販売可能客室数を正確に把握することが極めて重要です。
■ 月間・年間の稼働率の計算
日々の稼働率だけでなく、月間や年間の稼働率も重要な経営指標です。これらは、日々の数値を単純に平均するのではなく、期間中の延べ数を用いて計算するのが最も正確な方法です。
- 月間稼働率 = (月間の合計販売客室数 ÷ 月間の合計販売可能客室数) × 100
- 年間稼働率 = (年間の合計販売客室数 ÷ 年間の合計販売可能客室数) × 100
例えば、31日ある月で、毎日販売可能客室数が190室だった場合、月間の合計販売可能客室数は 190室 × 31日 = 5,890室となります。この月の合計販売客室数が4,712室だった場合、月間稼働率は (4,712 ÷ 5,890) × 100 = 80% となります。
日々の稼働率を正確に記録・集計し、月次、年次で分析することで、季節変動やイベント効果、施策の効果測定などを客観的に評価できるようになります。これらの計算は、後述するPMS(ホテル管理システム)を導入することで、自動的にかつ正確に行うことが可能です。
日本のホテルの客室稼働率の平均値
自社のホテルの客室稼働率が適切かどうかを判断するためには、市場全体の動向と比較することが有効です。ここでは、公的な統計データに基づき、日本のホテルの客室稼働率の平均値や推移について解説します。自社のポジションを客観的に把握し、目標設定や戦略立案の参考にしてください。
なお、ここで紹介する数値は、主に観光庁が毎月発表している「宿泊旅行統計調査」を基にしています。この調査は、日本国内の宿泊施設の稼働率や宿泊者数を把握するための最も信頼性の高い情報源の一つです。
■ 全体的な稼働率の推移
日本の宿泊施設全体の客室稼働率は、国内外の情勢に大きく影響を受けながら変動してきました。
- コロナ禍以前(〜2019年): 訪日外国人観光客(インバウンド)の増加に牽引され、日本の宿泊業界は活況を呈していました。全国の宿泊施設の客室稼働率は60%台で推移し、特にシティホテルやビジネスホテルなどの洋室系の宿泊施設では、80%を超える高い水準を維持していました。
- コロナ禍(2020年〜2022年前半): 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う渡航制限や移動自粛により、稼働率は歴史的な低水準まで落ち込みました。特にインバウンド需要が消失した影響は甚大で、2021年の年間客室稼働率は全国で34.6%まで低下しました。(参照:観光庁 宿泊旅行統計調査)
- 回復期(2022年後半〜現在): 水際対策の緩和や全国旅行支援などの国内観光振興策により、稼働率は急速に回復。特に2022年10月以降のインバウンド需要の本格的な回復が大きな追い風となっています。
■ 最新の稼働率データ(2024年4月時点)
観光庁が発表した最新の「宿泊旅行統計調査(令和6年4月分・第1次速報値)」によると、2024年4月の宿泊施設全体の客室稼働率は61.3%でした。これは、コロナ禍前の2019年同月比で-2.3ポイントと、ほぼ同水準まで回復していることを示しています。
■ 施設タイプ別・地域別の稼働率
稼働率は、ホテルのタイプや立地によって大きく異なります。自社の稼働率を比較する際は、全国平均だけでなく、自ホテルと同じ施設タイプ、同じ地域のデータと比較することが極めて重要です。
以下の表は、2024年4月(第1次速報値)のデータを基に、施設タイプ別・地域別の稼働率をまとめたものです。
| 施設タイプ/地域 | 2024年4月 客室稼働率 | 2019年同月比 |
|---|---|---|
| 【施設タイプ別】 | ||
| 全体 | 61.3% | -2.3 pt |
| 旅館 | 39.5% | -1.5 pt |
| リゾートホテル | 56.4% | +4.9 pt |
| ビジネスホテル | 71.9% | -4.4 pt |
| シティホテル | 74.5% | +0.4 pt |
| 【主要都道府県別(全体)】 | ||
| 東京都 | 75.3% | -3.5 pt |
| 大阪府 | 78.6% | -5.7 pt |
| 京都府 | 71.3% | -3.6 pt |
| 福岡県 | 75.2% | -4.2 pt |
| 沖縄県 | 63.8% | -2.4 pt |
| 参照:観光庁 宿泊旅行統計調査(令和6年4月・第1次速報値) |
このデータから、いくつかの重要な示唆が得られます。
- 施設タイプによる差: シティホテル(74.5%)やビジネスホテル(71.9%)といった都市型の宿泊施設は高い稼働率を維持している一方、旅館(39.5%)は依然として低い水準にあります。ただし、リゾートホテルはコロナ禍前を上回る稼働率(+4.9ポイント)を記録しており、デスティネーションとしての魅力が回復していることが伺えます。
- 地域による差: 大阪府(78.6%)、東京都(75.3%)、福岡県(75.2%)といった大都市圏は、インバウンド需要の回復を背景に非常に高い稼働率を示しています。
- 回復の質の変化: ビジネスホテルや主要都市では、コロナ禍前と比較して稼働率が若干低い傾向が見られます。これは、インバウンドの回復が進む一方で、ビジネス需要の回復ペースが緩やかであることや、宿泊単価の上昇(ADR増)を優先し、必ずしも稼働率の最大化を追っていないホテルが増えている可能性などが考えられます。
■ 自社の稼働率をどう評価するか
これらの平均値は、あくまで市場全体の「ものさし」です。自社の稼働率を評価する際には、以下の視点を持つことが重要です。
- 同条件での比較: 例えば、自社が京都のシティホテルであれば、全国平均(61.3%)ではなく、京都府の平均(71.3%)や、シティホテル全体の平均(74.5%)と比較することで、より正確な立ち位置を把握できます。
- 競合ホテル(コンペティティブセット)との比較: 最も重要なのは、自社と顧客層や価格帯、立地が類似する直接の競合ホテル群と比較することです。これにより、自社のパフォーマンスが市場内で優れているのか、劣っているのかを明確に判断できます。
- 季節変動の考慮: ホテル業界には明確な繁忙期と閑散期が存在します。自社の稼働率が低い月があっても、それが市場全体の季節的な落ち込みによるものであれば、過度に悲観する必要はありません。重要なのは、その落ち込み幅が競合と比べて大きいかどうかです。
これらの公的データをベンチマークとして活用し、自社の強みと弱みを客観的に分析することが、効果的な稼働率改善策の第一歩となります。
ホテルの稼働率が上がらない主な原因
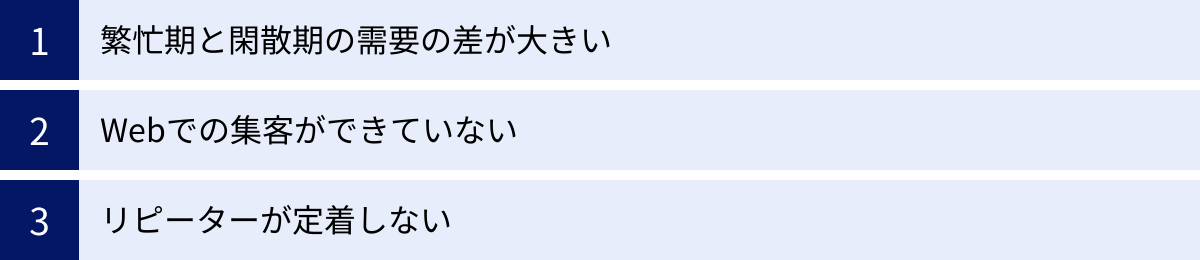
高い稼働率を維持しているホテルがある一方で、多くのホテルが稼働率の伸び悩みに直面しています。その原因は一つではなく、市場環境、集客戦略、顧客満足度など、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。自社の稼働率が上がらない原因を正しく特定することが、的確な対策を講じるための出発点となります。
ここでは、稼働率が低迷するホテルに共通して見られる主な原因を3つの側面に分けて解説します。
繁忙期と閑散期の需要の差が大きい
多くのホテルが抱える構造的な課題が、需要の大きな波、つまり繁忙期と閑散期の稼働率の差が激しいことです。週末や大型連休、夏休みなどの繁忙期には満室に近い稼働を記録するものの、平日の特定の曜日や、1月下旬~2月、6月といった旅行需要が落ち込む閑散期には、稼働率が大幅に低下してしまうケースです。
- 原因:
- レジャー需要への過度な依存: 観光地のホテルやリゾートホテルに多く見られます。土日や休日に宿泊客が集中し、平日の集客に苦戦します。
- 特定のイベントへの依存: 国際会議場や大規模なコンサートホールの近くにあるホテルでは、イベント開催時には高い稼働率を誇りますが、イベントがない期間は閑散としてしまいます。
- 季節性: スキーリゾートやビーチリゾートのように、特定の季節に需要が集中する立地もこの課題を抱えがちです。
この問題を抱えるホテルでは、年間の平均稼働率がなかなか向上しません。例えば、週末の稼働率が95%でも、平日の稼働率が40%であれば、週の平均稼働率は約60%((95%×2日 + 40%×5日) ÷ 7日)に留まってしまいます。
この需要のギャップを放置することは、収益の不安定化に直結します。閑散期には固定費をカバーできず赤字となり、繁忙期の利益でそれを補填するという不安定な経営を強いられることになります。この課題を克服するには、閑散期の需要をいかにして創出するかという視点が不可欠です。
Webでの集客ができていない
現代において、旅行先の情報収集から宿泊予約まで、そのほとんどがWeb(インターネット)上で完結します。このデジタル時代において、Webでの集客力が弱いことは、稼働率が上がらない致命的な原因となり得ます。
- 原因:
- OTA(オンライントラベルエージェント)への過度な依存: じゃらんや楽天トラベルといったOTAは強力な集客ツールですが、これに頼りすぎるといくつかの問題が生じます。まず、売上の10%~15%程度という高い送客手数料が利益を圧迫します。また、OTA上では価格競争が激しく、自社のブランド価値を伝えきれずに値下げ合戦に巻き込まれがちです。自社で集客する力がないため、OTAの集客力に依存せざるを得ない状況に陥ります。
- 魅力に欠ける公式サイト: 自社の公式サイトが、スマートフォンでの表示に最適化されていない(レスポンシブ対応でない)、デザインが古くて魅力が伝わらない、宿泊予約までの手順が複雑で分かりにくい(予約フォームの離脱率が高い)といった問題を抱えているケースです。たとえOTAでホテルに興味を持っても、公式サイトを見て予約をやめてしまう顧客は少なくありません。
- SEO・MEO対策の不足: 潜在顧客が「[地名] ホテル」や「[地名] 観光」といったキーワードで検索した際に、自社の公式サイトが検索結果の上位に表示されない(SEO対策不足)。また、Googleマップでホテルを検索した際に、表示される情報が古かったり、写真が魅力的でなかったり、口コミへの返信がなかったりする(MEO対策不足)。これでは、能動的に情報を探している最も熱心な顧客層を取りこぼしてしまいます。
- SNSの未活用: InstagramやFacebook、X(旧Twitter)といったSNSでの情報発信ができていない、あるいは更新が止まっている状態。SNSは、ホテルの魅力を視覚的に伝え、未来の顧客と関係を築くための重要なプラットフォームですが、これを活用できていないホテルは多くの機会を損失しています。
リピーターが定着しない
安定したホテル経営の基盤となるのは、一度宿泊してくれた顧客に再び選んでもらう「リピート利用」です。一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかる(1:5の法則)と言われています。常に新規顧客を探し続けなければならない状態は、非効率で不安定な経営に繋がります。
- 原因:
- 期待を下回る顧客体験(CX): 予約時の期待値に対して、実際の宿泊体験がそれを下回ってしまったケースです。フロントスタッフの無愛想な対応、客室の清掃不備、写真と実物のギャップ、食事が美味しくなかったなど、顧客が何らかの不満を感じると、再訪の可能性は著しく低下します。「泊まるだけ」以上の特別な価値や感動を提供できていないと、顧客の記憶に残らず、リピートには繋がりません。
- 顧客データの未活用: 多くのホテルでは、宿泊者の名前や連絡先といった情報は取得しているものの、それを次のサービスに活かせていません。顧客の誕生日や記念日、過去の利用履歴(禁煙室を好む、景色の良い高層階を希望した等)といった情報を記録・管理(CRM)し、再訪時にパーソナライズされたおもてなしを提供できていないと、顧客は「その他大勢の一人」として扱われていると感じてしまいます。
- チェックアウト後の関係構築の欠如: 顧客がチェックアウトした瞬間に、ホテルとの関係が途切れてしまっているケースです。感謝を伝えるサンキューメールの送付や、季節のおすすめ情報や会員限定プランを案内するメールマガジンの配信など、顧客との接点を持ち続け、ホテルのことを思い出してもらうための継続的なアプローチがなければ、リピーターは育ちません。
これらの原因は、それぞれ独立しているのではなく、相互に関連しあっています。例えば、Web集客が弱いために価格競争に陥り、利益が圧迫されてサービス品質が低下し、顧客満足度が下がってリピーターが定着しない、という負のスパイラルに陥ることも少なくありません。自社がどの課題を最も深刻に抱えているかを冷静に分析することが、次の一手を見つけるための鍵となります。
ホテルの稼働率を上げるための施策7選
稼働率が上がらない原因を特定したら、次はいよいよ具体的な改善策を実行するフェーズです。ここでは、多くのホテルで効果が実証されている、稼働率を向上させるための7つの施策を、具体的なアクションプランと共に解説します。これらの施策は単独で行うよりも、複数を組み合わせて自社の状況に合わせて実行することで、より大きな効果が期待できます。
① ターゲット層とコンセプトを見直す
全ての施策の土台となるのが、「誰に、どのような価値を提供するホテルなのか」という根幹部分を再定義することです。ターゲットが曖昧なままでは、どのような宿泊プランを作り、どのチャネルで発信すれば良いのかが定まらず、全ての施策が中途半端に終わってしまいます。
- 現状分析(3C分析): まずは自社の置かれた状況を客観的に把握します。
- 自社 (Company): 強み(例:駅近、眺望が良い、食事が自慢)と弱み(例:建物が古い、大浴場がない)は何か。
- 競合 (Competitor): 周辺の競合ホテルはどのようなターゲット層に、どのような価格帯で、何をウリにしているのか。
- 市場 (Customer): 自社のエリアにはどのような需要(ビジネス、レジャー、インバウンド、ファミリー層など)が存在するのか。
- ペルソナの設定: 漠然としたターゲット層ではなく、より具体的な顧客像(ペルソナ)を描きます。例えば「20代女性」ではなく、「平日に有給休暇を使い、一人で近場のホテルに泊まってデジタルデトックスと癒やしを求める28歳の女性会社員。ホテル選びではSNS映えと口コミを重視する」といったレベルまで具体化します。
- コンセプトの明確化: ペルソナに響く、自社ならではの価値提案(コンセプト)を考えます。例えば、「最新設備を揃えたビジネスホテル」から、「出張中でも心身ともにリフレッシュできる、上質な睡眠と健康的な朝食を提供するウェルネスホテル」へとコンセプトを尖らせることで、価格競争から抜け出し、独自の魅力を求める顧客を引きつけることができます。
② 宿泊料金を最適化する(レベニューマネジメント)
レベニューマネジメントとは、需要と供給のバランスを予測し、宿泊料金を動的に変動させることで、収益の最大化を図る科学的な手法です。稼働率と平均客室単価(ADR)の最適なバランスポイントを見つけることが目的です。
- ダイナミックプライシングの実践: 曜日、季節、周辺のイベント、競合ホテルの料金、予約の先行期間(リードタイム)、自社の残室数といった様々なデータを基に、宿泊料金を柔軟に変動させます。
- 需要が高い日: 週末、祝日、近隣でのコンサート開催日などは、料金を高く設定し、ADRを最大化します。
- 需要が低い日: 平日や閑散期には、料金を戦略的に下げて稼働を確保し、RevPARの底割れを防ぎます。
- 価格戦略の多様化: 単に料金を上下させるだけでなく、様々な価格戦略を組み合わせます。
- 早期割引(早割): 早く予約するほどお得になる料金設定で、先の予約を確保し、需要予測の精度を高めます。
- 直前割引(直割): 直前になっても空室がある場合に、限定的な割引で売り切るための料金です。
- 注意点: 安易な値下げはブランド価値を毀損するリスクがあります。価格を下げる場合は、「眺望指定なし」「キャンセル不可」といった条件を付けたプランにするなど、正規料金の価値を下げない工夫が重要です。
③ 魅力的な宿泊プランを作成する
価格だけでなく、「そのホテルに泊まりたい」と思わせる付加価値のある宿泊プランは、稼働率向上の強力な武器となります。先の①で見直したターゲット層のニーズに応えるプランを企画しましょう。
- 閑散期対策プラン:
- ワーケーションプラン: 平日限定で、レイトチェックアウト、高速Wi-Fi、会議スペース利用などをセットにしたプラン。ビジネス客やフリーランスをターゲットにします。
- 地元企業向け研修プラン: 企業の研修やオフサイトミーティング用に、宿泊と会議室、食事をパッケージにしたプランを提案します。
- 体験価値向上プラン:
- 地域連携プラン: 地元の観光施設(水族館、美術館など)の入場券や、伝統工芸の体験教室などをセットにしたプラン。地域全体の魅力を伝えることで、宿泊の動機付けを強化します。
- 美食プラン: 地元の旬の食材をふんだんに使った特別ディナーコース付きプランや、有名シェフとのコラボレーションディナーなど、「食」を目的とした滞在を促します。
- ターゲット特化型プラン:
- 推し活応援プラン: コンサートに参加するファン向けに、DVDプレーヤーの貸し出しや、メンバーカラーのドリンクサービスなどを提供します。
- 記念日プラン: 誕生日や結婚記念日のカップル向けに、ケーキやシャンパン、フラワーアレンジメントなどを提供し、特別な思い出作りをサポートします。
④ OTA(オンライントラベルエージェント)の活用を見直す
OTAは重要な集客チャネルですが、ただ登録しているだけでは手数料を取られるだけの存在になりかねません。OTAを戦略的に「活用」するという視点が重要です。
- OTAミックスの最適化: 特定のOTAに依存するのではなく、複数のOTAに登録し、それぞれの特徴(例:ビジネス客に強い、若者向け、海外ユーザーが多いなど)を理解した上で、プランの出し分けを行います。
- OTA内での露出最大化:
- 写真の質と量を向上させる: プロのカメラマンに依頼するなど、魅力的で高画質な写真を多数掲載します。特にトップページの写真は顧客の第一印象を決定づけます。
- 口コミへの丁寧な返信: 全ての口コミに、定型文ではなく個別具体的に、迅速かつ丁寧に返信します。真摯な姿勢は他の見込み客にも伝わり、信頼性を高めます。
- 特集企画への参加: OTAが実施するキャンペーンや特集企画に積極的に参加し、露出機会を増やします。
- 公式サイトへの誘導: OTAの役割は、あくまで「自社ホテルを知ってもらうための広告塔」と位置づけ、最終的には公式サイトでの予約(直販)に繋げることを目指します。OTAのページに公式サイトの魅力を記載したり、公式サイト限定の特典(ベストレートギャランティなど)を用意したりする工夫が有効です。
⑤ 公式サイトやSNSなどWeb集客を強化する
OTA依存から脱却し、利益率の高い直販比率を高めるためには、自社のWeb集客力を強化することが不可欠です。
- 公式サイトの改善:
- 予約システムの最適化(ブッキングエンジンの導入・見直し): スマートフォンで簡単に予約が完了する、シンプルで分かりやすい予約フローを実現します。多言語・多通貨対応、事前決済機能も必須です。
- コンテンツマーケティング: ホテルの魅力だけでなく、周辺の観光情報、グルメ情報、イベント情報などをブログ記事として発信します。「[地名] 観光」などのキーワードで検索したユーザーを公式サイトに呼び込み、ホテルの認知度を高めます。
- SEO(検索エンジン最適化): 「[地名] ホテル」「[駅名] ビジネスホテル」といった主要なキーワードで、自社サイトがGoogle検索結果の上位に表示されるように内部・外部対策を行います。
- MEO(マップエンジン最適化): Googleビジネスプロフィールを最適化します。正確な情報を登録し、魅力的な写真を多数掲載、口コミを管理し、最新情報を投稿することで、Googleマップ経由の予約を増やします。
- SNSの戦略的活用:
- Instagram: 美しい客室や料理、絶景などの「映える」写真や動画(リール)を投稿し、視覚的に魅力を伝えます。ハッシュタグキャンペーンなども有効です。
- X (旧Twitter) / Facebook: 空室情報や限定プランの告知、イベント情報の発信、フォロワーとのコミュニケーションの場として活用します。
⑥ 口コミの数を増やし評価を高める
今日のホテル選びにおいて、口コミは予約を決定づける最も重要な要素の一つです。良い口コミを増やし、真摯に評価に向き合う姿勢が、信頼と集客に繋がります。
- 口コミ投稿の依頼: 宿泊客が満足していると感じたタイミングで、自然な形で投稿を依頼します。チェックアウト時にサンキューカードと共にQRコードを渡す、チェックアウト後のサンキューメールに口コミサイトへのリンクを記載する、といった方法が効果的です。
- ネガティブな口コミへの対応: ネガティブな口コミは、サービス改善のための貴重なフィードバックです。無視したり、感情的に反論したりせず、まずは謝罪し、事実確認を行い、具体的な改善策や対応を真摯に返信します。この対応は、問題解決能力の高さを示し、他の潜在顧客からの信頼を得る機会にもなります。
- 口コミの分析と活用: 集まった口コミを定期的に分析し、自社の強み(よく褒められる点)と弱み(よく指摘される点)を把握します。これをサービス改善やスタッフ教育に活かすPDCAサイクルを回すことが重要です。
⑦ リピーターを育成するための施策を行う
一度きりの関係で終わらせず、顧客と長期的な関係を築き、「また泊まりたい」と思ってもらうための仕組み作りが、安定した稼働率の基盤を築きます。
- 顧客管理(CRM)の実践: 顧客の宿泊履歴、誕生日、記念日、リクエスト内容(禁煙、高層階希望など)といった情報をデータとして蓄積・管理します。PMS(ホテル管理システム)には、基本的なCRM機能が備わっていることが多いです。
- パーソナライズされたおもてなし: 蓄積したデータを基に、個々の顧客に合わせたサービスを提供します。再訪時に「〇〇様、再びお越しいただきありがとうございます」と名前で挨拶する、以前と同じタイプの部屋を用意する、記念日にささやかなプレゼントを用意するなど、「自分のことを覚えてくれている」という体験は、強い顧客ロイヤルティを生み出します。
- 会員制度・ポイントプログラムの導入: 宿泊料金の割引や、レイトチェックアウト無料、ウェルカムドリンクサービスといった会員限定の特典を用意し、リピート利用のインセンティブを高めます。
- ダイレクトマーケティング: メールマガジンやLINE公式アカウントなどを活用し、顧客との接点を持ち続けます。会員限定の先行予約プランや、誕生日クーポンの送付など、パーソナライズされた情報を届けることで、再訪を効果的に促します。
ホテルの稼働率改善に役立つITシステム
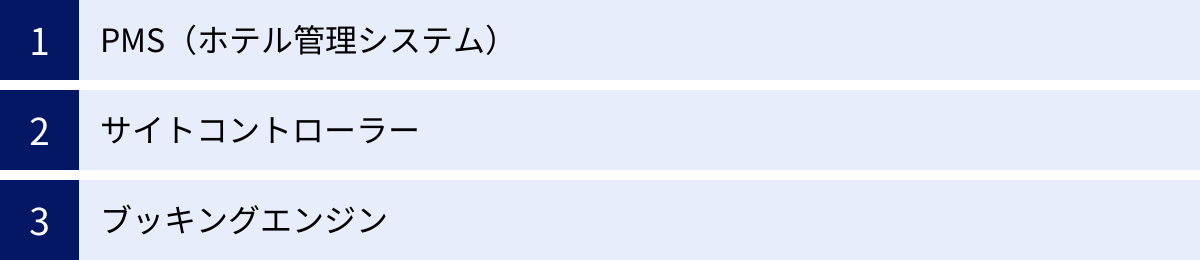
前章で紹介した稼働率向上のための各種施策は、人手だけで行うには限界があります。特に、料金の動的変更、複数サイトの在庫管理、顧客情報の管理といった複雑な業務は、ITシステムを活用することで、効率的かつ正確に実行できるようになります。ここでは、ホテルの稼働率改善に不可欠な代表的な3つのITシステムを紹介します。
PMS(ホテル管理システム)
PMS(Property Management System)は、ホテル運営の心臓部ともいえる基幹システムです。予約管理、客室在庫管理、顧客情報管理(CRM)、会計処理、清掃管理など、フロント業務からバックオフィス業務まで、ホテル運営に関わる情報を一元管理します。
稼働率改善における役割:
- 正確な在庫管理: リアルタイムで正確な空室状況を把握できるため、販売機会の損失やオーバーブッキングを防ぎます。販売停止客室(OOO)の管理も容易になり、正確な稼働率の算出が可能になります。
- データ分析の基盤: 稼働率、ADR、RevPARといった重要指標を自動で集計・分析する機能があります。日別、月別、予約経路別など、様々な角度からデータを可視化し、戦略立案をサポートします。
- 顧客データ(CRM)の蓄積: 宿泊者の予約情報や利用履歴、要望などを一元的に蓄積できます。このデータを活用することで、リピーター育成のためのパーソナライズされたサービス提供が可能になります。
HOTEL SMART
「HOTEL SMART」は、株式会社ilingが提供するクラウド型のPMSです。特に中小規模のホテルや旅館、ホステルなどから高い支持を得ています。シンプルな操作性と、導入のしやすさが特徴です。初期費用や月額費用が無料から始められるプランもあり、コストを抑えてシステムを導入したい施設に適しています。タブレットやスマートフォンからも操作できるため、場所を選ばずに予約状況の確認やフロント業務を行える点も魅力です。(参照:HOTEL SMART公式サイト)
tap
株式会社タップが提供する「tap」は、主に大手ホテルチェーンや大規模なシティホテル、リゾートホテルで豊富な導入実績を持つPMSです。多機能性と高いカスタマイズ性が特徴で、施設の規模や運用形態に合わせて柔軟なシステム構築が可能です。会計システムやレストランのPOSシステムといった他の基幹システムとの連携にも強く、ホテル全体の情報を統合管理したい場合に強みを発揮します。(参照:株式会社タップ公式サイト)
サイトコントローラー
サイトコントローラーは、複数のOTA(じゃらん、楽天トラベルなど)と自社公式サイトの客室在庫、料金、予約情報を一元管理するためのシステムです。現代のホテル運営において、不可欠なツールと言っても過言ではありません。
稼働率改善における役割:
- オーバーブッキングの防止: どこかのサイトで予約が入ると、瞬時に他の全てのサイトの在庫を自動で減らします。これにより、手作業での在庫調整ミスによる二重予約(オーバーブッキング)を確実に防ぎ、顧客からの信頼を維持します。
- 販売機会の最大化: キャンセルが発生した場合も、即座に在庫を全てのサイトに自動で再販売します。これにより、「売れるはずだったのに売れなかった」という販売機会の損失を最小限に抑え、稼働率の向上に直接貢献します。
- レベニューマネジメントの効率化: 各サイトの宿泊料金を一括で変更できるため、ダイナミックプライシングの実践が飛躍的に効率化します。需要に応じて迅速に価格を調整することで、収益の最大化を図れます。
ねっぱん!サイトコントローラー++
株式会社リクルートが提供する「ねっぱん!サイトコントローラー++」は、国内で非常に高いシェアを誇るサイトコントローラーの一つです。対応しているOTAや宿泊予約サイトの数が業界トップクラスに多く、幅広い販路を一元管理できます。PMSとの連携(ブッキングデータ自動取り込み)にも力を入れており、予約管理業務全体の大幅な効率化を実現します。(参照:ねっぱん!サイトコントローラー++公式サイト)
TEMAIRAZU
手間いらず株式会社が提供する「TEMAIRAZU」シリーズも、業界で広く利用されている代表的なサイトコントローラーです。国内のOTAはもちろん、海外の主要なOTAや卸売業者(ホールセラー)との連携にも強く、インバウンド集客に力を入れているホテルにとって強力なツールとなります。複数の施設を運営している場合のグループ一元管理機能も充実しています。(参照:手間いらず株式会社公式サイト)
ブッキングエンジン
ブッキングエンジンは、自社の公式サイトに設置する宿泊予約システムのことです。公式サイトを単なる情報案内の場から、収益を生み出す直接の販売チャネルへと進化させるために不可欠なシステムです。
稼働率改善における役割:
- 直販比率の向上と利益率の改善: 公式サイトからの直接予約(直販)が増えることで、OTAに支払う高額な送客手数料を削減できます。浮いたコストを顧客へのサービス向上や新たな投資に回すことができ、経営の好循環を生み出します。
- 自由なプラン造成とブランディング: OTAのフォーマットに縛られず、自社の魅力を最大限に伝える自由な宿泊プランを作成・販売できます。会員限定プランや公式サイト限定の特典などを提供しやすく、リピーター育成やブランドイメージの向上に繋がります。
- 顧客データの直接取得: 公式サイト経由で予約した顧客のデータは、全て自社の資産となります。この貴重なデータを分析し、メールマガジン配信などのダイレクトマーケティングに活用することで、顧客との継続的な関係を構築できます。
リザーブリンク
株式会社リザーブリンクが提供する「リザーブリンク」は、ホテル・旅館業界に特化した機能を多数搭載したクラウド型の予約システム(ブッキングエンジン)です。施設のブランドイメージに合わせてデザインを柔軟にカスタマイズできる点が強みです。また、セキュリティレベルが高く、クレジットカードの事前決済機能も標準で備えているため、顧客も安心して予約できます。(参照:株式会社リザーブリンク公式サイト)
tripla(トリプラ)
tripla株式会社が提供する「tripla」は、AIチャットボットが一体化した多機能なブッキングエンジンとして知られています。顧客の質問に24時間365日自動で応答するAIチャットボットから、シームレスに予約画面へ誘導できるのが最大の特徴です。多言語対応に優れており、インバウンド顧客の獲得に強みを発揮します。宿泊予約だけでなく、アップセル(部屋のアップグレード提案)やクロスセル(レストラン予約の提案)を促す機能も搭載しており、客単価向上にも貢献します。(参照:tripla株式会社公式サイト)
これらのITシステムを戦略的に導入・活用することで、稼働率向上のための施策をより高いレベルで実行し、持続可能な収益基盤を築くことが可能になります。
まとめ
本記事では、ホテル経営の根幹をなす「客室稼働率(OCC)」について、その基本的な定義から、経営分析に不可欠な関連指標(ADR、RevPAR)、日本の市場平均、そして稼働率を向上させるための具体的な施策まで、網羅的に解説してきました。
改めて要点を振り返ると、以下のようになります。
- 客室稼働率(OCC)は、販売可能な客室のうち、どれだけ販売できたかを示す「量」の指標であり、ホテルの集客力と収益基盤の安定性を示すバロメーターです。
- しかし、稼働率だけでは経営の全体像は見えません。「質」の指標である平均客室単価(ADR)と、両者を掛け合わせた総合的な収益力指標であるRevPARと合わせて分析することが極めて重要です。
- 稼働率が上がらない原因は、多くの場合、「繁忙期と閑散期の需要格差」「Web集客力の弱さ」「リピーターの不足」といった複数の要因が絡み合っています。
- これらの課題を解決し、稼働率を向上させるためには、①ターゲットとコンセプトの見直しを土台とし、②レベニューマネジメントによる料金最適化、③魅力的な宿泊プランの作成、④OTAの戦略的活用、⑤公式サイトやSNSによるWeb集客強化、⑥口コミ評価の向上、そして⑦リピーター育成といった施策を、自社の状況に合わせて複合的に実行することが不可欠です。
そして、これらの多岐にわたる施策を効率的かつ効果的に推進するためには、PMS、サイトコントローラー、ブッキングエンジンといったITシステムの活用が強力な後押しとなります。
ホテルの稼働率を上げる道は、決して平坦ではありません。市場は常に変化し、顧客のニーズも多様化し続けています。しかし、自社の現状をデータに基づいて客観的に分析し、明確な戦略を持って一つひとつの施策を粘り強く実行し、その結果を検証して次のアクションに繋げる、という継続的な改善活動(PDCAサイクル)を回し続けることこそが、持続可能なホテル経営を実現する唯一の道です。
この記事が、あなたのホテルの稼働率を向上させ、より強固な経営基盤を築くための一助となれば幸いです。